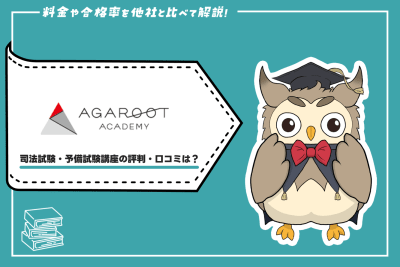司法試験の合格を志すなら大学で「遊べない」のか?在学中の予備合格の実態を徹底解説
更新
「司法試験に挑戦したら、大学生活なんて遊べない…」
そんな噂を耳にして、受験を迷ったり不安を感じたりしていませんか。
確かに、司法試験は合格率が4〜5%台に留まる超難関で、学習時間も2,000時間を超えるともいわれます。しかし数字だけを見て「遊べない」と決めつけてしまうのは早計かもしれません。
本記事では、必要学習時間の実態や在学中に合格した先輩たちのタイムマネジメント術、さらに通信講座を活用して勉強と遊びを両立させる具体策まで、幅広く解説します。
「遊べない」のイメージを覆し、志望校生活を楽しみながら合格を狙うヒントを探っていきましょう。
人気講座ランキング

 もっと見る>
もっと見る>- 特出した実績を持つ最注目のオンライン講座!


- 業界最高の合格者占有率を記録する王道予備校

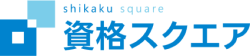 もっと見る>
もっと見る>- リーズナブルかつ高品質なコスパ抜群の講座
このページにはプロモーションが含まれています
司法試験勉強と大学での遊びの両立は可能
司法試験は長丁場ですが、大学生活を犠牲にしなければ合格できないわけではありません。
目標時間を逆算して学習と余暇の時間割を作り、平日と週末にメリハリをつければ、サークルや旅行も楽しみつつ知識を積み上げられます。
ポイントは「すべてを我慢する」のではなく「優先順位を明確にして時間を可視化する」ことです。日々のタスクを朝晩に固定し、週末に一気に復習するリズムを作れば、合格力と大学生活の充実感を両取りできます。
「遊べない」のではなく「遊び方を選ぶ」発想が鍵です。
1日たった3~4時間の勉強でも合格を目指せる
一般的に、司法試験合格の最少学習量は約2,000時間、平均3,000〜4,000時間とされています。仮に最低ラインの2,000時間を2年間で積む場合、年間1,000時間、週20時間が目安になります。
平日は授業後に2時間、土日に各5時間学習すれば到達可能です。週20時間の計画が組めれば、残り100時間超は食事・睡眠・アルバイト・趣味に充てられます。
時間をブロック化し、25分間の集中時間と5分間の休憩を繰り返し行う学習ポモドーロ法や、学習記録アプリを併用すると「3時間でも濃い」学習が実現し、遊びの予定を無理なくキープできます。
通信講座なら学校や遊びとの両立もしやすい
通学型予備校は講義+移動で週15時間以上を拘束されることが珍しくありません。
一方で、通信講座なら講義をスマホで倍速視聴し、自宅・図書館・移動中に演習できるため、同じ内容を半分以下の時間で消化できます。
その結果、サークルやアルバイトの参加機会を削らずに済み、友人と旅行へ行く前後で「講義のDL視聴→到着後に観光」という柔軟なスケジュールも実現可能です。
ただし、自由度の高さは自律心を試す刃でもあります。毎週の到達目標を学習管理アプリで可視化し、未達の日は翌日にリカバリーするルールを徹底すれば、「遊びすぎて時間不足」というリスクを最小化できるでしょう。
司法試験と大学生活の両立について口コミから調査
司法試験と大学生活を両立させるための実態を、実際の口コミを元に調査しました。
合格を目指す学生たちがどのように学業と試験勉強を両立させたのか、また、両立が難しかった学生たちの実際の声を通じて、その工夫や課題を紹介します。
両立に成功し合格した人の声
サークルやアルバイトも行っていたため、出来るだけ効率よく勉強したいと考えていた
短答でも論文でも、自分に合った方法を選び、効率的に学ぶことができたのが合格の秘訣です。私は、長時間机に向かうことが苦手という弱点を受け入れ、隙間時間や音声講座を活用して工夫を重ねました。その結果、司法試験に一発合格することができました。どんな人でも、自分の弱点に向き合い、それに合った方法を選べば、必ず結果を出せると思います。
伊藤塾の講義をしっかりと受けて復習さえすれば、大学での勉強やサークル活動、アルバイトなどとも両立できるとおっしゃっていました。
(一部省略)
アルバイトはカフェでやっています。試験直前期はお休みをもらいましたが、普段は週2〜3日程度働いています。サークル活動をしていない分良い気分転換になりました。また、学校外にも年齢の近い友人を作ることができてよかったです。
多くの合格者が証言するように、司法試験と大学生活の両立は十分に可能です。
ある合格者は「サークルやアルバイトも行っていたため、できるだけ効率よく勉強することを心がけていた」と語っています。
また別の合格者は「短答でも論文でも、自分に合った方法を選び、効率的に学ぶことができたのが合格の秘訣です」と強調しています。
自分の弱点を受け入れ、隙間時間や音声講座を活用するなど工夫を重ねた結果、一発合格を果たしたケースもあります。
また、週2〜3日のカフェでのアルバイトを続けながら合格した方は「試験直前期はお休みをもらいましたが、普段は良い気分転換になりました」と振り返っています。
適切な予備校の活用と自分のペースに合わせた学習法を見つけることで、大学生活を犠牲にすることなく司法試験合格への道を切り開くことができるのです。
学習に追われ両立が難しかった人も多い
学校に泊まり込みで勉強したり、眠くなったら廊下を歩きながら暗記
1日ストップウォッチで10時間測る生活を1000日やってようやく合格
伊藤塾の自習室に朝7時から夜10時まで籠り、“ポークの缶詰め”状態だった
一方で、合格者の中には「1日10時間を1000日」「朝7時から夜10時まで自習室に籠る」「学校に泊まり込みで暗記する」など、生活の大半を勉強に振り切った人も少なくありません。
令和6年司法試験の最終合格率は42.13%と依然4割強に留まり、得点競争が激しい直前期には遊ぶ余地がなくなるケースが現実にあります。こうした「缶詰め」期間は心身への負荷こそ大きいものの短期で得点力を底上げできる強みもあります。
自由時間を確保したい学生は試験年の春休み〜GW以降の約3か月だけ集中的に導入し、終了後に必ず休養を取るなどセルフケアを徹底する、といった戦略を取るようにすると良いでしょう。
在学中に司法試験に受かるメリット
在学中に司法試験に合格するメリットとして、キャリアを前倒しする効果がある点が挙げられます。
学業と並行して試験を突破することで、早期にキャリアをスタートできるだけでなく、将来の進路選択にも大きな影響を与える可能性があります。ここでは、その具体的な利点を見ていきましょう。
早くから実務を経験できる
卒業と同時に司法修習入りすれば、25歳前後で弁護士登録が可能です。法廷での期日対応や企業法務のデューデリジェンスに主体的に関われるため、経験曲線を急速に伸ばせます。
若いうちに交渉術や訴訟戦略を習得できることは、30代でパートナー弁護士やインハウス上級職に昇進する際に大きな武器となります。
さらに扱う案件の単価も年次に比例して上がりやすく、同世代より早い段階で高付加価値業務を担えるため、年収面でも長期的な優位性を確保できます。
予備試験への合格は就活でも評価される
予備試験合格は、卓越した法律知識だけでなく計画遂行力やストレス耐性を示す強力な指標となります。
特に、外資系コンサル・投資銀行・総合商社などでは「法務×ビジネス」の即戦力として高評価され、選考フロー短縮やリファラル枠での面接オファーが届くケースもあります。
また、内定時に待遇交渉で優位に立てるほか、入社後も新人研修段階から法務プロジェクトにアサインされやすく、組織内での差別化が容易です。
資格取得に裏付けられた専門性が、経営陣へのプレゼンや社外折衝で説得力を高め、早期にリーダーポジションを任される土台となるのです。
人気講座ランキング

 もっと見る>
もっと見る>- 特出した実績を持つ最注目のオンライン講座!


- 業界最高の合格者占有率を記録する王道予備校

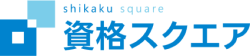 もっと見る>
もっと見る>- リーズナブルかつ高品質なコスパ抜群の講座
法科大学院への進学も選択肢の一つ
大学生活を最大限楽しみつつ法律家を目指すなら、ロースクール進学は堅実なルートです。
法学未修コースなら基礎から体系的に学べ、3年間で判例・法改正・模擬裁判を段階的に習得できます。
演習中心のカリキュラムは司法試験と直結しており、在学生ルートの合格率は令和6年実績で約55%と高水準です。
ただし学費は年間約150万円、3年間で450万円+生活費が必要で、奨学金や教育ローンの検討は必須です。
また、課題提出やゼミ討論は週10コマを超えることもあり、自由時間は予備試験組より少ない点も留意が必要です。
そのため、学部時代に単位を先取りし、3年次からロースクール準備を始めることで、遊び時間と学習時間のバランスが取りやすくなります。
少しでも自分の時間を確保するなら通信講座の活用がおすすめ
通信講座は「移動ゼロ」「倍速視聴」「AI演習」により、学習効率を最大化しつつ自由時間を守れる仕組みが整っています。
動画教材をスマホにダウンロードすれば、通学電車やアルバイトの休憩中でもインプットが進み、1日3〜4時間の学習目標を隙間時間だけで達成できます。
また、学習管理アプリが進捗を可視化し遅延を自動警告してくれるため、自律心を保ちやすいのもメリットです。
「遊びゼロか勉強ゼロか」という二項対立を解消し、大学イベントや友人との旅行を楽しみながら確実に合格ラインへ近づけます。
アガルート

アガルートは短期合格に特化した「逆算カリキュラム」が特徴です。
重要論点に学習を絞ることで平均学習時間を圧縮することができ、講義はすべて倍速対応、スマホ1台で視聴・過去問演習・質問投稿が完結します。
また、定期カウンセリングでは講師が学習ログを分析し、未達要因を具体的にフィードバックしてくれる点も強みです。
価格は10万円台からと通学予備校の半額以下ながら、2024年度の予備試験合格率は全国平均の1.3倍と実績も十分です。さらに、対象講座を受講後に予備試験に合格した場合、受講料の全額が返金される全額返金制度などもあり、コスパを求める学生に最適です。
項目 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
価格 |
・学習経験がない方向け: 498,000〜1,180,000円(税抜) ・学習経験がある方向け: 295,920〜658,000円(税抜)
295,920〜808,000円(税抜)
295,920〜658,000円(税抜) | 業界水準の価格設定(相場は約100万円)。また、10回分割手数料無料。 |
教材 | ・フルカラーテキスト ・デジタルブック対応 ・オリジナル教材 ・映像講義 ・論点マップ ・判例索引・事項索引 ・本試験出題実績付き ・『総合講義1問1答』無料プレゼント | 試験で問われる知識に絞り込んだ内容で、科目ごとに効率的に学習できる構成になっている。 |
講師 | ・工藤北斗氏(代表取締役) ・業界最多20名以上のプロ講師陣 | 旧司法試験合格者やアルバイト講師は不在。全員が新司法試験合格者で、最新の試験傾向に完全対応している。 |
合格実績 | ・令和6年(2024年)司法試験合格者:602名 ・合格者占有率:37.8% ・司法試験合格率:42.1% ・793名以上の合格者輩出 | 司法試験合格者の約4割がアガルート受講生。 |
サポート体制 | ・パーソナルコーチング(月1回) ・業界最多206問の添削 ・バーチャル校舎 ・口頭論文添削(完全予約制) ・質問制度(400回まで) ・オフィスアワー ・オンライン質問サービス「KIKERUKUN」 ・オンライン自習室 | プロ講師が担任としてマンツーマン指導をしてくれ、リアルタイムでの質問対応も受け付けている。 |
特徴/学習法 | ・短期合格を目指す効率的学習 ・バーチャル校舎での双方向コミュニケーション ・段階的な5ステップ学習法 ・論文過去問重視のカリキュラム ・担任制による個別指導 ・倍速再生機能 ・マルチデバイス対応 | 「総合講義300」で基礎知識を習得し、「論文答案の書き方講座」で論文作成の基礎を学習する。 |
キャンペーン | ・全額返金制度(合格特典) ・他資格試験合格者割(10%OFF/5%OFF) ・5%OFF割引 ・予備試験最短合格カリキュラム受講生限定割引(30%OFF) ・教育クレジットローン(分割手数料無料) ・高校生・大学生向け無料講座 | 対象カリキュラム受講後に予備試験合格で全額返金(実質0円)制度あり。 |
アガルートの司法試験・予備試験講座について詳しく知りたい方はこちら。
資格スクエア

資格スクエアはAI問題演習未来問が人気で、過去問データを機械学習させた予測問題が出題される点が大きな差別化ポイントです。
理解度に応じて最適な論点を提示するため、苦手科目の復習に時間を割きすぎるリスクを回避できます。
価格は業界最安水準の7万円台からで、学割プランを活用すればさらなるコスト削減も可能となっています。また、学習スケジューラが週次・月次の進捗を自動集計し、遅れが出た際にはリスケ案を通知してくれるため、旅行やゼミ合宿と学習を両立しやすい環境が整っています。
項目 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
価格 |
| スタディングの次に安い水準でコスパ良好。また、単科講座の組み合わせも可能。 |
教材 | ・オンラインレジュメ ・デジタルテキスト ・製本テキスト(オプション) ・厳選された過去問題集 ・短答攻略クエスト(アプリ) ・約540時間の動画講義 | オンラインレジュメは加筆・修正・マーカー・付箋機能で自由に編集可能。アウトプット学習を重視した教材構成なのが特徴。 |
講師 | ・樋田早紀講師(予備試験短答1位) ・加藤喬講師(司法試験担当) ・小野講師(フォローアップ担当) など | 加藤講師は労働法1位、論文36位の成績で合格しているなど、実績経験共に豊富な講師による的確な指導を受けられる。 |
合格実績 | ・令和5年予備試験合格率:25.9% ・受講生合格率は全国平均の7.24倍(令和5年度) ・論文式試験1位合格者を輩出 ・2022年には22.8%の合格率を記録 | 2019年度試験では論文式1位の合格者を輩出し、学生から社会人まで幅広い合格者を輩出している。 |
サポート体制 | ・業界最多275通の論文添削 ・月1回の電話学習相談(15分) ・ワンクリック質問(200回) ・合格者による質問回答 ・学習習慣化プログラム ・合格ロードマップ&ステップ学習シート | 動画講義画面のボタンでワンクリック質問が可能。「どの科目の」「どの学習過程を」「どの順番で」進めるべきかを明確化してくれる。 |
特徴/学習法 | ・「最短」にこだわったカリキュラム ・アウトプット重視の学習法 ・スモールステップ学習 ・短時間で効率的な講義 ・合格から逆算した学習設計 ・初学者向け整理されたカリキュラム | とにかく早く1周して、全体感をつかむことを大事にしており、「アウトプット」に素早く移行できるよう基礎講義はコンパクト設計になっている。 |
キャンペーン | ・他校乗り換え割引(10%OFF) ・他資格合格者支援制度(10,000円引き) ・再受講割引(50%OFF) ・予備試験合格特典(20万円相当の司法試験講座) | 予備試験に合格すると司法試験講座の手当が受けられる。定期的なキャンペーンを実施している。 |
資格スクエアの司法試験・予備試験講座について詳しく知りたい方はこちら。
司法試験勉強は通信講座?予備校?
学習スタイルを誤ると時間もお金も浪費しがちです。そのため、両者のメリット・デメリットを正しく理解しておくことが大事です。
ここでは、通信講座と予備校の向き・不向きを整理し、自分に合う環境選びの指針を示していきます。
通信講座の受講がおすすめな人
時間と場所を自らコントロールし、学習管理アプリやToDoリストで日々の進捗を可視化できるタイプの方は通信講座がおすすめでしょう。
移動中に講義を倍速視聴し、カフェでAI演習をこなせば、週20時間の学習枠を隙間時間だけで達成し、夜はサークル活動やアルバイトに集中できます。
また、費用が予備校の半額以下で済むため、浮いた資金を留学や資格追加受験に投資するなど、大学生活の選択肢を広げられる点も大きなメリットです。
予備校の受講がおすすめな人
一方で、計画立案が苦手で学習ペースを外部に管理してほしい人、講師や仲間とディスカッションしながら深く理解を進めたい人は通学予備校が適しています。
自習室やゼミ、個別添削といった環境が整っており、論文答案の質を短期間で底上げできます。
ただし、授業出席と移動で1日7〜10時間を拘束されるケースが多く、サークルや旅行との両立は難しくなるため、学習優先フェーズだと割り切れるかがポイントです。
予備校なら伊藤塾がおすすめ
伊藤塾は論文添削・口述模試・進路相談までワンストップで提供する最大手の予備校です。
講師との個別面談では弱点科目の対策だけでなく、精神面のケアや日々の学習計画まで具体的にサポートしてくれるのが特徴です。
また、OB・OGネットワークが厚く、実務家講演や法律事務所見学会も充実しているため、学習モチベーションを保ちながらキャリア観を深められる環境が整っています。
費用は高めですが、総合的なバックアップを求める受験生にとって魅力的といえます。
人気講座ランキング

 もっと見る>
もっと見る>- 特出した実績を持つ最注目のオンライン講座!


- 業界最高の合格者占有率を記録する王道予備校

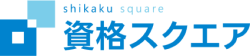 もっと見る>
もっと見る>- リーズナブルかつ高品質なコスパ抜群の講座
通信講座を活用して勉強と遊びを両立しよう
司法試験合格と大学生活の充実は二者択一ではありません。
通信講座の時短機能と学習管理アプリを駆使し、週20時間の学習枠を死守すれば、サークル活動や旅行も存分に楽しめます。
重要なのは「計画→実行→振り返り」のPDCAサイクルを高速で回し、自分に合った最適バランスを獲得することです。
遊びの予定を罪悪感なく入れつつ、学習の質は犠牲にしない――このスタンスが長い受験生活を乗り切る最大のコツになります。