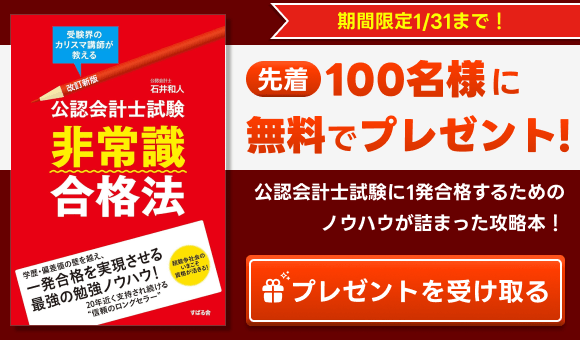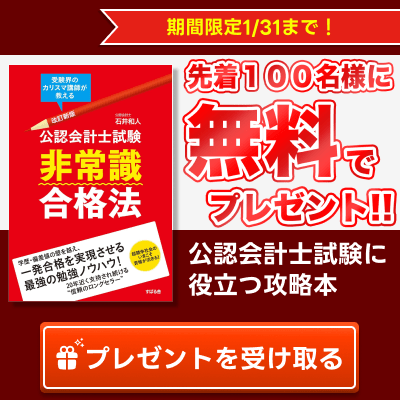公認会計士試験の難易度はどのくらい?試験が難しい理由やその合格率を徹底解説
更新
公認会計士試験は、その高度な難易度から難関国家資格と評されています。
本記事では、試験がいかに困難であるか、その理由、そして合格率について説明していきます。
単なる知識の暗記では通用せず、専門知識に基づく深い理解力と洞察力が必要とされるこの試験の実態に迫りましょう。
人気講座ランキング

 もっと見る>
もっと見る>- 合格者占有率60%以上の定番講座!

 もっと見る>
もっと見る>- 抜群の安心感を誇る大手資格予備校!



- ベテラン講師による満足度の高い講義
このページにはプロモーションが含まれています
公認会計士試験の難易度は高い

公認会計士試験は、他の資格と比べても非常に難しい試験です。実際、合格率は約11.2%と決して高くありません。しかし、これは難関資格と呼ばれる社会保険労務士試験の合格率8%を上回っています。
つまり、公認会計士は確かに難関資格の部類に入りますが、きちんと対策を立てて臨めば十分に合格可能な難易度であるといえます。難関ではあるものの、適切な勉強方法と努力次第では夢は叶えられる資格だと位置付けられるでしょう。
公認会計士の難易度を偏差値にすると
公認会計士の偏差値は65~70
公認会計士試験の難易度は、偏差値で65〜70程度と言われています。大学で例えるならば東京大学を始めとした旧帝国大並みです。
しかしその一方で、偏差値が高いからといって一般の人が受験できないような過酷な試験ではありません。確かに難しいですが、継続的な努力を重ねることで十分に合格を勝ち取ることができる試験なのです。
公認会計士の難易度は医師・弁護士並み
公認会計士は医師・弁護士と並んで「三大国家資格」と呼ばれることもあります。これらの資格試験では極めて高度な専門知識が要求され、並大抵の努力だけでは合格できません。
その分、これらの資格を取得すると、専門性が高く重要な社会的責務を果たせる人間であると証明されます。その責任の重さや資格取得の難易度の高さから、年収も高い傾向にあります。
公認会計士試験は科目数が多く範囲が広い
公認会計士試験は、科目数が多岐にわたり、試験範囲が広いです。試験は短答式と論文式の2形式で行われ、合計で約9科目を学ぶ必要があります。
短答式試験は会計、税法、監査の基本原則と高度な理論を問われます。
さらに、論文式試験では具体的事例に基づき、会計原則や監査理論の深い理解力が試されます。
公認会計士試験の受験資格は
公認会計士試験は非常に難しい試験とされていますが、受験資格には制限がなく、誰でも挑戦することができます。
これにより、多様な視点と経験を持つ公認会計士の増加を見込むことができますが、正式に公認会計士になるためには、4科目の試験に合格した後2年間の研修が必要であり、高度な専門知識と優れた判断力が求められます。
受験資格の取得は容易ですが、公認会計士として活躍するための関門は高いのが実情です。
公認会計士試験の合格が難しい理由

公認会計士の合格率は1次試験で15~30%程度と非常に低く、その高い難易度は広範囲にわたる専門的な試験科目と、合格に向けて必要となる莫大な学習時間が要因となっています。
試験科目は会計学、金融論、商法など多岐に渡り、一科目ずつ300~400時間もの学習時間を要します。
これは大学生の1学期の学習時間の3~5倍に相当します。さらに受験資格がないため、幅広い層の受験生が参加し、競争率を高めています。
試験の受験科目数が多く出題範囲が広い
公認会計士試験の受験科目は多岐にわたります。短答式試験では財務会計論、管理会計論、監査論、企業法の4科目が出題されます。
一方、論文式試験では会計学、監査論、租税法、企業法に加え、選択科目として経営学、経済学、民法、統計学のうち1科目が課されます。
このように多くの科目を学ばなければならないため、学習範囲が広く、その分難易度が高い試験となっています。
さらに、それぞれの科目ごとに合格を判定する制度ではなく、全科目に同時に合格する必要があることも難易度を高める要因です。働きながらこれだけの範囲を学ぶとなると、相応の努力が必要であることが理解できるでしょう。
科目ごとの合格基準が高い
公認会計士試験の合格基準は高く、短答式試験では総点数の70%、論文式試験では得点比率の52%が基準です。
例えば短答式試験では500点満点中350点が合格ラインですが、1科目でも得点比率が40%未満だと不合格になる可能性があります。
そのため、全科目で一定以上の点数を取る必要があります。出題範囲が広く、科目ごとに異なる内容を習得する必要があるため、合格率が低くなる要因となっています。
科目合格制度が存在しない
公認会計士試験には科目合格制度がありません。
これは一度合格基準に達した科目が次回以降の受験で免除される制度で、税理士試験などで導入されています。
税理士試験では一度合格した科目は永久に合格扱いとなりますが、公認会計士試験では論文式試験の一部科目にのみ科目免除資格があり、短答式試験には適用されません。
そのため、短答式試験では一度の試験で全科目の合格ラインを満たさなければならず、これが合格率の低さの一因となっています。
勉強期間は最短でも1年以上必要
公認会計士試験は、監査の専門家としての高度な知識と理解が求められるため、合格に向けて長期間の学習が必要とされています。
試験科目の内容が専門的で難解なことから、3,000時間から6,000時間もの長期的な学習時間が必要とされています。1日10時間の学習でも最短で1.5年から2年、5時間の場合は4年程度の期間を要します。
個人の学習ペースによって変わりますが、少なくとも1年は学習に専念しなければなりません。
公認会計士試験の合格率
公認会計士の合格率
公認会計士試験は、日本の厳格な資格制度が導入されており、難易度が非常に高いことが特徴です。
上記の公認会計士の合格率をまとめた表からもわかる通り、合格率は10%前後の低水準で推移し、試験に合格するには約3,500時間に及ぶ学習が必要とされています。
公認会計士試験の合格基準点
公認会計士試験は、短答式試験と論文式試験の両方で一定の基準を満たす必要があります。
先述の通り短答式試験は4科目の合計点で70%以上、論文式試験は5科目の合計点で52%超えることが求められます。
注意すべき点は、どちらの試験でも一科目でも40%に満たない場合は不合格になる可能性があることです。そのため、合格に向けては、出題頻度の高い重要範囲に焦点を当てた効率的な学習が重要です。
公認会計士合格までに必要な勉強時間
公認会計士試験に合格するためには、一般的に4,000時間以上の勉強が必要とされています。資格取得には最低でも2年は必要で、それ以上かかる場合も少なくありません。2年間の計画で行くと、1日の勉強時間は5時間半以上が必要です。
スキルアップ研究所の調査によると、勉強時間には個人差が大きいことがわかっています。以下はその調査結果を表にしたものです。
勉強時間 | 人数 |
|---|---|
2000時間未満 | 2 |
2000~4000時間 | 2 |
4000~6000時間 | 1 |
6000時間以上 | 1 |
合計 | 6 |
この調査結果からもわかるように、2000時間未満で合格する人もいれば、6000時間以上を要する人もいます。勉強時間には個人差があるため、自分に合った計画を立てて、着実に学習を進めることが重要です。
公認会計士試験の合格者層
2024年の公認会計士試験における願書提出者、論文式受験者、合格者の年代別データを以下の表にまとめました。
| 年齢 | 願書提出者(人) | 論文式受験者(人) | 合格者(人) | 合格者構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 442 | 41 | 18 | 1.1 |
20~24歳 | 10,029 | 2,082 | 986 | 61.5 |
25~29歳 | 5,341 | 1,156 | 418 | 26.1 |
30~34歳 | 2,425 | 468 | 123 | 7.7 |
35~39歳 | 1,292 | 250 | 42 | 2.6 |
40~44歳 | 834 | 151 | 10 | 0.6 |
45~49歳 | 496 | 72 | 2 | 0.1 |
50~54歳 | 297 | 64 | 4 | 0.2 |
55~59歳 | 192 | 34 | 0 | 0.0 |
60~64歳 | 113 | 20 | 0 | 0.0 |
65歳以上 | 112 | 16 | 0 | 0.0 |
合計 | 21,573 | 4,354 | 1,603 | 100 |
願書提出者で最も割合が多いのは20代で71.2%、次に多いのは30代で17.2%です。
論文式受験者でも同様に、最も割合が多いのは20代で74.4%、次いで30代が16.5%となっています。最終的な合格者の割合は、20代が87.6%、次が30代で10.3%です。
これらのデータから、公認会計士試験を目指す人の多くが20代で、公認会計士試験の合格者平均年齢も20代が中心であると考えられます。
公認会計士の国家資格難易度ランキング
以下は他の資格と合格に必要な学習時間・合格率を考慮したランキングです。
順位 | 資格名 | ジャンル | 参考学習時間 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
1位 | 司法試験・予備試験 | 法律関係 | 2,000~10,000時間 | 4%前後 |
2位 | 司法試験 | 法律関係 | 3,000~6,000時間 | 30~45% |
3位 | 医師国家資格 | 医療関係 | 6年間 | 90%前後 |
4位 | 公認会計士 | 会計・経営・労務関係 | 3,000~5,000時間 | 7~11% |
5位 | 不動産鑑定士 | 不動産・建築関係 | 2,000~3,700時間 | 5~6% |
6位 | 司法書士 | 法律関係 | 3,000時間 | 4~5% |
7位 | 弁理士 | 法律関係 | 3,000時間 | 6~9% |
8位 | 税理士 | 会計・経営・労務関係 | 2,000~3,000時間 | 15~20% |
公認会計士は、必要な学習時間と合格率の観点から見て4位に位置しています。
ここからは他の資格と比較した際の公認会計士の難易度についてみていきましょう。
他の会計・経営系資格と難易度を比較
税理士
項目 | 合格率(令和6年) |
|---|---|
公認会計士 | 7.4% |
税理士 | 16.6% |
税理士と公認会計士を比較すると、一般的に公認会計士の方が難易度が高いと言われています。まず、公認会計士資格を取得することで税理士業務にも携われるため、別途税理士登録が必要ですが、資格の幅が広がります。
また、税理士試験には「有効期限なしの科目合格制度」があり、地道に時間をかければ合格が可能です。
さらに、公認会計士試験の方が上位資格と認識されており、受験者層のレベルが高いです。税理士試験の最終合格率は毎年15%~20%と公認会計士試験に比べて高い傾向にあります。
そのため、早期に経理・会計業界の資格を取得し、働くチャンスを得たいと考える受験生は、公認会計士試験よりも難易度の低い税理士試験を目指すことで、その可能性を高められるでしょう。
簿記1級
資格名 | 公認会計士 | 簿記1級 |
|---|---|---|
勉強時間 | 4,000時間 | 800~2,000時間 |
合格率 | 10%前後 | 10%前後 |
偏差値 | 74 | 64~67前後 |
試験科目 | 9科目 | 4科目 |
受験資格 | 特になし | 特になし |
簿記1級の資格取得者は、専門性を活かして企業の会計や経理部門で活躍することが多くなります。日常業務では、企業の資金調達や物品管理、取引の正確な記録作成を担当します。
上記の資格取得の難易度を比べた表を見てみると、公認会計士と簿記1級では内容の範囲や学習時間に大きな開きがあります。簿記1級取得のために必要な勉強時間は800~2,000時間程度です。
合格率は両者とも10%前後と厳しいものの、偏差値で見ると公認会計士が74、簿記1級が64~67とされています。
試験科目数も異なり、公認会計士は9科目、簿記1級は4科目です。公認会計士試験には複雑な計算問題や高度な理論が出題されるのに対し、簿記1級は基礎的な内容が中心です。総合的に見ると、公認会計士試験の方が難易度が高いと言えるでしょう。
社労士
項目 | 合格率(令和6年) |
|---|---|
公認会計士 | 7.4% |
社労士 | 6.9% |
社労士と公認会計士は、いずれも非常に難易度の高い国家資格です。社労士試験の合格率は6-7%と、極めて厳しいことがわかります。2024年度の合格率も6.9%と、かなり低い数字となっていました。
社労士試験の方がやや難しいとされていますが、求められる知識やスキルが異なるため、受験者の適性次第でどちらが難しいかは変わってきます。
司法書士
項目 | 合格率(令和6年) |
|---|---|
公認会計士 | 7.4% |
司法書士 | 5.3% |
公認会計士試験と司法書士試験の難易度を比較すると、公認会計士試験の方がハードルが低いと言えます。
公認会計士試験は年2回受験できる上、一部合格による免除制度があります。また合格後の就職・転職市場でも需要が高いため、比較的早期に業界で活躍できる可能性があります。
一方、司法書士試験は年1回の一発勝負で、そのような制度がありません。したがって、資格取得までのハードルを下げたい場合や、受験中から得た知識を活用したい場合は、公認会計士試験の方が適していると考えられます。
三大国家資格と公認会計士の難易度比較
日本には多くの国家資格がありますが、特に医師、弁護士、公認会計士の資格は非常に難しいと言われています。それぞれ専門的な知識と対応力が必要とされ、独自の過程を経て資格を取得するため、難易度が高いのです。
以下ではそんな三大国家資格と公認会計士の難易度について比較していきます。
弁護士
項目 | 合格率(令和6年) |
|---|---|
公認会計士 | 7.4% |
弁護士(司法試験) | 42.1% |
弁護士(予備試験) | 3.6%(令和5年度) |
司法試験は合格率だけを見ると公認会計士試験より簡単なように見えますが、実際には受験資格の取得から広範囲にわたる高度な試験内容まで様々な段階で高い壁があります。
司法試験を受けるためには予備試験の合格か法科大学院修了が必須です。その予備試験が合格率3%~4%とかなりの難関です。同じ法律系の資格である司法書士試験よりも難易度が高く、試験範囲も広いと言われています。したがって合格率だけでなく、受験そのものが困難な挑戦を伴う資格試験だと言えます。
このことから公認会計士試験に比べると、司法試験の方が難易度が高い資格試験であると考えられます。
医師
医師や弁護士は試験前に一定の知識を保有している状態が整えられています。
一方で、専門学校や独学を含めて誰でも受験できる公認会計士試験は、「誰でも公認会計士試験に挑戦できる」というメリットに惹かれて、公認会計士への転職を検討している人も少なくありません。
もちろん、誰でも受験できるからといって簡単に合格できるわけではありません。どの程度まで勉強して知識をつけているのかも人それぞれです。
医師や弁護士の試験と比較して、公認会計士は誰にでも受験するチャンスが与えられているため、勉強の度合いによって試験の難易度が変わる実情があります。
東大入試と比べるとどちらが難しい?
公認会計士試験と東京大学入試の難易度を一概に比較することは困難です。公認会計士試験は短時間で合格する人も少なからずいます。
東大入試の社会的認知度や競争率の高さを考慮すると、東大入試の方が公認会計士試験よりも難易度が高いと言えるでしょう。
公認会計士試験の科目
会計学
公認会計士試験には「会計学」という科目があり、これは財務会計論と管理会計論の2つの領域から構成されています。財務会計論は、企業の業績や財務状況を数値化し、投資家や債権者などの外部関係者に開示することが目的です。
一方、管理会計論は、社内の管理者に対して事業活動を効率的に行うための経営情報を提供することを目指しています。つまり、財務会計論は外部報告、管理会計論は内部管理を担っていますが、どちらも企業の業績測定や価値創造をサポートする共通の目的があります。
異なる視点から会計情報を扱いながらも、企業活動を適切に理解・評価するためには両領域の知識が不可欠とされています。論文式の試験では、この2つの領域を融合した問題が出題されます。そのため、それぞれの理論を熟知し、企業活動との関わりを理解する必要があります。
財務会計論
「財務会計論」は企業の財政状況や経営成績を適切に表す重要な研究分野です。この分野は、企業の取引を正確に記録・計算する「簿記」と、会計処理の基準や原則を理解する「財務諸表論」の二つに大別されます。
簿記は、企業活動を適切に記録し、資金状況や業績を把握するための透明性の高い手続きです。簿記の手順やルールを学ぶことは、単に問題演習をするだけでなく、その意義を理解する上で重要です。
一方、財務諸表論は、会計基準や理論的背景、会計理論間の対立点などを学びます。これにより、会計処理の根拠となる原則や基準を深く理解することができます。
このように、簿記と財務諸表論は表裏一体の関係にあり、両者を継続的に学習し、理論と実践を関連付けることで、財務会計に関する総合的な理解が深まります。
管理会計論
企業経営において、経営者が将来の企業のあり方を計画したり、その成果が期待通りに進んでいるかを管理するための情報が必要です。
そこで、管理会計論では、このような情報の収集・分析・報告を行うための、原価計算を中心とした会計システムについて学びます。
管理会計論においては、まずは計算方法をマスターし、それから関連する理論をしっかりと押さえることが重要です。
租税法
会計学における重要な科目の一つである「租税法」では、様々な税法や税規則の基本的な理解と適切な適用力が求められます。会計士として専門的な業務を行う上では、法人税法の正確な適用と計算力が不可欠です。
法人税法に加え、所得税法や消費税法などの理解も必要とされます。これらの税制度は企業経営や個人生活に深く関わっており、それぞれ異なる観点から税金の計算や納税義務を定めています。
理論や基礎的な計算問題に加え、他の会計科目との関連性も重視されます。つまり、会計全体を理解し攻略することで、租税法という一部の科目も理解し、結果的に攻略できるのです。
監査論
公認会計士は、企業の財務諸表を監査する重要な役割を担っています。「監査論」という科目では、財務諸表監査に関する幅広い規則とその背景にある理由を学びます。
初級者は、専門用語に惑わされることなく、各規則の意味と存在理由を深く理解することが重要です。
ルールが必要とされる理由を明確に把握し、適切に適用できるようになれば、実際の監査業務に役立てることができるでしょう。
企業法
企業活動を円滑に進めるためには、会社法をはじめとする企業法の理解が欠かせません。企業は社会との密接な関係の中で活動する組織体であり、その形態、運営方法、事業内容などについて、法的な枠組みが定められています。
中でも株式会社に関するルールは重要であり、設立から消滅に至るまでの全過程で法的規範が存在します。また商法や金融商品取引法など、他の法律との関連性も無視できません。
企業法の学習においては、法律特有の表現方法への適応が重要であり条文の精査を通じて法律の構造や要素を理解することが肝心です。
選択科目
公認会計士の資格を取得するには、決められた科目の試験に合格する必要があります。試験科目は分野ごとに区分されており、一部の科目は受験者が自由に選択できるようになっています。
選択科目とは、「経済学」「商法」「財務諸表論」の3科目から2科目を選んで受験することを指します。選択科目の魅力は、自分の興味や将来のキャリアに合わせて科目を選べる点にあります。
以下では、そんな選択科目の詳細についてみていきましょう。
民法
民法は、私たちの日常生活で経験する契約や取引などを規律する法律であり、単に知識を詰め込むだけでなく、法条文の理解と解釈、学説の対立点について深く理解することが求められます。
事例の分析を通して、法的問題点の特定、主張、根拠を積極的に身につける必要があります。関連する法条文の把握と内容の正確な理解が重要となり、条文を適切に引用し適用する能力が法的問題解決の基礎となるため、民法の学習において欠かせない技能です。
経営学
経営学は、企業の運営方法や存在意義を探求する学問です。経営戦略、モチベーション理論、リーダーシップ、ガバナンス、ファイナンスなど、様々な側面を網羅しています。これらの知見を活用し、状況に応じた戦略を立案することが重要視されています。
現代の経営学は時事的な課題にも注目し、新しい動向を常に評価しています。
経営学の学習では、基本的な理論を適切に理解し全体像を構築することが大切です。概観しつつ、重要なポイントを押さえる必要があります。
特にファイナンス理論は、企業の財務や投資の側面を扱うため、学習者間で理解度に違いが出やすい分野で、重点的な対策が必要です。
統計学
公認会計士試験の統計学科目では、データの特性を理解し、確率を活用してデータから事実や予測を導き出す重要な手法を学びます。
具体的には、記述統計でデータの特性を抽出する方法、確率による予測、推測統計による限られたデータからの全体像の予測、相関・回帰分析によるデータ間の関連性の数値化と予測への活用などが扱われます。
この科目は高校文系数学程度の内容で、中学数学の理解があれば短期間で対応可能な難易度となっています。
経済学
経済学は、企業や個人から国家や世界規模まで、さまざまな経済活動を分析する学問です。この分析は、現実の経済をモデル化したものに基づいて行われます。
経済学には、ミクロ経済学とマクロ経済学という2つの視点があります。ミクロ経済学は、消費者や企業に焦点を当て、特定の財やサービスの需給バランスを分析します。一方、マクロ経済学は国全体や世界全体という広い視野から、経済活動全般を対象とします。
これらの理論やモデルを理解するには、経済学が体系立った基礎理論を持っていることを理解することが不可欠です。基礎知識を身に付けることで、より高度な経済分析が可能になります。
さらに、経済学は理論だけでなく、実際に問題を解く技術も必要とされます。特にミクロ経済学では計算問題が多いため、定期的にスキルを磨くことが重要です。
公認会計士が人気な理由
公認会計士は数ある資格の中でも特に高い人気を博しています。
ここでは、なぜ公認会計士が人気なのかについて紹介していきます。
非常に高い収入が見込める
公認会計士は専門性が高く、収入面でも魅力的な職業です。2018年の調査では、公認会計士の平均年収は892万円と全国平均の2倍以上に上りました。
IT化が進む中で、企業経営の健全性と信用力を守るための専門知識が求めらています。そのため高度な知識を持つ公認会計士の地位と報酬が高くなっています。
公認会計士の特徴でもある高収入は社会的評価の高さを物語っているため、多くの人から注目される人気の資格となっています。
役職が上がると年収がより上がりやすい
公認会計士は、経験と能力を積み重ねることで、より高い役職と収入を手にすることができる職業です。
監査法人では、スタッフからパートナーまで階層があり、役職が上がるごとに給与も上昇していきます。特にパートナーになれば、年収は1500万円以上から3000万円程度と非常に高額になる可能性があります。
長年の経験と知識と努力を重ねることで、高度な専門性が評価され、報酬も大きくなっていくのです。
需要は高いため就職・転職に有利
公認会計士は独自の監査業務を担う専門職であり、その高度な専門性から安定した職業として評価されています。
AIの進化により仕事が奪われるリスクもありますが、単なる計算能力だけでなく、企業や個人事業主への専門的なサポート力こそが公認会計士の真価です。
AIが実用化されても、適切なデータ供給や最終結果の確認といった役割は公認会計士に求められ続けるでしょう。
活躍できる仕事領域が広い
公認会計士は、多様な分野で活躍できる資格です。
監査、税務、コンサルティング、企業内会計など、それぞれの領域で専門性を発揮することができます。自分の適性やキャリアプランに合わせて、職種を自由に選択できるのが魅力です。
大手監査法人で経験を積んだ後、独立してコンサルティングを始めるなど、キャリアチェンジも柔軟に対応できます。
また、長期的な視点に立ち、監査からコンサルティングへとステップアップすることも可能です。
資格としての価値が高くどこでもステータスとして使える
公認会計士は、経済界で最高の信頼と評価を受ける資格です。
医師や弁護士と並ぶ国家資格であり、厳しい試験に合格しなければ取得できません。独占的な仕事も多いことから、公認会計士の肩書きだけで、人々から高い信頼と安心感を得られます。
上記の通り公認会計士は経済社会での地位が確立されているのです。
一度合格すれば一生有効である
公認会計士は、資格を一度取れば一生有効であり、将来への不安を和らげてくれる資格になっています。
テクノロジーの進化によって職業が変わっていく中で、公認会計士の資格は変わることがありません。世界中のビジネスが会計の基本概念に依存しているため、正確で信頼できる情報を提供する能力は常に求められるからです。
さらに、定年がないため、健康であれば何歳になっても活躍し続けられます。
現代における老後の資金不安を考えると、安定した収入源を確保できる点が大きな魅力となっています。長期的な安定感とキャリアへの自信を与えてくれます。
公認会計士に向いている人はどんな人?

責任感が強い人
公認会計士の仕事の基本は、クライアントの財務諸表を正確に作成し、法的に問題のない状態を保つことです。税務や監査の分野でも、企業や個人の経済活動に関わる重要な決定を下すため、その結果が直接的に影響を与えることも少なくありません。
加えて、ミスや不正を見逃すことが許されないため、細部にまで気を配り、慎重に行動する姿勢が必要です。
そのため、公認会計士には非常に高い責任感が求められます。試験を通して身につける知識やスキルはもちろん重要ですが、最終的にはその知識を適切に運用できる強い責任感がなければ、公認会計士としての役割を全うすることは難しいでしょう。
勉強が得意な人
公認会計士試験に合格するためには膨大な量の学習が求められますが、勉強が得意である方なら公認会計士試験にも合格しやすいかもしれません。
既にご紹介したように試験科目は多岐にわたり、数多くの理論的な知識を深める必要があります。これまでの大学受験や他の資格取得に向けた勉強などを通じて、自分に合った勉強の仕方が分かっている方であれば、試験に向けた準備を着実に進めることができるでしょう。
また、過去の試験勉強の過程で培われた難解な内容でも臆せず身につけようとする姿勢は、公認会計士の試験勉強においても活かされるはずです。
最後までやり遂げる力のある人
公認会計士試験は、長期間にわたる学習と集中力を必要とするため、最後までやり遂げる力がある人に向いています。
試験の内容は非常に幅広く、難易度も高いため、途中で挫折せずに粘り強く続けることが求められます。勉強の進捗に対する自信が揺らいだり、予想外の困難に直面することもありますが、それでも諦めずに目標に向かって努力を続けられる人は、この試験を突破しやすいです。
加えて、公認会計士として活躍するためには、常に自己研鑽を続けなければならず、試験後もその「最後までやり遂げる力」を仕事に活かすことができると言えることでしょう。
公認会計士は独学で合格できるのか
公認会計士を独学で合格するのはかなり難しい
公認会計士に合格する人のほとんどは予備校や通信講座を利用しています。
三大国家資格の一角である公認会計士を独学で合格するのは至難の業で、できるのは東大や医学部などに軽々合格できるレベルの頭脳がある人くらいです。
独学合格を目指すときのポイント
公認会計士の試験は内容が難しく広範囲であるため、一人で長期間学習を続けるのは大変です。モチベーションを保つことが難しく、挫折してしまう人も少なくありません。
そこで、つまづかないためのポイントについて見ていきましょう。
モチベーションをしっかり保とう
公認会計士試験に合格するには、長い時間と粘り強い努力が必要とされます。平均して2~4年を要する人が多く、一年で合格するのは例外的なケースです。そのため、合格までの道のりは一貫したモチベーションの維持が成功のカギとなります。
モチベーションを保つ上で最も重要なのは、「絶対に合格したい」という強い意志です。この試験は忍耐力が求められ、壁にぶつかることも避けられません。そういった障害を乗り越えられるのは、「合格したい」という気持ちが強い場合に限られます。
そのような熱意を持つには、「なぜ公認会計士になりたいのか」を改めて自問自答することをお勧めします。キャリアアップや収入の安定、専門性の向上など、公認会計士を目指す理由をはっきりと認識し、心に刻むことで、前に進む力が湧いてくるはずです。「もう少し頑張ろう」「最後まで諦めない」という強い意志が生まれるでしょう。
さらに、適切な学習環境を整えることもモチベーション維持に欠かせません。良い環境があれば、モチベーションを保ちやすいでしょう。
学習スケジュールをしっかり立てて勉強を進めよう
独学で公認会計士試験に合格するためには、しっかりとした学習スケジュールを立てることが極めて重要です。
スケジュールは山登りの際のルート図のようなものです。ゴールまでの道のりや休憩のタイミング、到達目標などが具体的に見えるため、着実に進めやすくなります。
公認会計士試験対策は1日や2日で終わるものではなく、長期的な視野を持って計画を立てる必要があります。継続的な学習が不可欠です。スケジュールに従って学習を進めていけば、少しずつでも前進していると実感できるでしょう。
計画的に学習時間を確保しよう
公認会計士試験合格には膨大な学習時間が必要とされています。試験範囲の広さと高度な専門性から、約3,000時間の学習が最低でも求められるとされています。
まず、自分の環境に合わせて具体的な学習時間を設定しましょう。会社員なら平日2~3時間、休日10時間程度、学生なら平日4~6時間、休日10時間を目安にするとよいでしょう。
次に、その学習時間を毎日確保できるよう時間管理を徹底し、「確実に合格する」という強い意志を持ち続けることが大切です。
インターネットや参考書を活用してスケジュールを作成し、明確な目標を立てましょう。一歩一歩、着実に進んでいけば、必ず合格できるはずです。より具体的なアドバイスは、専門サイトや書籍を参考にしてみてください。
暗記だけではなく理解も大切
公認会計士試験に合格するためには、単なる知識の暗記だけでなく深い理解と実践的な思考力が重要です。公認会計士試験は広範囲にわたる専門知識を問うものです。
試験では、会計士としての役割や職務に対する理解が求められ、様々な知識をどのように統合し実務で活用するかが問われます。
したがって、公認会計士を目指す際は、要点を理解し、知識を有機的に結びつける力を身につけることが重要なのです。
忙しい社会人には通信講座がおすすめ
公認会計士は高度な専門知識が求められる資格ですが、特定の教育機関を卒業する必要はありません。厳しい試験に合格さえすれば、誰でも取得が可能なのです。そのため、独学で挑戦できるかという疑問が出てくるのも無理はありません。
確かに独学合格は可能で、実際に多くの人がその道を選んでいます。ただし、独学合格には学習能力と自制心、深い知識が必要不可欠です。知識の習得はもちろんのこと、問題解決能力も試される公認会計士試験を一人で学び抜くのは、至難の業と言えるでしょう。
そこで推奨したいのが、通信講座を活用することです。通信講座では、公認会計士試験に特化したカリキュラムが用意されており、独学では分かりにくい部分もしっかりとサポートしてくれます。また、自分のペースで学習を進められるため、社会人にとっても便利なのです。
人気講座ランキング

 もっと見る>
もっと見る>- 合格者占有率60%以上の定番講座!

 もっと見る>
もっと見る>- 抜群の安心感を誇る大手資格予備校!



- ベテラン講師による満足度の高い講義
公認会計士の難易度まとめ
公認会計士試験は極めて難関と言われ、合格には多大な時間と労力を要します。専門知識を問う一次試験と、実践的な問題解決力を試される二次試験があり、どちらも容易ではありません。
しかし、その難易度の高さは公認会計士の資格が高く評価されている証しであり、合格者には高収入やキャリアアップのチャンスが待っています。
ぜひこの記事を活かして公認会計士への挑戦の一歩を踏み出しましょう!