予備試験は天才以外には無理ゲーなのか?合格率と実際の例から難関突破の鍵を探る
更新
予備試験は合格率が低いため、難しい試験と思われがちです。
しかし、実際には計画的に学習を進めれば、合格は十分に可能です。
本記事では、予備試験の実際の難易度や独学での合格方法について詳しく解説します。
試験に挑戦する前に、しっかりと理解しておきましょう。
- 予備試験は無理ゲーではない
- 合格率は低いが、しっかり対策すれば十分合格可能な試験
- 通信講座や予備校を活用しながら対策を行うのがおすすめ
人気講座ランキング

 もっと見る>
もっと見る>- 特出した実績を持つ最注目のオンライン講座!


- 業界最高の合格者占有率を記録する王道予備校

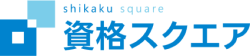 もっと見る>
もっと見る>- リーズナブルかつ高品質なコスパ抜群の講座
このページにはプロモーションが含まれています
予備試験の「合格率」は低いが無理ゲーではない
結論から言って、予備試験は合格率は低いですが、決して無理な試験ではありません。
予備試験の合格率は毎年4~5%前後と数字だけを見ると極めて狭き門に映りますが、実態は決して“無理ゲー”ではありません。
合格率が低く見えるのは、受験者層が広く、十分に準備せずに受験する人が多いためです。
法律学習経験の浅い層や記念受験層も母集団に含まれるため、十分に準備した層の実質的な合格率は2〜3倍とも言われています。
短答・論文・口述という三段階の試験は、それぞれ出題範囲とパターンがはっきりしており、過去問の反復演習と答案構成の型を身に付ければ得点源を確実に積み上げられます。
特に論文は、条文・判例・趣旨をワンセットで整理し、答案の骨格をテンプレート化しておくことで大幅に効率化できます。
計画的な学習計画を立て、答案練習会やオンライン添削を活用しつつ地道にアウトプットを重ねれば、社会人でも在学中でも合格は充分射程内と言えるでしょう。
予備試験の難易度が高いと言われる理由
予備試験は、司法試験を目指す上での重要なステップですが、その難易度が高いと広く言われています。
多くの受験生がその壁に直面し、合格を果たすためには相当な努力が必要だと感じることでしょう。
では、なぜ予備試験は難易度が高いと言われるのでしょうか。その理由について詳しく見ていきます。
合格率が司法試験より圧倒的に低いから
予備試験の難易度が高いと言われる主な理由は、合格率が非常に低いことにあります。
令和6年(2024年)の予備試験では、受験者12,569人に対し合格者は449人、合格率は約3.6%でした。
出典:法務省『司法試験予備試験の結果について(平成23年~令和6年)』
一方、同年の司法試験の合格率は約42.1%(受験者3,779人、合格者1,592人)と、予備試験より圧倒的に高くなっています。
出典:法務省『司法試験の結果について(平成23年~令和6年)』
ただし、予備試験は年齢や学歴などの制限がなく「誰でも受けられる」ため、受験者層が広く、結果として合格率が低くなりやすい側面もあります。
確かに難関試験ではありますが、合格率の数字だけを見て過度に恐れる必要はありません。しっかりと対策を立てて学習すれば、突破は十分可能です。
3種類の試験を突破する必要がある
予備試験の難易度が高いと言われる最大の理由は、短答式試験・論文式試験・口述試験という3種類の異なる試験をすべて突破しなければならない点にあります。
各試験はそれぞれ出題形式や求められる能力が異なり、個別に対策が必要です。
さらに、短答式試験に合格しなければ論文式試験を受験できず、論文式試験に合格しなければ口述試験に進むことができません。
一度でも不合格になると、翌年は最初からやり直しとなるため、3つの試験すべてに同一年度で合格する必要がある点が大きなプレッシャーとなります。
科目数が多く対策量が多い
予備試験の難易度が高い理由の一つは、科目数が多く、試験範囲が広いことです。
短答式試験では憲法・民法・刑法などの基本的な7科目に加え、一般教養科目も含まれ、論文式試験ではさらに民事実務基礎や刑事実務基礎、選択科目が加わります。
合計で10科目にもなり、これは法律系資格試験の中でも最多の科目数です。
そのため、受験生は広範囲にわたる学習を行わなければならず、膨大な対策が必要となります。
また、各科目の内容も専門的であり、効率的な学習が求められるため、これが予備試験の難易度を一層高めています。
人気講座ランキング

 もっと見る>
もっと見る>- 特出した実績を持つ最注目のオンライン講座!


- 業界最高の合格者占有率を記録する王道予備校

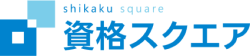 もっと見る>
もっと見る>- リーズナブルかつ高品質なコスパ抜群の講座
予備試験の難しさについて口コミから調査
予備試験の難易度については、多くの受験生や経験者がさまざまな意見を持っています。
実際にどのような点が特に難しいと感じられているのか、口コミを通じてその実態を探ってみましょう。
予備試験が難しいと嘆く声
やっぱり予備試験って難しいな。
短答の段階からむずい
司法試験より予備短答の方がむずい説は割と推してる
ヤヴァイ
せっかく7科目
憲法、民法、刑法、商法、民訴、刑訴、行政法の短答式を10年一周完了して民法戻ってきたらなんかだいぶ忘れてヤヴァイ!見た事ある問題やが何やったけな? 結果6割くらいの精度だわ。無勉強でも5割は正解できたのにな。1割あげるのに2割あげるのに凄い大変!短答式むずい
予備試験の難しさについて、実際に受験した人々からは多くの声が上がっています。
特に短答式試験が非常に難しいと感じる受験生が多く、司法試験よりも予備試験の短答の方が難しいという意見もあります。
また、科目数と範囲の広さにも苦しむ受験生も多いようです。一度学んだ内容でも時間が経つと忘れてしまい、精度を上げるのが非常に大変だという声も目立ちます。
実際に合格した人の声
予備論文の勉強法としては予備過去問も大事だけど、司法試験の論文過去問が1番有用。
私の予備論文の勉強法は過去問解いて、採点実感読み込むのに注力した。司法試験合格レベルを目指して司法試験合格レベルになれば当然予備も受かります。
合格率は予備の方がきついけど問題は司法試験の方がむずい。
転職に備え、予備試験を受験し、予備試験には昨年4回目で合格しました。
平日は仕事をしているため、通勤中でも勉強ができるスタディングを受講することとし、勉強を始めたときから司法試験の受験当日まで聴き続けました。
通勤時間を勉強時間に変えることができたのは、学習密度が落ちるとはいえ、大きかったと思います。
モチベーションの維持については、いくつかの科目を並行して勉強したり、疲れたら短答の問題を解いたり、
また、勉強に飽きたときは、ジョギングなどの運動をしたりして、目線を変えて、勉強を途切れないように心掛けていました。(一部抜粋)
短答は、ひたすら過去問を解くことに注力しました。
まずは全範囲を2周解いて、分からなかった選択肢や問題にマークをつけ、3周目以降はその問題を中心に解き進めました。
何度も間違った問題や苦手な分野の問題は5~6周解いたと思います。
後は条文を2周ほど素読しました。過去問と条文素読を徹底することで十分合格点を勝ち取ることができると実感しました。
合格者からは「ちゃんと対策すれば予備試験は合格できないものではない」という意見が多く聞かれました。
科目数の多さや長期戦に対する不安はあるものの、進捗管理やモチベーション維持をしっかり行えば合格は十分に可能なようです。
特に短答式試験では、過去問を繰り返し解き、間違えた問題や苦手分野を重点的に復習する方法が効果的だとされています。
予備試験の実際の難易度はどれくらい?
予備試験の実際の難易度は非常に高く、大学入試に例えるならば、東大や京大の入試に匹敵するレベルだと言えるでしょう。
多くの科目と広範な範囲をカバーし、厳しい試験内容に挑戦することになるため、合格するには相当な努力と計画的な学習が求められます。
以下では、予備試験の難易度や回避方法について解説していきます。
学習時間は他の資格と比べても長い
予備試験合格までに必要な学習時間は一般的に3,000~8,000時間とされており、他の主要な資格試験と比べても非常に長い時間が必要です。
合格するためには、「短答式」「論文式」「口述式」の3つの試験すべてに合格しなければならず、科目数や試験範囲も広範囲にわたります。
特に独学の場合、8,000時間近くかかることも珍しくなく、継続的な努力と計画的な学習が不可欠です。
資格 | 勉強時間目安 |
司法試験・予備試験 | 3,000時間~8,000時間 |
弁理士 | 3,000時間 |
司法書士試験 | 3,000時間 |
公認会計士 | 2,500~3,500時間 |
中小企業診断士 | 1,000時間 |
土地家屋調査士 | 1,000時間 |
社労士試験 | 800~1,000時間 |
行政書士 | 600時間 |
予備試験は簡単になった?
予備試験の実際の難易度は依然として非常に高い水準にあります。
直近の合格率は3〜4%程度で、国家試験の中でも最難関に位置します。
しかし、受験者には十分な準備をしていない人も多いため、本気で対策をした受験生にとっては実質的な合格率はやや高くなります。
旧司法試験に比べて短期合格が狙いやすくなった面もありますが、大幅に簡単になったわけではなく、科目数が多く、三段階すべてに合格する必要があるため、依然として高い難易度を誇ります。
総じて、「昔より受かりやすくなった」とは言えるものの、予備試験が簡単になったとは言えないでしょう。
予備試験を避けたければ法科大学院への進学も選択肢の一つ
予備試験を避けたい場合、法科大学院への進学も一つの選択肢です。
司法試験合格を目指すために必ずしも予備試験を受ける必要はなく、法科大学院を経由する方法もあります。
この選択肢では、より充実した指導を受けながら学習できるため、学習の質やサポート体制が整っている点が大きなメリットです。
ただし、法科大学院には学費がかかるため、お金の余裕が必要となることを考慮する必要があります。
人気講座ランキング

 もっと見る>
もっと見る>- 特出した実績を持つ最注目のオンライン講座!


- 業界最高の合格者占有率を記録する王道予備校

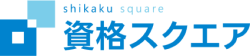 もっと見る>
もっと見る>- リーズナブルかつ高品質なコスパ抜群の講座
予備試験突破の目安
予備試験を突破するためには、各試験で一定の基準をクリアすることが求められます。
ここでは、短答式、論文式、口述式それぞれの合格基準の目安について解説します。
各試験に向けて、どのような準備をすれば良いかを理解することで、効率的に学習を進めることができます。
短答式で60%以上
予備試験を突破するための目安として、まず短答式試験で6割以上の得点を安定して取ることが重要です。
短答式の合格点は毎年270点満点中150~170点前後で推移しており、実際には得点率60%程度が合格ラインとなっています。
短答式で合格点を超えなければ次の論文式試験に進むことができないため、まずは短答式で6割以上取れる実力を身につけることが最初の関門となります。
論文式試験はトップ400
予備試験の論文式試験を突破するためには、例年「上位400人程度」に入ることが目安とされています。
論文式試験は相対評価で採点されるため、特定の科目に極端な弱点を作らず、全科目でバランスよく得点を重ねることが重要です。
また、合格点は年度によって変動しますが、500点満点中210~260点程度が目安となっています。
口述式試験の合格率は高い
予備試験突破の目安として、特に口述式試験の合格率は非常に高いことが特徴です。
直近の令和6年度(2024年)では、口述式試験の合格率は97.4%に達しており、過去5年でも毎年90%台後半を維持しています。
この高い合格率から、論文式試験を突破できれば、口述式試験もほぼ確実に合格できると言われています。
予備試験合格に向けては通信講座・予備校の利用がおすすめ
予備試験は決して「無理ゲー」ではありませんが、その膨大な学習量や高い合格水準のため、独学で合格を目指すのは非常に難しいのが現実です。
効率的に合格を目指すなら、通信講座や予備校の利用がおすすめです。
ここでは、特におすすめの通信講座・予備校を3つご紹介します。
アガルート

アガルートは、司法試験・予備試験対策に特化した大手の通信講座で、費用を抑えつつ、しっかりとしたサポートと実績を求める方におすすめです。
通学型の予備校と比べて受講料が安く、コストパフォーマンスに優れている点が大きな魅力です。
また、プロ講師による1対1のコーチングや、口述論文添削、オンライン自習室、質問制度など、予備校並みの手厚いサポートが受けられ、独学では得られない学習環境が整っています。
さらに、毎年多くの合格者を輩出しており、実績も豊富です。合格者の声やデータが公開されており、信頼性の高い通信講座として評価されています。
項目 | 内容 | ポイント |
料金 | 予備試験最短合格カリキュラム フル:998,800円 予備試験最短合格カリキュラム ライト:888,800円 分割払いや割引あり。単科講座も選択可。 | 他社と比べてやや安価~中間帯。コースやオプションによって幅があり、コスパ重視の設計。 |
初心者の学びやすさ | 図や表を多用したフルカラーテキスト、丁寧な基礎解説。初心者向けコースが充実。 | 法律初学者でも安心して学べる設計。学習レベルごとにコース選択可能。 |
講師・講義 | 各分野の専門講師が多数在籍。講義動画はオンライン配信、倍速再生や進捗管理機能あり。 | 講師陣がテキストも作成。質の高い講義と教材。講師ごとの担当科目が明確。 |
サポート体制 | オンライン質問サービス「KIKERUKUN」、月1回の無料カウンセリング、個別指導や添削(オプション)。 | 初心者にも安心のサポート。学習計画や疑問解消、個別指導も選択可。合格時返金特典も。 |
合格実績 | 令和6年度司法試験合格者602名、合格占有率37.8%。 | 業界トップクラスの合格実績。伊藤塾に次ぐ実績で信頼性高い。 |
伊藤塾

伊藤塾は司法試験や予備試験の合格実績が非常に高く、特に予備試験合格を目指す受験生から高い評価を受けている予備校です。
2024年の司法試験合格者のうち、実に約9割以上が伊藤塾の受講生であり、圧倒的な合格実績を誇ります。
また、カリキュラムの網羅性やサポート体制も充実しており、合格に必要な講義・教材・質問制度などが受講料に含まれている点も特徴です。
一方で、費用の高さは大きなネックとなっています。主要なコースの受講料は約110万円から140万円と、他の予備校と比べて30万円近く高額な設定になっており、経済的な負担が大きい点はデメリットです。
項目 | 内容 | ポイント |
料金 | 2年合格コース:1,459,000円 合格プレミアムコース:1,481,100円 入塾料は別途10,000円 他にも講座あり。 | 業界最高水準の合格実績とサポート体制があるが、受講料は他校より30万円~130万円ほど高い。 |
初心者の学びやすさ | 入門講座から丁寧に基礎を解説。テキストは網羅性が高く、重要ポイントを図表で視覚化。ゼロからでも体系的に学べる設計。 | 初心者に特に優しいカリキュラム。基礎から段階的に学べるため、法律未経験者でも安心して学習できる。 |
講師・講義 | 伊藤真塾長や呉明植氏など、実績・知名度ともに高い講師陣が担当。講義は分かりやすく、実践的な指導が特徴。 | 講師の質・知名度・指導力は業界トップクラス。答案作成や学習スケジュールまで丁寧にサポート。 |
サポート体制 | 質問制度、カウンセリング、スケジューリング、個別指導(有料)、受講生・合格者交流会など多様なサポートを用意。 | オンライン・通学どちらでも手厚いフォロー。進捗管理や学習相談も充実。自宅でも教室同様の環境を提供。 |
合格実績 | 2024年司法試験合格者のうち約90.2%(1,436名)が伊藤塾生。予備試験ルート合格者の約96%が伊藤塾受講生。 | 圧倒的な合格実績を誇る。合格者占有率は業界随一で、信頼度が非常に高い。 |
資格スクエア

資格スクエアは、司法試験予備試験合格を目指す受験生にとってコストパフォーマンスの高さが際立つオンライン予備校です。
他社と比較して受講料が安価でありながら、質の高い講義や充実したサポート体制が評価されています。
講師陣は説明が分かりやすく、疑問点への迅速な対応や個別指導も受けられるため、効率的な学習が可能です。
また、オンライン学習システムには倍速再生やメモ機能などが備わっており、忙しい社会人でも自分のペースで学習を進めやすいのが特徴です。
基礎問題を中心とした合格重視のカリキュラムで、実際に短期間で合格を果たした受講生の声も多く寄せられています。
項目 | 内容 | ポイント |
料金 | 司法試験予備試験講座:合格フルパッケージ:796,950円 短答攻略NEO:217,800円 論文攻略NEO:288,750円 他にも単科・オプションあり。 | 他校と比べてやや高額だが、割引キャンペーンや乗り換え割引も実施。 |
初心者の学びやすさ | 基礎問題中心のカリキュラムで、確実に合格ラインを目指す構成。 一問一答形式やカスタマイズ可能なオンライン教材を活用。 | 基礎から段階的に学べ、アウトプット重視。 講義画面はテキストと講師の手元が映るライブ風で理解しやすい。 |
講師・講義 | 東大教授監修のカリキュラム。 科目ごとに専門講師が担当し、コンパクトで効率的な基礎講義を重視。 | 実践的なアウトプット重視。 分かりやすい講義とスペシャリスト講師陣。 |
サポート体制 | 回数無制限の質問対応、月1回のZoom相談会、合格お祝い金1万円。 疑問はワンクリックで質問可能。 | 他社と比べても質問サポートが充実。 一週間以内に回答。 乗り換え割引なども用意。 |
合格実績 | 合格を最優先したカリキュラム設計。 基礎力重視で合格ライン突破を目指す。 | 合格者の声や実績も公式サイトで公開。 過去問対策や論述練習も好評。 |
司法試験勉強は通信講座?予備校?
司法試験の勉強方法には、通信講座と予備校の2つの選択肢があります。
それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選びましょう。
通信講座の受講がおすすめな人
通信講座は、自分のペースで計画的に学習を進めたい人に最適です。
また、好きな時間に講義を視聴でき、何度でも見返せるため、仕事や学業と両立しながら勉強したい社会人や学生にも向いています。
内容は体系的に整理されており、独学よりも効率よく知識が身につくうえ、分からない点は質問できる仕組みも整っています。
予備校に比べて費用が安く、コストを重視する人にも適した選択肢です。
予備校の受講がおすすめな人
独学や通信講座に不安がある方、確実に合格を勝ち取りたい方には、予備校の受講が最適です。
予備校は教材の網羅性が高く、合格に必要な知識を効率よく学べるカリキュラムや、丁寧な講義、演習講座が充実しています。
特に大手予備校は合格実績も豊富で、学習仲間や自主ゼミも作りやすい環境が整っています。
また、対面指導や個別フォロー、質問対応、自習室利用など、手厚いサポート体制も魅力です。
自分に合った講座を活用して予備試験を突破しよう
- 予備試験は無理ゲーではないが数千時間の対策は必要
- 予備試験は独学では突破は難しい
- 自分に合った通信講座や予備校を活用しながら合格を目指そう
予備試験は合格率が非常に低く、独学だけで突破するのは容易ではありません。
効率的に合格を目指すには、自分に合った講座を活用することが重要です。
講座を利用すれば、広範な試験範囲を体系的に学べるだけでなく、疑問点も早期に解消できます。
自分に最適な学習環境を整え、継続的に努力を重ねることで、難関に思える予備試験も確かな目標へと変わっていくでしょう。