品質管理の重要性とは|日本規格協会 末安氏に聞く
更新
今回は、品質管理に関する検定であるQC検定Ⓡ(品質管理検定Ⓡ)を運営する一般財団法人日本規格協会、品質管理検定センター所長の末安いづみ様にインタビューをさせていただきました。
QC検定Ⓡ創設の背景と目的

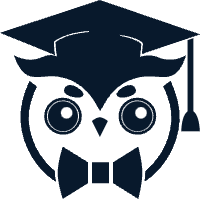
本日はお忙しい中、取材のお時間をいただき誠にありがとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。

品質管理検定センター所長を務めております末安です。
よろしくお願いいたします。
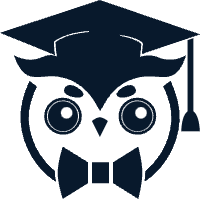
まず初めに、簡単に末安様の自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか?

標準化や品質管理技術の普及・開発を担う日本規格協会に就職し、ISO 9001(品質マネジメントシステム)等の規格開発や認証業務を経て、現在は品質管理検定センターの所長を務めております。
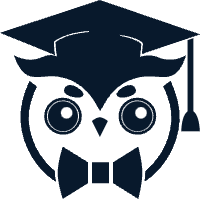
QC検定Ⓡはどのような背景で創設された検定なのでしょうか?

QC検定Ⓡは、2005年に始まりました。
当時は、1990年代のバブル崩壊を受けて日本の経営環境が大きく変化し、経費削減や品質教育の衰退など品質管理、品質改善への意識・知識が低下し、技術力の維持が難しく品質トラブルが増えた時期です。その頃は、品質管理に関する知識を測る共通の基準がなく、立場・職種に応じた必要な知識レベルも不明確でした。
そこで、産業界での品質向上のため、関係者全員が自身の立場に見合う品質管理の知識(4段階)を明確にし、試験で客観的に評価する目的で創設されたのがQC検定Ⓡです。
客観的に評価された品質管理の知識を現場で活用することにより品質管理の向上につなげられ、品質管理に関する共通言語をもつ、即戦力が期待できることの証明になるなど、多様に活用されています。
QC検定Ⓡの特徴
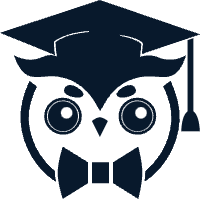
QC検定Ⓡを通して、具体的にどのような知識を身につけ、それらをどのように活かすことができるのでしょうか?

QC検定Ⓡの受検を通じて、組織が良い製品・サービスを提供してお客様に喜んでいただくためにはどのような考え方・活動(品質管理)が必要かという体系的な知識を身につけることができます。
「品質管理」という言葉は、製品の品質だから製造や設計、品質保証に限ると誤解されやすいのですが、決して限定的ではありません。「品質のための問題解決」と考えれば、製造や設計にとどまらず、管理部門であったり、社会人でなくとも日常での問題解決に繋がる知識を身につけることができます。
当該知識を発揮することによって、効率的かつ効果的に問題を解決したり、品質改善を実現することや、共通言語で関係者とコミュニケーションをとることも可能になります。
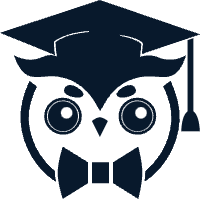
QC検定Ⓡの主な受検者層やターゲットを教えていただけますでしょうか?

現状としては、製造業の方が8、9割を占めています。徐々にサービス業も増えています。先ほど申し上げたように、産業界で製造・設計に関わる人以外にも幅広く受けていただけるため、職種もいろいろです。
製品・サービスを通じてお客様に喜んでいただくために、全関係者が品質管理を学び、品質の向上や改善に努めることを組織は期待しています。
社会人としての基礎的教養を身に着けたい学生や新入社員の方から、品質管理のスペシャリストを目指したい品質保証や設計、製造部門の方や転職を考えている方など、幅広い層がターゲットといえます。
QC検定Ⓡのメリット
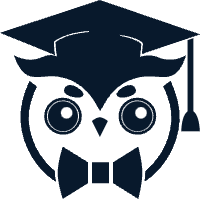
QC検定Ⓡを取得するメリットとして、どのようなことを想定されていますか?

QC検定Ⓡは、企業や学校など団体での申し込みと、個人での申し込みの双方が可能です。
団体、特に企業のメリットとしては、製品・サービスの改善のために、職場の問題解決能力や品質が向上し、不具合や問題が減ることがまず挙げられます。企業にとって、社員が品質管理の基本的な考え方を理解し、品質について同じ問題意識をもつような職場づくり・人づくりはとても重要です。それらの一手段として、QC検定Ⓡにメリットを感じてくださっています。
例えば、QC検定Ⓡを教育計画や社内外研修の有効性評価に用いたり、採用・昇進・昇格・ベア・配置といった人事に役立てている事例が実際に多くあります。
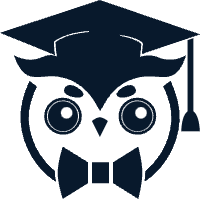
個人の受検者へのメリットについてもお聞かせいただけますか?

個人については、就職や転職でアピールポイントになる点がまず挙げられます。
QC検定Ⓡの合格は、一定の知識をもっていることの証明になるためです。
とある就職・転職サイトで「QC検定Ⓡ」と検索すると約3,000件がヒットしました。QC検定Ⓡが、採用の考課項目の一つとして参考に用いられていることが分かります。
ご自身の品質管理の知識レベルを証明するため、また、スキルやキャリアアップの手段として活用いただけます。
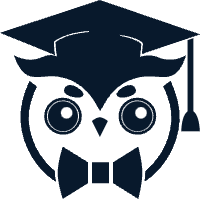
具体的にキャリアに役立った事例などございましたら伺いたいです。

QC検定Ⓡの合格が企業内の特定部署の配置条件や考課項目の場合、希望する部署異動が実現して品質管理の知識を発揮してキャリアを積んだり、就職・転職でキャリアを重ねたり、昇進・昇格・ベア条件を満たすことで相応の地位や収入を得るといった事例もあります。例えば、QC検定Ⓡ3級は企業でQCサークルなどの改善活動を行う場合のメンバーレベルを設定していますが、2級に合格してリーダーになり、活躍の機会が増えモチベーションが上がったという声も届いています。
また、スキルアップによって、実際に現場での作業効率アップなどの結果も報告されており、それが積み重なることでキャリアアップになり、学習のモチベーションを高めていただけると考えています。
品質管理では、問題・課題解決全般を学ぶことができますので、学んだ知識を使ってどんな分野・職種でもキャリアを築いていくことに役立てられます。
QC検定Ⓡとリスキリングの関係性
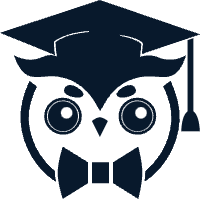
末安様は、リスキリングについてどのようにお考えですか?

リスキリングは当然、キャリアアップにとって重要です。
ただ、目的をもって学習すること、つまり単に知識を習得するだけでなく実際に使えるようにする意識が不可欠だと思います。
知識を実践で活用する意識がなければ、リスキリングの意義が下がってしまうと考えています。
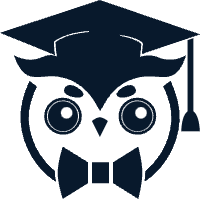
特にQC検定Ⓡは社会人のリスキリングとどう繋がってくるとお考えですか?

最近よく言われているデータサイエンスの考え方などは品質管理に含まれています。このようにQC検定Ⓡで学べる知識は、普遍的に確立されたものであり、一生涯を通じて役立つものです。
こうしたあらゆる業務の共通土台となる知識を「リスキリング」として学ぶ、学びなおすことには大きな意義があると考えます。
時代に沿った知識を学ぶことも重要ですが、いつの時代も変わらず必要とされる知識を土台として学んでおくことはキャリアの選択肢が広がり有用ではないかとの考えをもっています。

例えば品質管理には、後工程で働く人に喜んでもらえるように心がけて活動する考え方として「後工程はお客様」があります。
ここでいうお客様とは社外だけではありません。生産性高く、互いに気持ちよく仕事をするために社内であっても自分の仕事に続いて業務を行う人もお客様という意識をもつ、というものです。
これは、どのような仕事にも通用する考え方です。おそらく感覚的に言われなくてもわかっていることだとは思いますが、このような考え方や手法が品質管理では体系的に整理されていて、3級・4級は特に学びやすい、学びなおしやすいと考えます。
今後のQC検定Ⓡの展望は?
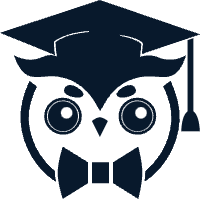
QC検定Ⓡ3級・4級の試験ではCBT(コンピュータ試験)が導入されると伺いました。
今後のQC検定Ⓡの展望についてお聞かせください。

業務改善や事業成長に繋がる提案をできる人材を育成し、人づくり・物づくり・サービスづくりを底上げしたい、産業界のお役に立ちたいという思いがあります。
そのためにも受検しやすさは重要だと考え、3級・4級は、第40回(申込:2025年5月8日~8月24日、試験:2025年6月23日~9月28日)から、CBTに切り替えて場所や時間をご自身で選択/変更できる方法に変更しました。
勉強のしやすさという面でも、見本問題、また4級の場合は『4級用テキスト(4級の手引き)』をHPで公開しています。加えて、CBTを意識して学習したい方に向けて、CBT用の書籍も別途用意があります。
将来的には、QC検定Ⓡを日本国内のみならず世界的に利用していただけるよう努めていこうと考えております。QC検定Ⓡの合格によって日本のハイレベルな品質管理の知識をもっていることが認知され、合格者が日本を含むグローバルに就職/活躍するチャンスが増えることを期待します。
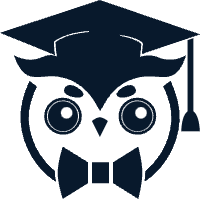
最後に、この記事をご覧の方へメッセージなどございますでしょうか?

CBT導入に伴い、3級・4級は特にQC検定Ⓡの受検しやすさが向上しました。一度、リスキリングの一環としてご受検を検討していただければ幸いです。