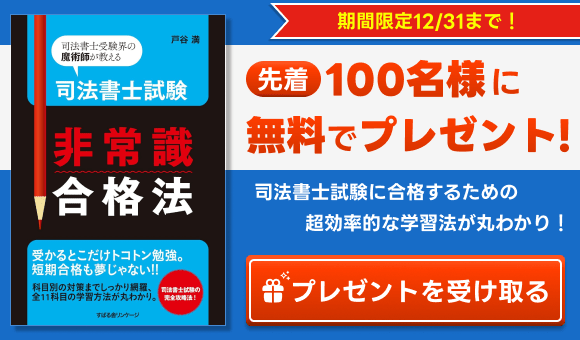司法書士のおすすめ勉強法は?初心者の勉強時間の目安や科目別の勉強法も解説!
更新
司法書士試験は合格率わずか5%前後と非常に難易度が高く、過去問だけでなく法律知識の理解が求められます。(出典:法務省 )
この記事では、初心者にも分かりやすい勉強法や、科目別の効率的な学習方法、1日の適切な学習時間をご紹介します。
このページにはプロモーションが含まれています
司法書士の独学合格のためのおすすめ勉強法

司法書士試験に合格するためには、資格取得講座や通学系スクールに通うよりも、独学で勉強する方が圧倒的に難しいと言われています。しかし、その難易度を理解した上で取り組むのであれば、学習効率を最大化する勉強法を導入することが重要になります。
司法書士試験では、不動産登記法、民法、商法、憲法など、専門用語が多く出題されるため、単に暗記するだけでなく、応用できる力が必要となります。
具体的には、「六法全書の完全理解」、「五感を使った覚え方」、「問題解決力の養成」の3つの方策を取り入れることで効率的な勉強を目指しましょう。
科目数が多いので関連する科目を同時進行で学ぶ
司法書士試験は幅広い知識が求められるため、効率的な学習法が重要になります。全ての科目を個別に進めるのは時間的・精神的負担が大きく、知識の定着も難しいです。そこで、関連する科目を組み合わせて学習する勉強法がおすすめです。
例えば、民法と不動産登記法は最重要科目で関連性が高いため、並行して学習すれば理解が深まります。特に民法は他科目との関連が多く、この分野を押さえておけば他の科目の理解も効率的になります。
同様に、商法・会社法と商業登記法も密接に関係しています。これらも組み合わせて学習することで、その後の理解を深めることができます。
さらに、不動産登記法や商業登記法の学習時には、択一式問題の解答技術と書式問題の対策も同時に行うと良いでしょう。
六法を常に引く癖づけが不可欠
司法書士試験の学習においては、六法全書の内容を丁寧に理解し、使いこなすことが非常に重要です。条文の文言だけでなく、その背景にある論理構成を把握することが欠かせません。
つまり、単に条文を暗記するのではなく、各条文の意義や表現の理由を考えて法的な思考力を身につける必要があります。
そのためには、六法全書を常に手元に置き、空き時間を活用して条文を確認し、考察を重ねることがおすすめです。
六法は一年ごとの買い替え必須
司法書士試験を独学で目指すうえで、法律の変化に敏感であることはとても大切です。法律は毎年のように改正され、新しい法律ができたり、古い法律が廃止されたりします。
そのため、古い六法を使い続けていると、誤った情報のまま学習してしまうおそれがあります。
こうしたリスクを避けるためにも、六法は毎年最新版を購入することをおすすめします。
最新の六法を使うことで、法改正の内容を正しく把握でき、安心して学習を進めることができます。
記憶に五感を取り入れる
法律知識を確実に身に付けるには、五感を総動員した学習法がおすすめです。視覚や聴覚などを上手に活用し、多角的なインプットを心がけることで、知識をより深く自分のものとすることができるでしょう。
例えば、講義の動画教材を視聴した後に音声版の講義を通勤中などに聴講する、といった学習です。このように様々な感覚を使ってインプットを重ねることで、学習時間や場所の制約を解消し、効率的な知識吸収を図れます。
加えて、テキストの内容を音読することも大切です。黙読ではなく、声に出して条文や解説を読み進めることで、理解の度合いを自覚しやすくなります。
自分なりにテキストを作ろう
司法書士を目指す上では、自分で重要な条文を選び出し、関連条文とともにまとめて解釈を加えることで、オリジナルのテキストを作成する方法もおすすめです。
条文を拡大コピーして見やすくし、空白部分に自分なりの理解をメモすれば、自分専用の教材ができあがります。自身で解釈を書き出すことで、条文の本質的な理解が深まり、記憶の定着にも役立ちます。
さらに、このテキストをコンパクトなサイズにすれば、移動中や空き時間にも活用できます。
こうして自分で作成したオリジナルテキストを活用することで、条文の暗記だけでなく、より深く理解できるようになります。
問題演習を積み重ねる
どの学習においても、問題を解く力は非常に重要です。独学の場合には、特に過去問を大量に解くことが重要になります。過去問の正答率が高ければ高いほど、試験での好成績が期待できます。
しかし、単に問題を機械的に解くだけではいけません。問題の背後にある本質を理解し、その上で正確な解答を導き出す力を養うことが重要です。
過去問の正答パターンを覚えるだけでは、表現が少しでも変わると答えられなくなる可能性があります。そのため、「なぜその答えになるのか?」という思考プロセスを確認し、自分の言葉で説明できるようになることが大切です。
解説を自分の言葉で語れるレベルまで理解を深めれば、真の理解が得られたと言えるでしょう。
司法書士試験合格に必要な勉強時間の目安は3000時間
司法書士試験に合格するためには、相当な勉強時間が必要とされています。最短でも1年8ヶ月程度の集中した学習が求められますが、実際にはそれ以上の時間を要する受験者が多数います。中には5年以上の長期にわたって努力を重ね、ようやく合格に至る人もいます。
| 回答 | 度数 |
|---|---|
2000時間未満 | 0 |
2000~2500時間 | 3 |
2500~3000時間 | 1 |
3000~3500時間 | 2 |
3500時間以上 | 3 |
合計 | 9 |
上記の表は、スキルアップ研究所の司法書士試験合格に必要な勉強時間に関する調査結果です。
表からわかるように、スキルアップ研究所の調査では、受験者9人のうち6人が3000時間以上の勉強を報告しており、2000時間未満で合格した例はありませんでした。
このように、受験者の前提知識やスキルの差により、必要な学習時間に大きな開きがあることがわかります。
合格までに勉強時間が長くかかる理由
司法書士試験は、多岐にわたる科目の深い理解と適切な解答技術が求められるため、合格には膨大な学習時間が必要とされています。出題範囲は広範囲に及び、記述式問題では単なる知識だけでは解答できず、科目ごとの深い理解と問題解決能力が不可欠です。
そのため、全科目に精通し、きめ細かな知識を身につけるためには、少なくとも3000時間の勉強が必要とされています。
他の国家資格試験に比べても、司法書士試験はその学習量の多さから、相当な努力を要する試験だと言えるでしょう。
1日ごとの勉強時間
司法書士試験に合格するためには、約3000時間の学習が必要です。受験生は自身の状況に合わせて、学習期間を設定する必要があります。
| 合格を目指す期間 | 1日当たりの勉強時間 |
|---|---|
1年 | 約8.2時間 |
2年 | 約4.1時間 |
3年 | 約2.7時間 |
上記の表は、司法書士試験に合格することを目標とした場合の、目標の期間と1日当たりの必要な学習時間の関係を示しています。
上記の表からわかるように、1年で合格を目指す場合、1日あたり約8時間の学習が求められます。
例えば、働きながら受験する人にとっては、この時間の確保は難しいでしょう。2年かけて学習する場合は、1日4時間程度の学習で済みます。3年で取得を目指す計画なら、1日2.7時間の学習で十分です。
受験生は、自身の生活スタイルに合わせて、最適な学習計画を立てる必要があると言えるでしょう。
勉強に集中できる専業受験生の勉強時間
専業受験生として司法書士試験の勉強を始めるなら、1年間で最低でも1日8時間の学習時間を確保することが望ましいでしょう。ただし、単に時間を費やすだけでなく、集中して取り組むことが重要です。
まずは1日8時間の学習を目指し、体調次第でさらに時間を増やすことをおすすめします。優秀な一部の人が2年以内に合格するケースもありますが、多くの人はそれ以上の時間を要し、5年以上かかる場合もあります。
しかし、最初から「長期間かかる」と考えるのではなく、「最短で合格する」という強い意志を持つことが大切です。
働きながら勉強をする兼業受験生の勉強時間
兼業で司法書士試験の勉強を進める人々にとって、時間の確保は最大の課題となります。平日と休日のバランスを取り、合理的な学習計画を立てることが重要です。
| 平日 | 休日 | かかる期間 |
|---|---|---|
3時間 | 6時間 | 2年強ほど |
4時間 | 8時間 | 1年9カ月ほど |
5時間 | 8時間 | 1年半ほど |
上記の表は、平日と休日それぞれの利用可能な時間と、その場合に必要な合計勉強期間の一例です。
平日3時間、休日6時間の学習時間を確保すれば、およそ2年以上の期間が必要となります。合格までの期間を短縮したい場合は、平日4時間、休日8時間の学習時間を設定すれば、約1年9カ月で合格が見込めます。
勤務形態によっては、平日5時間、休日8時間の学習時間という選択肢もあり、この場合、合格までの期間は約1年半となります。
このように、兼業受験生が司法書士試験に取り組む場合、最低でも2年前後の期間を想定するのが一般的です。ただし、法律知識の有無や資格の経験次第では、さらに短期間で合格できる可能性もあります。
司法書士試験に向けた1年間の勉強スケジュール
司法書士試験に1年で合格するには、科目の優先順位をつけて効率的に進めることが不可欠です。
ここでは、試験前年の7月から本番までの一般的な学習スケジュールモデルを紹介します。1年間の勉強スケジュールとして、試験前年の7月からスタートする例を紹介します。
7月〜10月:民法・不動産登記法
【学ぶ科目】
- 民法(基礎・総則・物権・債権など)
- 不動産登記法(記述式の基礎含む)
【重点ポイント】
- 民法は最重要科目のため、条文・趣旨・基本論点を丁寧に理解する
- インプットと並行して過去問に早期着手する
- 不動産登記法は書式の雛形に触れ、記述の構造を覚え始める
- 民法と登記法の関連を意識して並行学習する
【到達目標】
- 民法と不動産登記法の基礎を一通り理解
- 主要論点の過去問を1周
- 書式の基本パターンを把握する
10月〜12月:会社法・商法・商業登記法
【学ぶ科目】
- 会社法・商法
- 商業登記法(書式含む)
【重点ポイント】
- 条文構造が複雑なため、理解と問題演習をセットで進める
- 商業登記法では書式の種類・申請の流れを習得
- 主要4科目(民法・不登法・会社法・商登法)の過去問をすべて終わらせる
- 書式の解き方をパターン化し始める
【到達目標】
- 主要4科目の過去問を1周以上
- 会社法・商業登記法の基本論点を網羅
- 書式の雛形を自力で再現できるレベルに近づける
12月〜2月:マイナー科目(民訴・民執・民保・供託・司法書士法・憲法・刑法)
【学ぶ科目】
- 民事訴訟法
- 民事執行法
- 民事保全法
- 供託法
- 司法書士法
- 憲法
- 刑法
【重点ポイント】
- マイナー科目は出題範囲が比較的狭いため、効率的にインプット
- インプットと同時に短答式(択一式)の過去問で反復
- 「得点源」ではなく「落とさない科目」として確実に得点ラインを確保
- 主要科目の総復習も並行して継続
【到達目標】
- 全マイナー科目のインプット完了
- 過去問で基礎レベルの正答率を安定させる
- 全科目で最低限の知識の穴をなくす
3月〜本試験:総仕上げ(過去問・模試・総復習)
【学ぶ科目】
- 全科目
- 特に主要科目の総復習と記述式対策
- 過去問・模試・予想問題
【重点ポイント】
- 過去問を最低3周し、「理由まで説明できる状態」にする
- 書式は雛形とパターンを使って繰り返し解く
- 模試で時間配分・本番形式に慣れる
- 苦手分野の反復と論点の穴埋めを継続する
【到達目標】
- 本番形式で時間内に確実に解ける状態
- 過去問の頻出論点を完全に定着
- 書式の基本パターンを再現し、ミスを減らす
司法試験の短期合格を目指すためのコツ
限られた時間の中で合格を目指すためには、優先順位をつけた学習計画や、インプットとアウトプットのバランスを意識した勉強法がカギになります。
ここでは、短期合格を目指すための具体的な方法を解説します。
情報を集約させる
短期合格を目指すには、情報を分散させず、一つのテキストや講座に集約することが大切です。
複数の教材に手を出すと、内容の重複や情報の違いに混乱し、かえって非効率になります。
信頼できるテキストや講義を軸に学習を進め、そこに必要最低限の補助教材を加える程度にとどめましょう。情報を一元化することで、理解が深まり、復習の効率も格段に上がります。
基礎知識・重要知識に絞って勉強する
試験範囲のすべてを網羅しようとしないことも短期合格への鍵となります。
出題数の多い主要4科目(民法・不動産登記法・商法・商業登記法)を中心に、基礎知識と重要知識に絞って学習しましょう。
特に、過去問で繰り返し問われている論点は、毎年出題される可能性が高い超重要知識です。これらの知識は完璧に覚えることで、確実に得点源にできます。
まずは基本的なテキストを何度も読み込み、過去問演習を通して知識の精度を高めることに集中しましょう。
類似知識を区別できるようにする
司法書士試験では、似たような条文や制度が多数存在し、これらを混同して誤答してしまうケースが少なくありません。短期合格を目指すには、この類似知識を正確に区別することが非常に重要です。
たとえば、「善管注意義務」と「自己と同一の注意義務」のように、似ているようで異なる概念を比較しながら学習しましょう。
テキストで関連するページを行き来したり、自分なりに表や図を作成して違いを整理したりすると効果的です。
過去問を解く際も、選択肢のどこが違うのかを意識して解き、間違えた問題はなぜ間違えたのかを徹底的に分析してください。
司法書士試験の概要

以下では、司法書士試験の概要を紹介します。
受験資格
司法書士試験を受験するための資格要件は、特に設けられていません。これは、様々な経歴の人々に法務への道を開くためです。
つまり、法学部を出ていない方でも、別の職種で働いてきた社会人の方でも、だれでも受験することができます。学歴や職歴は問われず、受験の機会が公平に与えられているのが、司法書士試験の大きな特徴になっています。
受験料
司法書士試験の受験料は8,000円です。
この受験料は収入印紙で納める必要があります。収入印紙は郵便局や一部の法務局で購入でき、受験申請の際には申請書に収入印紙を貼付して提出する必要があるため、収入印紙・受験料の納付ともに忘れずに行うようにしましょう。
試験日程
司法書士試験の筆記試験は、例年7月の第1または第2日曜日に実施されます。
例年、試験は午前と午後に分かれて実施され、午前の部は9時30分から11時30分、午後の部は13時から16時まで行われます。1日を通した試験となっているため、問題を解き切る体力も必要になります。
また、司法書士試験には口述試験もあります。これは例年10月中旬~下旬の平日に行われていて、筆記試験の合格発表から約2週間後です。口述試験も午前と午後の組に分かれて実施されています。
口述試験は面接方式で、試験時間は15分程度です。受験生1人に対して面接官が2人おり、それぞれが受験生に質問し、それに口頭で答える形式となっています。
出願期間
司法書士試験の出願期間は、例年5月上旬から中旬にかけて行われます。年度ごとに出願期間の若干のばらつきがあるため、詳細な日程については年度ごとに確認を行いましょう。
また、願書は法務局または地方法務局の総務課で入手できます。受験申請書を窓口で直接受け取ることもできますが、郵送で請求することも可能です。出願に際しては、必要な書類を揃え、期限内に提出するようにしましょう。
試験科目
司法書士試験の試験科目は、午前の部と午後の部に分かれています。
午前の部では、憲法、民法、刑法、商法(会社法)の4科目が実施されます。これらの科目は、択一式の問題形式で出題され、基本的な法律知識を問われます。
午後の部では、民事訴訟法、民事保全法、民事執行法、司法書士法、供託法、不動産登記法、商業登記法の7科目が実施されます。午後の試験は、択一式と記述式の問題が含まれ、特に不動産登記法と商業登記法については、実務的な内容が問われる記述式問題が出題されます。
難易度
| 年度 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
令和7年度(2025年度) | 5.2% | 14,418人 | 751人 |
令和6年度(2024年度) | 5.3% | 13,960人 | 737人 |
令和5年度(2023年度) | 5.2% | 13,372人 | 695人 |
令和4年度(2022年度) | 5.2% | 12,727人 | 660人 |
令和3年度(2021年度) | 5.1% | 11,925人 | 613人 |
令和2年度(2020年度) | 5.2% | 11,494人 | 593人 |
令和元年度(2019年度) | 4.4% | 13,683人 | 601人 |
平成30年度(2018年度) | 4.3% | 14,387人 | 621人 |
平成29年度(2017年度) | 4.1% | 15,440人 | 629人 |
平成28年度(2016年度) | 3.9% | 16,725人 | 660人 |
上記の表は、司法書士試験の過去10年の合格率・受験者数・合格者数です。
毎年1万人を大きく超える人数がこの司法書士試験に挑戦し、合格するのはたったの600~700人程度です。合格率はなんと4~5%程度で、かなり低くなっています。
この合格率を見ても、司法書士試験がかなり難しいことが分かります。ただ、勉強すればどんな人にも合格のチャンスはあるので、あきらめずに勉強し続けることが大切です。
出典:法務省
司法書士の勉強法まとめ
この記事では司法書士の勉強法や、科目別の効率的な学習方法、1日の適切な学習時間を紹介しました。
司法書士試験に向けて、効果的な勉強法をご紹介しました。初心者の方には、適切な学習時間の配分や科目ごとに合った勉強法が重要です。
継続して知識を深めることが合格への近道となります。自分なりの勉強スタイルを見つけ、着実に実力をつけていきましょう。