土地家屋調査士の独学におすすめのテキスト・問題集ランキング11選!
更新
土地家屋調査士は不動産取引において欠かせない専門資格です。この資格取得には自己学習が不可欠ですが、学習教材の選択に迷う方が多いでしょう。
そこで今回は、合格率や評判の高い土地家屋調査士試験の独学教材をランキング形式でご紹介します。このランキングを参考に効率的な学習を心がけ、確実に資格取得を目指しましょう。
人気講座ランキング

 もっと見る>
もっと見る>- トップクラスの実績に裏付けられた抜群の指導力

 もっと見る>
もっと見る>- 長年に渡り業界最高の合格実績を維持!

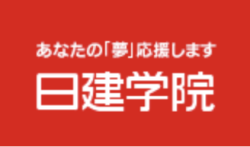
- 出題傾向を徹底分析した教材が魅力
このページにはプロモーションが含まれています
土地家屋調査士の独学におすすめのテキスト・参考書7選
土地家屋調査士は、不動産取引で必要不可欠な「表示に関する登記」を行う専門家です。この登記は法律で義務付けられており、需要が高まっています。
しかし、土地家屋調査士の合格率は例年8~9%で、2024年度試験の11.0%が直近10年で最高の数値となっており、非常に難易度の高い試験を突破しなければなりません。そのため、十分な勉強と質の高いテキストや参考書が不可欠です。
出典:法務省
土地家屋調査士受験100講

https://www.amazon.co.jp
「土地家屋調査士受験100講」は、土地家屋調査士試験に向けた学習において誰もが認めるバイブル的存在の参考書です。
この1冊で、登記法から調査士法理論に至るまで、試験で問われる重要事項をすべて網羅しており、深い理解を助ける内容となっています。
効果的な学習ができるこの参考書は、全国の多くの合格者に活用されてきた実績があり、信頼性という面では圧倒的なものがあります。
実績豊富な資格学校のノウハウを網羅
「土地家屋調査士受験100講」は、長年の実績を持つ予備校が出版した信頼できる参考書です。理論編2冊と書式編1冊の計3冊で構成され、専門知識が分かりやすく解説されています。
この参考書では、登記法から調査士法理論まで、試験対策が網羅されています。多くの合格者がこの参考書から豊富な情報を学び、試験に必要な知識とスキルを十分に身につけてきました。幅広い知識が詰まったこの参考書の価値は確かなものです。
土地家屋調査士試験は複雑な概念を順序立てて理解しなければならず、難易度の高い試験です。しかし、この参考書を用いれば苦手分野の克服にも役立ち、繰り返し読むことで、確実に合格に必要な力が身につくでしょう。
辞書としても使える
この参考書は、理論編2冊と書式編1冊の計3冊から構成されています。理論編(2)は民法について詳しく解説していますが、内容が難解で分量も多いため受験対策専用のテキストとしては不向きな面もあります。
一方、書式編は目次が整理されているため辞書のように使うことができます。書式を調べる必要が生じた際にその都度参照できるのが特徴です。
土地家屋調査士六法
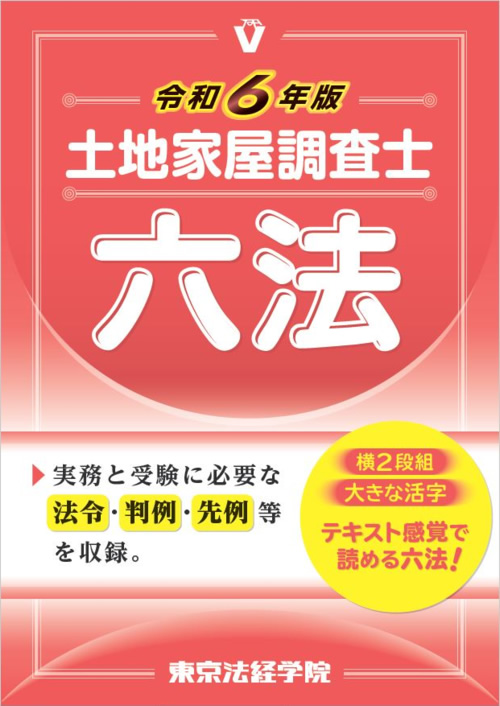
https://www.amazon.co.jp
土地家屋調査士試験に合格するためには、専門的な六法が必須です。
一般的な六法では不足している登記関連の法令や判例が収録された、東京法経学院から出版されている「土地家屋調査士六法」がおすすめです。この六法は、土地家屋調査士試験対策に長年携わってきた専門家によって編纂され、試験に必要な法律知識を網羅しています。
内容の充実度は随一
土地家屋調査士試験の勉強では、専門的な法律知識を理解することが非常に重要です。その中でも「土地家屋調査士六法」は内容の充実度が抜群です。
この六法には、一般的な六法では網羅できない不動産登記法に関する判例や先例の詳細な解説が記載されており、関連する他の法令の具体的な条文番号まで掲載されています。
幅広い情報が収録されているため、条文だけでなくその背景にある法理や判例知識、関連法令まで一度に学習できます。これにより効率的な自習が可能になるだけでなく、法の体系性や意義を深く理解することができます。
見やすさにも定評
土地家屋調査士試験に向けた効率的な学習を支援する「土地家屋調査士六法」は、横書き2段組のレイアウトで読みやすさに優れています。
不動産登記法の各条文には関連判例の要旨が掲載されており、理解を深めることができます。さらに、関連法令の条番号も記載されているため、法令間の関連性を一元的に調べられます。
土地家屋調査士試験 最速! 書式作図テクニック

https://www.amazon.co.jp
「土地家屋調査士試験 最速! 書式作図テクニック」は、独学で受験する際の最大の課題である書式の作図に特化したテキストです。豊富な説明図と明瞭な解説を通して、一人で学習する際の理解を深めることができます。
著者の中山祐介氏は、さいたま登記測量の代表を務める他、土地家屋調査士、行政書士、測量士の資格を持ち、土地家屋調査士試験で全国1位の実績を収めるなど、その専門性は高く評価されています。
中山氏が受験生時代に蓄積した経験と研究に基づき、作図用具の使い方や加工方法、さらには各種法定図面の迅速かつ正確な作図方法などが紹介されています。
こうした独学では得がたい貴重な情報が詰まったテキストを活用することで、困難な作図問題にも対応できる力が身につくでしょう。
独学者の苦手な作図に特化
独学で土地家屋調査士試験に挑戦する受験生にとって、作図対策は試験合格の鍵を握り、このテキストはその領域に特化しています。
著者の中山祐介氏が、自身の受験生時代の経験を活かし、体系立てた作図方法を公開しています。適切な作図用具の選び方から、独自の加工方法まで詳しく解説されています。
特に注目すべきは、確実かつ速やかに各種法定図面を描く技術です。一般的な独学では習得が難しい点ですが、試験対策として非常に重要です。中山氏による丁寧な解説により、土地所在図、地積測量図、各階平面図、建物図面など、様々な図面作成が可能になります。
初心者でも分かりやすいテキスト構成で、三角定規の使い方から作図の順序まで丁寧に解説されています。さらに、ボールペンなどの文房具の選び方までアドバイスされており、独学での学習を進める受験生にとってありがたい一冊です。試験に初めて挑戦する人にも役立つ、まさに完璧な参考書と言えるでしょう。
土地家屋調査士「測量計算と面積計算」

https://www.amazon.co.jp
「測量計算と面積計算」は、土地家屋調査士試験の対策として最適な参考書です。
座標の求め方から面積計算まで網羅的に解説されており、特に実務で必要となる電卓の効率的な使い方についても詳しく記載されています。試験では時間が限られているため、電卓を素早く操作できることが求められます。
さらに理解度を確認するための豊富な問題が収録されているため、効率的に学習を進められます。概念から計算手順、問題解決まで一貫して学べる総合的なテキストとして高い評価を得ています。
土地家屋調査の複雑な計算に対応
「測量計算と面積計算」は、複雑な計算でも理解しやすいように、仕組みを明確に解説した書籍です。特に、土地家屋調査士試験で欠かせない電卓を使った計算方法を詳しく記載しており、限られた試験時間内でも素早い操作が可能になります。
従来は「fx-991ES」や「fx-993ES」がカシオの定番電卓でしたが、最近では「fx-JP500」が多くの学校や予備校で推奨されるようになりました。本書では、fx-JP500の具体的な操作方法を具体的に教えています。fx-JP500は複素数計算にも対応しており、より高度な計算も可能です。
また、同シリーズの「登記申請書と添付画面」と内容が連携しているため、セットで使うことで初学者でも書式問題に対応できます。実務で必要なスキルを効率良く身につけ、試験や実生活で活用することができます。
土地家屋調査士試験 関数電卓必勝活用術

https://www.amazon.co.jp
「土地家屋調査士試験 関数電卓必勝活用術」は、土地家屋調査士試験に向けて電卓の効果的な使い方を学べる実践的な参考書です。著者の斎木光一氏は、日建学院の講師として長年の経験を持ち、受験生が短期間で電卓の操作を習得できるよう工夫されています。
本書では、土地家屋調査士試験で広く使われているカシオ製「fx-JP900」の活用法に焦点を当てています。この電卓の独特な操作方法を確実に身につけることで、試験の問題をスムーズに解答できるようになります。
ただし、複素数計算については詳しく扱われていないため、その部分に不安がある受験生は別のテキストを補助的に利用する必要があるかもしれません。
しかし全体としては、「土地家屋調査士試験 関数電卓必勝活用術」は電卓の使い方を効率的に学習し、試験対策に役立つ優れた一冊と言えます。
複素数で解く!関数電卓による測量計算

https://www.amazon.co.jp
「関数電卓による測量計算」は、複素数を活用した測量計算の手法を実践的に解説しており、土地家屋調査士試験の合格はもちろん、実務現場でも直ちに役立つ内容となっています。著者の豊富な経験に基づく具体的な学習法が紹介されており、試験対策と実務の両面をカバーするオリジナル練習問題も収録されています。
このように、理論と実践のバランスを重視した構成になっているため、測量計算を全体的に理解し、様々な問題に対応できる力を身につけることができます。ただし、説明に使用されている電卓が古い型であるため、新しい電卓を使う人には少し対応が難しい面もあります。
土地家屋調査士になりたいと思ったらはじめに読む本

https://www.amazon.co.jp
「土地家屋調査士になりたいと思ったらはじめに読む本」は、土地家屋調査士試験の独学対策に最適な入門書です。著者の木村真弓氏は、LEC東京リーガルマインドの人気講師で、豊富な教育実績と経験から信頼されています。
この本は試験対策だけでなく、土地家屋調査士のライフスタイルや仕事内容についても詳しく解説しています。特に5人の実務家の開業までの道のりと奮闘ぶりが描かれており、具体的なキャリア像を描くことができます。
さらに短期合格のためのスケジュールが掲載されており、計画面も含めた効率的な学習が可能です。
土地家屋調査士の独学におすすめの問題集・過去問題集4選
土地家屋調査士 択一式(記述式)過去問

https://www.amazon.co.jp
「土地家屋調査士 択一式過去問(または記述式過去問)」は、法的思考力と解答力の育成を目指した問題集です。
豊富な内容と高い質が本書の特徴です。択一式問題は8年分を収録しており、短期間で解き終えることはできません。時間をかけて取り組む価値がある問題の宝庫です。
著者の斎木光一氏は、戸田校の講師として実績が評価されています。明晰な法的思考力と解答力を活かして一問一問丁寧に作成された問題は、参考書を超える質を備えています。本書を活用することで、斎木氏の優れた思考力と解答力を身につけることができるでしょう。
本番さながらの演習ができる
この参考書の最大の魅力は、実際の試験に即した形で演習ができる点にあります。過去問題を単に掲載しているだけでなく、問題を分野別に整理し、詳しい解説も付けられているため、自学自習をする人でも使いやすくなっています。
法的問題を正しく理解するには、専門知識だけでなく法的思考力も必要不可欠です。この参考書には一つひとつの問題に対する丁寧な解説があり、それを読むことで法的思考力を養うことができます。そのため、より深く本質に迫ることができます。
さらに、最新の令和5年度の問題までが本試験と同じ形式で掲載されているため、まるで模擬試験を受けているかのような実戦的な演習が可能です。この参考書を活用することで、実際の試験と同等の厳しい練習ができるだけでなく、自然と法的思考力も身につきます。
鉄則!土地家屋調査士内堀式択一過去問徹底理解塾

https://www.amazon.co.jp
「鉄則!土地家屋調査士内堀式択一過去問徹底理解塾」は、土地家屋調査士試験に非常に効果的な参考書です。この問題集には、初心者から上級者まで幅広いレベルの過去問が収録されており、実践的な問題に取り組むことで、試験で求められる知識と応用力を養うことができます。
さらに、法令や判例を用いた丁寧な解説により、正解を暗記するだけでなく問題の背景にある理論や法理を深く理解することが可能です。一問一答形式なので、重要なポイントを逐次確認しながら学習でき、実際の場面で適切な法令や判例を思い浮かべて答えを導き出せるよう訓練できます。
片手間でハイレベルを理解できる
「鉄則!土地家屋調査士内堀式択一過去問徹底理解塾」は、難しい過去問題を理解しやすくするためのコンパクトなサイズで、どこでも手軽に学習できるように設計されています。
学習方法の特徴は、問題と解答をQ&A形式で提示し、何度も読み返すことで問題の内容と解答を理解することができます。
単なる答え合わせや記憶力に頼るのではなく、Q&Aを繰り返すことで、思考力と表現力を養成します。これにより、選択肢式問題だけでなく論述式問題への対策も可能になりました。
土地家屋調査士過去問マスター シリーズ

https://www.amazon.co.jp
「土地家屋調査士過去問マスターシリーズ」は、充実した内容と豊富な問題数が魅力の問題集です。
昭和から最新までの過去問を網羅し、基礎から応用レベルまで幅広く対応しています。基本問題と応用問題に分かれているため、初心者から上級者まで、それぞれのレベルに合わせて効率的な学習が可能です。
また、この問題集では効率的な学習方法や、各法規ごとの解答のコツを学ぶことができます。例えば、択一式の民法や不動産登記法の問題では、正確な概念関係の把握や論点の明確化が重要視されます。一方、記述式の問題では、素早く正確な計算力や事例の正確な理解を目的としています。
過去問を徹底的に分析し、多数の問題を収録しているこの問題集は、土地家屋調査士受験生にとって非常に助けになるものとなります。
土地家屋調査士 過去問セレクト

https://www.amazon.co.jp
「土地家屋調査士 過去問セレクト」は、20年以上にわたる本試験の過去問題を精選した参考書です。この一冊で重要なポイントを把握し、様々な問題を学習することができます。しかし、出版元の廃業に伴い現在は絶版となっているため、入手が困難な状況にあります。
ページ数は400ページ程度と膨大なものではありませんが、その内容は質が良く、非常に高い評価をされています。ただし、他の参考書や問題集と併せて活用することで、より幅広い学習が可能となります。
入手の難しさや内容の網羅性には課題があるものの、この問題集は着実な学習を進めるための良質な一冊と言えるでしょう。
土地家屋調査士のテキストはどう選ぶ?
土地家屋調査士試験に合格するには、適切な対策テキストを選ぶことが重要です。
ここでは合格を左右するとも言える土地家屋調査士のテキストの選び方について解説していきます。
理解しやすい解説があるかどうか
土地家屋調査士試験の効果的な勉強には、理解しやすい解説と実践的な技術指導が含まれたテキストを選ぶことが重要です。解説の中で正答に至る過程が丁寧に説明されており、問題解決の考え方を身につけられるかどうかを重視しましょう。
また、書式問題では電卓や定規の使い方が分かりやすく記載されているテキストを選ぶことで、知識面だけではなく技術面でも試験に対応できる高水準に達することができます。
このように、理論と実践の両面からサポートしてくれるテキストを選べば、確実な合格に向けて着実に力をつけていくことができます。
最新の法改正に対応しているか確認
特に民法をはじめとする関連法令は頻繁に改正されるため、利用するテキストが常に最新の法改正を反映していることが大切です。古いテキストを使っていると、新しい制度や改正点を見落とし、それらに関する出題に適切に対応できなくなってしまう可能性があります。
テキストの出版年月や改訂時期を確認することで、内容の新しさを判断することができます。また、出版社のウェブサイトなどで、テキストの法令対応状況を事前に確認するのも賢明です。
テキスト選びは個人の理解度や学習スタイルにも左右されますが、法改正対応状況を慎重に吟味し、総合的に自分に合ったテキストを選ぶことが肝心です。
口コミや評判は必ずチェック
試験対策テキストを選ぶ際は、先輩の口コミや評判をチェックすることが重要です。しかし、口コミは人それぞれの意見です。初学者と上級者では求めるものが異なるため、その人の背景などをよく考慮して口コミを見る必要があります。
また、中には、テキストの内容や活用方法についての情報も口コミに記載されていることがあります。具体的な使い方のアドバイスは、購入後の活用に役立つでしょう。
多くの口コミを見ても迷うこともあるかもしれません。そんな時こそ、幅広い意見を参考にして、自分に最適なテキストを見つけることが大切です。安易な選択はせず、自分のスタイルや理解度に合わせて選べば、合格に確実に近づくはずです。
数が少ないのでテキスト選びは慎重に
土地家屋調査士の資格は非常に専門的なため、参考書やテキストの選択肢が限られています。そのため自分に合った学習材料を選ぶには、カリキュラムの新旧、学習量、難易度などを慎重に確認する必要があります。
参考書の種類が少ないので、実際に書店で手にとって比較するのが難しい場合もありますが、大きな書店を訪れれば、複数のテキストを見比べる機会が得られます。手間はかかりますが、自分に合った学習材料を見つけるためには一度足を運んでみる価値はあります。
ただし、分厚く難解なテキストや、法令の改正点が反映されていない古いものもあるので注意が必要です。専門的なテキストであっても、自分が理解できるかどうかが最も重要です。過去の法令情報だけで学習すると出題範囲から外れてしまうリスクもあるため、最新版を選ぶことを忘れないようにしましょう。
参考になる出版社としては、東京法経学院、早稲田法科専門学院、日進学院、LEC等があり、これらの出版社から出されているテキストを中心に見ていくとよいでしょう。
人気講座ランキング

 もっと見る>
もっと見る>- トップクラスの実績に裏付けられた抜群の指導力

 もっと見る>
もっと見る>- 長年に渡り業界最高の合格実績を維持!

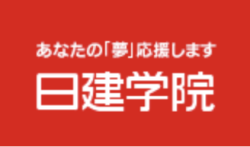
- 出題傾向を徹底分析した教材が魅力
土地家屋調査士を独学で目指すための勉強法
土地家屋調査士の資格取得には、筆記試験と口述試験の2段階があります。筆記試験は年に1回実施され、合格すれば翌年の口述試験を受けられます。両試験に合格すると、ようやく土地家屋調査士の資格が授与されます。
筆記試験の午前は平面測量と作図、午後は民法、不動産登記法、土地家屋調査士法の択一問題と、土地・建物に関する記述式問題があります。口述試験は個別の面接形式で、筆記試験の午後の範囲が対象となります。
合格には計画的な学習が欠かせません。各分野を順を追って学び、必要な知識と技術を身につける必要があります。加えて過去問題を活用して模擬試験を行い、時間配分や問題傾向を把握することも重要です。
出典:日本土地家屋調査士連合会
勉強時間の目安は1000〜1500時間
土地家屋調査士の資格取得は容易なことではありません。試験範囲が広範囲にわたり専門的であるため、合格に必要な勉強時間は1000時間から1500時間と言われています。膨大な知識を身につけ、筆記試験と口述試験の両方に対応できるレベルの理解力を得るには、相当な時間を要するのです。
例えば、1日3時間の学習時間を確保したとしても、1年以上かかる計算になります。3時間は確保できそうな時間と思えますが、実際に1年間持続できるかどうかは、個人の生活環境、仕事の負荷、学習能力次第です。勉強時間を十分に確保するだけでなく、その時間を継続して確保し、効果的に活用できるよう計画を立てることが重要になります。
具体的には、1日のどの時間帯に学習するか、どのペースで進めていくか、休憩をどの程度入れるかなど、細かい部分まで計画を立てることが不可欠です。時間管理を上手く行えば、資格取得がより現実的なものになるでしょう。
短期合格には午前の部の免除が必須
土地家屋調査士試験は、筆記試験が「午前の部」と「午後の部」に分かれており、両方に合格する必要があります。
しかし、「午前の部」は、測量士、測量士補、一級建築士、二級建築士の資格を持つ人が免除を受けられるため、受験者数が毎年数十人程度にとどまっています。
特に、測量士補の資格は取得が比較的容易なため、9割以上の受験生がこの試験に合格し、「午前の部」を免除しています。5月に行われる測量士補試験に合格すれば、「午前の部」を受けずに「午後の部」に進むことができます。
「午後の部」は専門知識を問う難易度の高い試験ですが、「午前の部」を免除することで、受験生は心に余裕を持って挑戦できます。このように、免除制度を利用すれば資格取得の道のりをスムーズに進めることができます。資格取得は険しい道のりですが、賢く制度を活用することで、その困難を乗り越えられるのです。
まずは学習計画の作成
土地家屋調査士の試験は幅広い知識と実践的な技術が求められ、合格には適切な学習計画が重要となります。はじめに長期的な目標を設定し、そこから具体的な短期目標や日々の学習計画を立てましょう。各分野の理解度や難易度、出題割合を考慮し、法律分野には十分な時間を割く必要があります。
しっかりとした学習計画を立てることで、モチベーションの維持や進捗管理も容易になります。ただし、状況に応じて柔軟に計画を調整することも大切です。
最重要なのは過去問を解くこと
土地家屋調査士の資格取得を目指す際、独学でも効果的な勉強法は過去問題に取り組むことです。特に択一式問題では過去問を繰り返し解き、問題のパターンを十分に把握することが重要です。
間違えた問題や理解が曖昧な箇所については、テキストに戻って確認し、繰り返し学習することで知識を定着させる必要があります。つまずいたポイントをメモし、振り返りながら修正を重ねることで、確実な理解を深めていきます。
また、土地家屋調査士試験では法令や規則に関する出題が多いため、条文を丸暗記するのではなく、六法全書を活用して具体的な内容を理解することが求められます。
過去問題は出題範囲を把握するだけでなく、試験対策としても有効活用できます。自己採点を行いながら繰り返し取り組むことで弱点を明確にし、効率的な対策を立てることができます。このように独学でも、過去問題を中心とした着実な学習を重ねることで、土地家屋調査士の資格取得が可能となります。
不動産登記の専門用語と概念を把握
不動産登記の専門用語と概念を正しく理解することは、土地家屋調査士になるための重要な課題です。特に、似た表現が多く存在するため、用語の微妙な違いを正確に把握する必要があります。例えば「表題登記」と「表題部の登記」は、異なる概念を指しています。このような専門用語の意味をしっかりと区別できるよう、丁寧に学習することが求められます。
不動産登記法には、法律用語の背景にある概念を理解しなければならない箇所が数多くあります。現場で適切な判断を下すためには、それぞれの用語が何を指しているのか正確に把握しておく必要があります。
そのためまずは参考書で用語と概念を学習し、次に問題演習を通して知識を定着させることが重要です。参考書を活用すれば、用語の解説や法律解釈を詳しく学ぶことができます。そして問題演習を繰り返すことで、理解を深め、自分のものとすることができるでしょう。
民法は出題範囲を重視
土地家屋調査士の資格取得には、民法の学習が必要です。民法の筆記試験では、「総則」「物権」「相続」の3分野から各1問が出題されるため、これらの範囲を中心に学習する必要があります。民法の出題が始まったのは平成16年度以降なので、最新の法改正や判例を反映したテキストを使用し、法の解釈や理解の技術を身につけることが大切です。
また、行政書士などの他資格の過去問題も活用することで、多角的な視点から理解を深めることができます。出題範囲の理解、最新情報に基づく学習、他資格の過去問題活用が資格取得への確実な道筋となります。
申請書の型を覚える
土地家屋調査士の資格取得には、申請書の様式を段階的に学ぶことが重要です。まず土地や建物の問題について多角的な理解が求められます。そのうえで、基本的なケースから覚えていく学習法が有効でしょう。
土地の問題は比較的限られているため、基本的な様式を理解し、それをベースに複雑なケースへの対応力を養うことができます。一方で建物の問題は事例が増えるにつれて複雑さも高まります。そのためまずは基本をしっかり理解し、徐々に難易度を上げていくことが重要となります。
このように、基本から始めて徐々に複雑な問題に挑戦することで、申請書の様式を洗練された形で習得できます。その結果、資格取得に大きく貢献することとなります。
電卓を使った計算に慣れる
土地家屋調査士の資格取得には、電卓を用いた計算能力が欠かせません。土地問題では、座標値の計算精度が極めて重要です。ささいな誤りが面積や辺長の計算に連鎖的な影響を及ぼし、最終的な結論を左右する可能性があるのです。
特に、点の移動、放射計算、交点計算、補正計算の4つの計算手法は必須です。これらは土地家屋調査士に求められるスキルの一部であり、電卓を確実に操れることが何よりも大切なのです。計算ミスは解答全体に影響を及ぼすため、しっかりとマスターする必要があります。
電卓操作は日常的に求められるため、日頃から電卓に親しむことが重要です。電卓との馴染みを深め、計算の速さと正確さを高めると合格の可能性もあげられるでしょう。
独学が厳しいなら通信講座も視野に
土地家屋調査士の資格取得は極めて難しく、全国的に見ても合格率は10%に満たない厳しい現状があります。一人で勉強を続けながら合格を目指すのは容易なことではありません。そこで、通信講座の受講も一つの選択肢です。各講座では効率的な学習が可能で、社会人でも十分に学べる環境が用意されています。
中でもアガルートの土地家屋調査士講座は、卓越した合格実績が魅力的です。令和5年度の合格率は一般の6.56倍である驚異的な63.41%を記録しました。さらに、合格者には受講料全額返金の制度もあり、他講座とは一線を画しています。
資格取得に向けた最適な環境が整っているアガルートの通信講座は、是非一度チェックしてみる価値があるでしょう。
土地家屋調査士おすすめテキストまとめ
独学で土地家屋調査士の資格取得を目指す方々向けに、初心者から上級者まで幅広いレベルに対応したテキストや問題集をランキング形式で紹介しました。
実際の試験問題に近い内容の参考書や、学習スタイルや目標に合わせて選べるラインナップが揃っています。
ぜひこの記事を活かしながら自分に合った参考書を見つけて、土地家屋調査士合格を目指してみてください!
人気講座ランキング

 もっと見る>
もっと見る>- トップクラスの実績に裏付けられた抜群の指導力

 もっと見る>
もっと見る>- 長年に渡り業界最高の合格実績を維持!

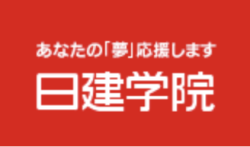
- 出題傾向を徹底分析した教材が魅力