司法書士の平均年収はいくら?月収を上げる方法や主な業務内容を解説
更新
司法書士の年収がどのくらいか、気になっている方も多いのではないでしょうか。
実は、独立開業と勤務では収入に大きな差があり、年収を上げるための方法もさまざまです。
本記事では、司法書士の平均年収や月収の実態を詳しく解説し、収入を上げるための具体的な方法や主な業務内容についても紹介します。
このページにはプロモーションが含まれています
司法書士の全国平均年収は1121.7万円

厚生労働省の調査によると、全国の司法書士の平均年収は1121.7万円となっています(令和6年)。これは令和4年の平均年収971.4万円から約150万円上昇した数字です。
ただし、この数字は独立開業している司法書士も含めた全体の平均であり、勤務形態によって大きく差があります。勤務司法書士の平均提示年収は約394万円と報告されており、300~399万円の年収帯が全体の55.72%を占めています。
一方、独立開業した司法書士の平均年収は1,000万円程度で、30~40代から高収入を得て、2,000~3,000万円まで稼ぐ司法書士も存在します。
(出典:職業情報提供サイト Jobtag)
司法書士の年収は勤務形態によって大きく差が出る
独立開業での平均年収は1000万円〜5000万円
独立開業している司法書士の収入は、その実力や営業力によって大きく差が開きます。
独立開業司法書士の約30.8%が年収1,000万円から4,999万円の収入を得ており、これが最も多い年収帯となっています。
ただし、独立開業して収入を得るためには、専門分野での実績作りや顧客との信頼関係構築が不可欠です。
特に都心部や企業が集中する地域で開業している司法書士は、より高額な案件を獲得しやすく、中には2,000万円から3,000万円の年収を達成している司法書士も存在します。ただし、このような高収入を得るためには、司法書士としての専門知識だけでなく、効果的な集客ノウハウや営業力も必要不可欠となります。
企業勤務での平均年収は約400万円程度
一方で、司法書士として企業や法律事務所に勤務する場合、平均年収は約400万円程度となっています。勤務司法書士の収入で最も多いのは「300~400万円未満」で全体の21.0%を占め、次いで「400~500万円未満」が18.3%となっており、一般的なサラリーマンの平均年収(461万円)とそこまで変わらない水準です。
ただし、東京や大阪などの都市部では平均600万円程度まで上がる傾向があり、経験やスキルによって年収1000万円を超える勤務司法書士も存在します。年収は経験年数やキャリア、勤務地域によって大きく左右されるため、実務経験を積むことが収入アップの鍵となります。
(出典:日本司法書士会連合会 司法書士白書 2021年版 / 国税庁)
司法書士の年収に性別・年齢は関係ある?
男性の平均年収は約650万円、女性は約450万円と差がありますが、これは能力差ではなく働き方の違いによるものです。女性は育児や家事との両立のため、パートタイムで働くケースが多いためです。フルタイムで働く女性司法書士の中には男性以上の収入を得ている方も少なくありません。
年齢別では、経験やスキルの蓄積に比例して収入が上がる傾向があります。20代で約463万円、30代で約823万円、40代で約937万円、50代で約1,043万円、60代で約979万円となっています。
司法書士は性別に関わらず活躍できる職業であり、年齢を重ねるごとに収入アップが期待できる魅力的な仕事といえるでしょう。
(出典:賃金構造基本統計調査 令和3年賃金構造基本統計調査)
※「所定内給与額」と「年間賞与その他特別給与額」を合計した額から算出。また、法務従事者として算出しており、弁護士等も含まれる)
そもそも司法書士とは?
司法書士は、不動産登記や商業登記、相続手続きなどの法律業務を行う専門職です。
ここでは、司法書士の役割や業務内容について詳しく解説します。
司法書士の仕事内容
司法書士は、法律上の手続きを専門に行う法律家です。主な業務は不動産登記や商業登記の代理、法務局・裁判所・検察庁に提出する書類の作成などが挙げられます。
具体的には、不動産の売買や相続時の登記手続き、会社設立・役員変更などの商業登記、成年後見業務、相続関連業務などを担当しています。また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所での訴訟代理も行えます。
司法書士は「市民の身近な法律家」として、依頼人の権利を守り、法的問題の解決をサポートする重要な役割を担っています。2024年からは相続登記の申請が義務化され、社会的にニーズが高まっています。
司法書士になる方法
司法書士になるには、法務大臣が実施する司法書士試験に合格する必要があります。この試験は非常に難関で、合格率は令和3年度実施のもので5.1%となっています。(出典:法務省 令和3年度司法書士試験の結果について)
試験内容は、憲法・民法・商法・不動産登記法・商業登記法などの法律科目が中心です。合格後は、司法書士会に登録し、実務研修を受けることで正式に司法書士として活動できるようになります。
大学や専門学校での法律の学習は必須ではなく、独学でも合格は可能です。しかし、法的知識と論理的思考力が求められるため、計画的な学習が重要です。また、司法書士事務所での実務経験を積むことも、将来独立開業する際に役立ちます。
司法書士として働くやりがい
司法書士として働くやりがいは、人々の権利や財産を守る重要な役割を担うことにあります。不動産登記や会社設立、相続手続きなど、人生の重要な場面で専門知識を活かして依頼者をサポートできる喜びは大きいでしょう。
特に、複雑な法律問題を解決し、依頼者から感謝の言葉をいただけたときの達成感は何物にも代えがたいものです。また、成年後見人として判断能力が不十分な方の生活や財産を守る業務など、社会的に意義のある仕事に携われることも大きなやりがいといえます。
司法書士は単なる書類作成の専門家ではなく、国民の権利擁護と公正な社会の実現に貢献する重要な法律専門家です。依頼者の人生に寄り添いながら、法的な専門知識で問題解決をサポートできる点が、この仕事の最大の魅力といえるでしょう。
弁護士と異なる点は?
弁護士と司法書士は法律の専門家ですが、業務範囲に大きな違いがあります。弁護士は訴訟代理人として全ての裁判所で依頼者を代理できるのに対し、司法書士は簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟代理に限定されています。
また、弁護士は法律相談全般を扱えますが、司法書士は登記や供託手続きなど特定分野の相談に限られます。
報酬面でも差があり、弁護士の平均年収が司法書士より高い傾向にあります。司法書士は主に不動産登記や商業登記、成年後見などの専門性の高い業務を担当し、権利関係の書類作成や申請代理を行う専門家として、市民の権利擁護に貢献しています。
司法書士の主な業務内容・報酬額
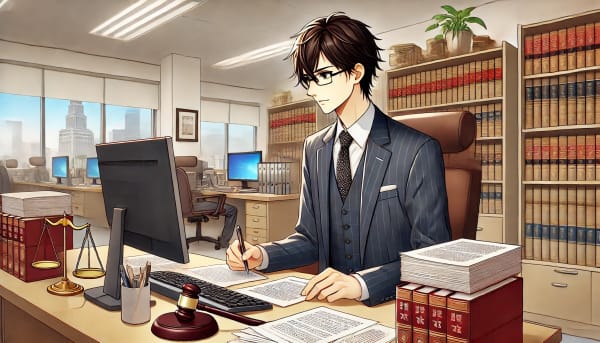
司法書士の業務は、不動産登記や商業登記、相続手続きなど多岐にわたります。
ここでは、主な業務内容と、それぞれの業務で得られる報酬額について詳しく解説します。
不動産登記
業務内容 | 報酬額 | |
|---|---|---|
相続登記 | 被相続人の不動産を相続人名義に変更する登記 | 5万~20万円+登録免許税 |
所有権保存登記 | 所有権の登記がない不動産に対し、初めて所有権を登記する手続き | 5万円~ |
| 所有権移転登記(売買・贈与) | 不動産の売買や贈与により所有者が変わった際の登記手続き | 5万~10万円+登録免許税 |
抵当権設定登記 | 金融機関が融資の担保として不動産に抵当権を設定する登記 | 4~5万円 |
抵当権抹消登記 | 住宅ローン完済後に、登記簿から抵当権を削除する手続き | 5,000円~1.5万円 |
相続登記
相続登記は、被相続人(亡くなった方)の不動産を相続人の名義に変更する手続きです。2024年の不動産登記法改正により、相続発生から3年以内の登記が義務化されました。
司法書士に依頼する費用は一般的に5万円~20万円程度で、不動産の数や状況によって変動します。この費用とは別に登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)がかかります。
司法書士に依頼するメリットとして、不動産の登記漏れ防止、必要書類の収集代行、相続関係説明図の作成などがあります。特に複数の相続人がいる場合や遠方に不動産がある場合は、専門家に任せることで手続きがスムーズに進みます。
相続登記は専門知識が必要な業務のため、単価も比較的高く、少子高齢化の影響で需要も拡大しています。司法書士のキャリアアップにおいても重要な分野といえるでしょう。
所有権保存登記
所有権保存登記とは、所有権の登記がない不動産について初めて行われる所有権の登記です。新築建物の場合、まず表題登記が行われた後に、この所有権保存登記によって「誰が所有者か」を登記情報の甲区に記録します。
この登記は所有者の任意ですが、不動産の売買や抵当権設定などの際には必須となります。特に住宅ローンを組む場合は、金融機関への担保提供のために絶対に必要です。
申請者は原則として表題部に所有者として記録された人が単独で行いますが、その方が死亡している場合は相続人が申請することも可能です。
登記の際には専門的な書類作成が必要となるため、司法書士に依頼するケースが一般的で、1案件あたりの報酬は相場として50,000円程度からとなっています。
所有権移転登記(売買・贈与)
所有権移転登記は、不動産の所有者が変わった際に行う重要な手続きです。売買や贈与によって不動産の所有権が移転した場合、その事実を登記簿に反映させます。
一般的な報酬相場は1案件あたり50,000円~となっており、物件価格によって変動します。例えば2,000万円の物件であれば、約10万円前後が相場です。
必要書類としては、売主側は不動産売買契約書、登記識別情報、印鑑証明書、固定資産評価証明書などが必要です。買主側は住民票や身分証明書が必要となります。
登記申請から完了までは法務局の混雑状況にもよりますが、通常1~2週間程度かかります。登録免許税は固定資産評価額の1,000分の20が基本ですが、土地の場合は特例で1,000分の10となっています。
抵当権設定登記
抵当権設定登記は、住宅ローンなどの融資を受ける際に必要となる重要な登記手続きです。金融機関が融資の担保として不動産に抵当権を設定する際に行われます。
この登記により、債務者が返済不能になった場合、金融機関は担保不動産を競売にかけて債権を回収できる権利を得ることになります。
報酬の相場は融資額によって変動し、1,000万円の融資であれば約4〜5万円程度が一般的です。複雑なケースや高額融資の場合はさらに高くなることもあります。
司法書士は本人確認や意思確認を行い、必要書類の作成から申請手続きまでを代行します。また、金融機関との打ち合わせや期日管理も重要な業務となります。
住宅購入時には必須の手続きであるため、司法書士の主要な収入源の一つとなっています。
抵当権抹消登記
抵当権抹消登記は、住宅ローンなどの完済後に不動産の登記簿から抵当権を消す手続きです。住宅ローンを返済しても自動的に抹消されるわけではなく、自ら申請する必要があります。
この手続きは、金融機関から受け取る抵当権解除証書や委任状などを法務局に提出して行います。報酬相場は5,000円~15,000円程度で、比較的リーズナブルな業務です。
抵当権抹消登記を怠ると、登記上は「抵当権付き物件」のままとなり、将来的に不動産売却の際に支障をきたしたり、相続発生時に手続きが複雑になったりする可能性があります。そのため、住宅ローン完済後は速やかに手続きを行うことをおすすめします。
商業登記
業務内容 | 報酬額 | |
|---|---|---|
会社設立登記(株式会社) | 株式会社を設立する際に必要な登記手続き | 7万~12万円+実費 |
合同会社設立登記 | 合同会社を設立する際の登記手続き | 7万~12万円+実費 |
役員変更登記 | 取締役や監査役などの役員の就任・退任・再任に伴う登記手続き | 1万~3万円/1名 |
本店移転登記 | 会社の本店所在地を変更した際に行う登記手続き | 5万円+実費 |
会社設立登記(株式会社)
会社設立登記は、新たに株式会社を設立する際に必要な手続きです。司法書士は、定款や議事録などの必要書類の作成から登記申請までをトータルでサポートします。
登記される内容には、会社の商号(社名)、本店所在地、事業目的、資本金、役員の氏名などが含まれます。
平成18年5月からの新会社法施行により、最低資本金制度が廃止されるなど制度が大きく変わり、司法書士の役割もさらに重要になっています。
会社設立は専門的な知識が必要なため、ミスなく確実に登記を行うためには司法書士への依頼が一般的です。司法書士は依頼者からヒアリングを行い、適切なアドバイスをしながら手続きを進めます。
また、報酬額の相場は7万円~12万円程度となっています。これに加えて、定款認証手数料5万円や印紙代4万円などの実費が別途必要になります。
合同会社設立登記
合同会社設立登記は司法書士の主要業務の一つです。設立登記の申請は、代表社員(法人の場合はその職務執行者)が本店所在地を管轄する法務局に対して行います。
登録免許税は資本金の1000分の7(最低額6万円)が必要となります。申請には「合同会社設立登記申請書」の作成が必須で、商号、本店所在地、登記事由などを記載します。
添付書類としては、定款、業務執行社員の一致を証する書面、代表社員の就任承諾書、出資財産の払込証明書類などが必要です。
司法書士への報酬額は一般的に7万円~12万円程度が相場となっています。これに加えて定款認証手数料や印紙代などの実費が別途必要となります。
役員変更登記
役員変更登記は、会社の取締役や監査役などの役員に変更があった場合に行う登記手続きです。
役員の就任・退任・再任・任期満了などの変更事項を法務局に届け出ることで、会社の透明性を確保し、第三者に対して正確な情報を公開する重要な手続きとなります。
この登記は変更があった日から2週間以内に申請する必要があり、期限を過ぎると過料の対象となる場合があります。
司法書士に依頼する場合の報酬相場は、役員1名あたり1〜3万円程度で、変更する役員の人数や会社の規模によって変動します。
複数の役員を同時に変更する場合は割引が適用されることもあるため、事前に司法書士に相談することをおすすめします。
本店移転登記
本店移転登記は企業の本店所在地変更を法的に反映させる重要な手続きです。
手続きの流れとしては、まず株主総会で本店移転の議事録を作成し、移転先と日程を決定します。その後、移転から2週間以内に法務局へ登記申請を行う必要があります。
必要書類は移転先が同じ法務局管轄内か管轄外かによって異なります。管轄外移転の場合は、本店移転登記申請書2通、株主総会議事録、株主リスト、取締役会議事録または取締役決定書、印鑑届書、委任状2通などが必要となります。
また、司法書士に本店移転登記を依頼する場合の報酬額は、一般的に5万円前後が相場となっています。ただし、事務所によって料金設定は異なりますので、依頼前に確認することをおすすめします。
裁判所向け書類作成業務
業務内容 | 報酬額 | |
|---|---|---|
遺言書の検認手続き | 自筆証書遺言や秘密証書遺言を家庭裁判所で確認する手続き | 3万~5万円+裁判所提出書類作成費 |
成年後見人の選任手続き | 認知症などにより判断能力が低下した人のために、家庭裁判所が成年後見人を選任する手続き | 7万円~ |
相続放棄の手続き申請 | 被相続人の財産(負債含む)を一切相続しない手続き | 3万円~ |
遺言書の検認手続き
遺言書の検認とは、遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認する手続きです。自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見した場合、相続人は遺言書を家庭裁判所に提出し検認を受ける必要があります。
検認手続きの流れは、まず申立てに必要な書類を揃え、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。その後、裁判所から検認期日の通知が届き、指定された日に相続人が立ち会いのもと、裁判官が遺言書の内容や日付、署名、訂正加筆部分などを確認します。
検認が完了すると検認済証明書が交付され、その後は遺言書の内容に従って相続手続きを進めることができます。なお、公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言は検認が不要です。
司法書士に遺言書検認手続きを依頼する場合の報酬額は、一般的に3万円~5万円程度が相場です。
ただし、相続人が多数いる場合や複雑な事案では追加費用が発生することもあります。裁判所提出書類作成業務として5万円以上かかる場合もあります。
成年後見人の選任手続き
成年後見人の選任手続きは、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行うことから始まります。
申立てができるのは本人、配偶者、四親等内の親族、保佐人などです。申立て後、家庭裁判所による面談調査や鑑定が行われます。
家庭裁判所は後見開始の要件が満たされていると判断すれば、後見開始の審判を行い、成年後見人を選任します。申立ての際に候補者を推薦できますが、必ずしも推薦した人が選ばれるとは限りません。
選任された成年後見人には、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。これは本人の法律上の課題や財産管理の複雑さなどを考慮して決定されます。
司法書士が成年後見申立書類作成を行う場合の報酬相場は7万円程度からとなっています。成年後見人業務は専門知識やスキルが求められる内容であり、単価は高めに設定されています。また、少子高齢化の影響で需要も拡大している業務の一つです。
相続放棄の手続き申請
相続放棄は、被相続人の財産(借金含む)を一切相続しない手続きです。申請は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
必要な書類としては、相続放棄申述書、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本などを準備し提出します。申請後、家庭裁判所から「照会書」が送られてくるので回答を返送します。
手続きは郵送でも可能ですが、回答内容によっては却下されることもあり、一度却下されると再申請できないため注意が必要です。
相続放棄が認められると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。債権者への証明には別途「相続放棄申述受理証明書」の申請が必要です。
司法書士に相続放棄申立書類作成を依頼する場合の報酬相場は3万円~となっています。案件の難易度により報酬額が増減することがあり、別途印紙代や郵券代などの実費が必要になります。
司法書士として年収アップを目指すには

司法書士として年収を上げるには、業務の幅を広げたり、集客力を強化することが重要です。
ここでは、年収アップのための具体的な方法や戦略について詳しく解説します。
他の専門士業と協力する
司法書士が年収アップを目指すなら、弁護士、税理士、行政書士などの他の専門士業との連携が効果的です。
例えば、不動産取引では税理士と連携することで、登記手続きだけでなく税務面のアドバイスも含めた総合的なサービスを提供できます。また、弁護士と協力して相続や債務整理の案件を共同で取り扱うことで、より複雑な案件にも対応可能になります。
このような連携により、単独では受けられなかった案件の紹介を受けたり、ワンストップサービスとして付加価値を高めたりすることができます。専門分野の異なる士業とのネットワークを構築することで、クライアントの多様なニーズに応え、結果として収入増加につながるでしょう。
クライアントとの継続的な関係を構築する
司法書士の収入を安定させるには、一度きりの取引ではなく、継続的なクライアントを確保することが重要です。
企業や不動産会社との長期的な関係構築は、安定した案件獲得につながります。定期的な連絡や情報提供を行い、クライアントの法的ニーズに常に応えられる体制を整えましょう。
また、一つの案件を丁寧に対応することで信頼関係が生まれ、そのクライアントからの紹介という形で新規顧客獲得にもつながります。特に相続や企業法務など、継続的なサポートが必要な分野では、クライアントとの信頼関係が収入アップの鍵となります。
顧客満足度を高めるためのアフターフォローも忘れずに行いましょう。
最初から仕事を限定せずに受ける
司法書士として年収を上げるためには、特に独立開業初期は様々な業務に挑戦することが重要です。不動産登記や商業登記だけでなく、成年後見、相続手続き、債務整理など幅広い分野の仕事を受けることで、経験と実績を積むことができます。
多様な案件を扱うことで、クライアントの幅も広がり、将来的に専門分野を確立する際の基盤になります。また、様々な業務を経験することで、自分の得意分野や高単価で提供できるサービスを見つけることができるでしょう。
初めは小規模な案件でも丁寧に対応し、信頼関係を構築することで、リピートや紹介につながり、結果的に年収アップに貢献します。
司法書士に将来性はあるのか?
司法書士は専門性の高い職業ですが、AIの発展や業界の変化により将来性が気になる人も多いです。
ここでは、今後の需要やキャリアの可能性について詳しく解説していきます。
グローバル化への適応需要
グローバル化の進展に伴い、司法書士の業務にも国際的な要素が増えています。外国人の不動産取得や外資系企業の日本進出に関わる登記手続きなど、国際的な法務ニーズが拡大しています。
特に東京や大阪などの大都市圏では、こうした国際業務に対応できる司法書士の需要が高まっており、英語力や国際的な法律知識を持つ司法書士は差別化が可能です。
また、海外との取引に関連する法的手続きや、外国人の相続問題など、従来の業務にグローバルな視点が求められるケースも増加しています。こうした新たな需要に対応できる司法書士は、将来的に高い収入を得られる可能性があります。
シニア世代向けの対応要請
高齢化社会の進展に伴い、シニア世代向けの法的サポートへの需要が急増しています。特に成年後見制度の利用者は年々増加しており、司法書士への期待も高まっています。
認知症や判断能力の低下に悩む高齢者とその家族にとって、財産管理や権利擁護の専門家である司法書士の存在は不可欠です。また、相続や遺言書作成のサポートも重要な業務となっており、シニア世代の財産保全や円滑な世代間資産移転をサポートする役割も担っています。
このような社会的ニーズの高まりから、高齢者向け法務に特化した司法書士の需要は今後も拡大すると予測されます。シニア世代に寄り添い、複雑な法的問題を分かりやすく説明できるコミュニケーション能力を持つ司法書士は、特に重宝されるでしょう。
ダブルライセンスを活かすと強みになる
司法書士が行政書士などの資格も取得してダブルライセンスを持つことで、業務範囲が大幅に広がります。両資格は試験科目が重複するため、比較的容易に取得できるのが魅力です。
ただし、急いでダブルライセンスを目指す必要はありません。まずは司法書士としての専門性を高め、自分なりのビジネスモデルを確立することが年収アップの近道です。
士業は互いに仕事を紹介し合うネットワークがあるため、できない業務は他の専門家に依頼することも可能です。しかし、将来的に業務範囲を拡大したい場合は、ダブルライセンスによって一人で多様な法律サービスを提供できる強みを持つことができるでしょう。
司法書士の独立開業に必要なスキル
司法書士として独立開業するには、専門知識だけでなく経営や集客のスキルも求められます。
ここでは、どのようなスキルが必要なのか、具体的に解説していきます。
顧客獲得のための営業力
司法書士として独立開業後の収入を安定させるには、優れた営業力が不可欠です。現代では人口減少に伴い案件も減少しており、待っているだけでは仕事は舞い込みません。
積極的な営業活動として、ホームページやSNSを活用したマーケティング、セミナー開催、他士業との連携などが効果的です。特に税理士や弁護士との関係構築は、相互紹介による安定した顧客獲得につながります。
また、顧客との信頼関係を築き、継続的な依頼に繋げることも重要です。一度の仕事で終わらせず、アフターフォローを徹底することで、リピーターや紹介による新規顧客獲得が期待できます。専門分野を確立し、その分野のエキスパートとして認知されることも、高単価案件の獲得に効果的です。
不動産登記・商業登記・相続登記などの実務スキル
司法書士として独立開業するためには、不動産登記・商業登記・相続登記などの基本的な実務スキルを確実に身につけることが不可欠です。
特に不動産登記では、売買や贈与、相続などによる所有権移転登記や抵当権設定登記の手続きを正確に行う能力が求められます。
商業登記においては、会社設立手続きや役員変更、組織変更などの登記申請を適切に処理できるスキルが必要です。
相続登記については、相続人の確定や遺産分割協議書の作成など、相続に関連する法律知識と実務経験が重要となります。
これらの実務スキルを磨くことで専門性が高まり、独立後の収入アップにも直結します。特定分野に特化することで、その分野のエキスパートとして認知され、難しい案件も扱えるようになり、結果として高額報酬につながるでしょう。
会計・経理スキル

司法書士として独立開業する際、会計・経理スキルは事務所経営を安定させる重要な基盤となります。
収支管理や税務申告を適切に行うことで、事務所の財務状況を常に把握し、経営判断の材料とすることができます。特に開業初期は、売上と経費のバランスを正確に把握することが事業継続の鍵となります。
また、クライアントからの預り金管理も司法書士業務では重要です。不動産登記などでは高額な資金を一時的に預かることもあるため、厳格な資金管理が求められます。
さらに、税理士に依頼するとしても、基本的な会計知識があれば無駄な経費を削減でき、節税対策も効果的に行えます。
事務所経営を長期的に安定させるためにも、会計ソフトの活用や基本的な経理知識の習得は欠かせません。
ネットワーキング能力
また、ネットワーキング能力も司法書士として独立開業する際に収益を安定させる重要な要素となります。
不動産会社、金融機関、税理士、弁護士などの専門家とのつながりを構築することで、継続的な案件紹介を受けることができます。特に不動産登記や会社設立の案件は、こうした関連業種からの紹介が多いため、日頃から信頼関係を築くことが大切です。
また、地域の商工会や各種団体への参加、セミナー開催なども効果的なネットワーキング手段となります。これらの活動を通じて自分の専門性をアピールし、「この分野なら〇〇先生」と認識してもらうことで、専門分野からの案件獲得につながります。
オンライン上でのネットワーク構築も忘れてはなりません。SNSやウェブサイトを活用して自分の専門性や実績を発信することで、直接会わない潜在顧客とのつながりも広げられます。
開業後万が一廃業してしまったら転職可能?
司法書士として開業後、何らかの理由で廃業せざるを得なくなった場合でも、転職の道は十分に開かれています。司法書士資格は一度取得すれば一生涯有効であり、廃業後も資格を活かした再就職が可能です。
多くの場合、開業経験があることはむしろ強みとなります。独立経験で培った実務知識や顧客対応スキルは、勤務司法書士として高く評価されることが少なくありません。
また、司法書士事務所だけでなく、不動産会社や金融機関の法務部門、法律事務所のパラリーガルなど、法律知識を活かせる関連業界への転職も選択肢となります。
廃業を検討する際は、司法書士会のサポートを受けながら、自身のキャリアプランを見直してみるとよいでしょう。
司法書士の年収に対してよくある質問
ここでは、司法書士の年収についてのよくある質問に対して答えていきます。
司法書士の年収は正直低いの?
前述した通り、司法書士の年収は勤務形態によって大きく異なります。勤務司法書士の平均年収は約400万円程度で、一般的なサラリーマンと比較してそれほど高くありません。
一方で、独立開業した司法書士の平均年収は約970万円と高く、1,000万円以上稼ぐ司法書士も少なくありません。
つまり、勤務司法書士としてのスタート時は決して高収入とは言えませんが、経験を積んで独立することで収入アップの可能性は十分にあります。また、専門分野に特化したり、認定司法書士の資格を取得したりすることで、勤務司法書士でも年収を上げることは可能です。
年収アップを目指せる転職先は?
年収アップを目指す司法書士には、大都市圏の事務所への転職がおすすめです。東京や大阪などの都市部では平均600万円程度と地方より高い傾向があります。
特に不動産取引が活発な地域や企業法務に強い事務所は高収入が期待できます。また、独立開業も選択肢の一つで、独立司法書士の年収のボリューム層は1000万円〜5000万円と勤務司法書士の平均年収約480万円よりはるかに高くなっています。
さらに、専門分野を持つことも重要です。債務整理や企業法務などの特定分野に特化した事務所は高収入を得やすく、中には年収1,000万円を超える司法書士も少なくありません。自分の強みを活かせる分野の事務所を選ぶことが年収アップへの近道です。
司法書士にボーナスはある?
司法書士のボーナスは勤務形態によって大きく異なります。勤務司法書士の場合、一般的に事務所の規模や業績に応じたボーナスが支給されることが多いです。大手の司法書士法人では年2回のボーナス支給が一般的で、基本給の1〜3ヶ月分程度となっています。
一方、独立開業している司法書士にはボーナスという概念はなく、繁忙期の収入増加が実質的なボーナスの役割を果たしています。特に3月や年度末、相続関連の案件が増える時期には収入が増加する傾向があります。
ボーナスの有無や金額は事務所によって異なるため、就職・転職の際には事前に確認することをおすすめします。また、成果報酬型の給与体系を採用している事務所では、実績に応じて収入が大きく変動することもあります。
司法書士年収まとめ
いかがでしたでしょうか?
司法書士の年収は、勤務か独立かで大きく異なり、経験や業務の幅によっても変動します。
収入を上げるには、業務の幅を広げる、集客力を高めるなどの様々な工夫が必要であることがわかりました。
本記事で紹介したポイントを参考に、自分に合ったキャリアプランを考えてみましょう。
司法書士としての収入を向上させるために、まずは自身のスキルや業務範囲を見直し、具体的なアクションを起こしてみてください。


