税理士の年収の現実は?年齢・性別での比較や高収入を狙う方法を紹介
更新
税理士は高収入な職業として知られていますが、実際の年収は働き方や経験年数によって大きく異なります。
本記事では、年齢や性別による年収の違いを具体的なデータで解説するとともに、より高収入を目指すためのキャリアパスについても詳しく紹介します。
これから税理士を目指す方はもちろん、現役の税理士の方々にとっても、収入アップのヒントとなる情報が満載です。
このページにはプロモーションが含まれています
税理士の平均年収の現実

税理士の平均年収は約780万円とされ、日本の平均年収を大きく上回る高収入な職業です。ただし、働き方や性別、年齢などによって実際の年収には大きな差があり、その現実は一様ではありません。
ここでは、税理士の平均年収の現実を年代や性別、職種などに分類して比較していきます。
出典:令和5年賃金構造基本統計調査 より
税理士の平均年収
厚生労働省が発表した「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、税理士の平均年収は約780万円です。
これは一般的な給与所得者の平均年収458万円と比べると、かなり高水準といえます。
ただし、この数値は企業規模10人以上の事業所に勤める税理士のデータであり、小規模事務所や開業税理士の収入は含まれていません。
過去5年間の推移を見ると、年によって変動があり、2020年には958万円まで上昇した一方で、2021年には658万円まで下落するなど、経済状況や業界動向の影響を受けやすい傾向にあります。
また、企業規模によっても年収に大きな差があり、1,000人以上の大企業に勤める税理士の平均年収は約712万円、10~99人規模では約593万円となっています。
税理士の年代別の年収
税理士の年代別年収は、20代前半で360万円台からスタートし、経験を積むにつれて段階的に上昇していきます。
30代後半から40代にかけて年収は大きく伸び、35~39歳で約800万円、40~44歳で約840万円に達します。
年収のピークは50~54歳で約990万円となり、その後は年齢とともに緩やかに減少する傾向にあります。
ただし、年収は単純に年齢だけでなく経験年数に大きく左右されます。同じ年代でも、経験年数が5~9年の税理士と1~4年の税理士では、数百万円の年収差が生じることもあります。
これは税理士が中途転職組も多い職種であり、資格取得年齢が人によって大きく異なることが影響しています。
つまり、税理士の年収は年功序列というよりも、実務経験とスキルの蓄積が重要な要素となっているのが現実です。
年齢層 | 年収(万円) |
|---|---|
20-24歳 | 360 |
25-29歳 | 400 |
30-34歳 | 600 |
35-39歳 | 800 |
40-44歳 | 840 |
45-49歳 | 900 |
50-54歳 | 990 |
55-59歳 | 950 |
60歳以上 | 900 |
出典:令和5年賃金構造基本統計調査 より
税理士の男女別の年収
男女別の税理士の年収を見ると、男性税理士の平均年収は約890万円、女性税理士は約670万円となっており、約220万円の差が存在します。
この差は、税理士業界における性別による差別が原因ではありません。むしろ、税理士は実力重視の職種であり、能力があれば性別に関係なく昇進できる環境です。
年収差が生まれる主な要因は、女性税理士に時短勤務を選択する方が多いことや、出産・育児によるキャリアの一時中断などが挙げられます。
ただし、税理士は専門性が高く人手不足の職種であるため、ブランク後の復帰がしやすいのが特徴です。
近年では、フレキシブルな働き方を提供する事務所が増加しており、子育てと両立しながら専門性を活かして高収入を得る女性税理士も増えています。
性別 | 平均年収 |
|---|---|
男性 | 890万円 |
女性 | 670万円 |
税理士の生涯年収
税理士の生涯年収は、22歳から59歳までの場合、男性が約3億3,860万円、女性が約2億2,637万円となっています。
これは一般的な生涯年収(男性約2億5,000万円、女性約2億円)と比較して、大幅に高い水準です。
特筆すべきは、税理士には定年退職の概念がなく、60歳以降も生涯現役として働き続けることが可能な点です。
実際、定年後に独立開業するケースも多く、国税庁の調査では全国の税理士約7万3,000人のうち、約8割が独立開業しているというデータがあります。
さらに、日本税理士連合会の調査によれば、独立開業した税理士の6割が年収1,000万円以上を達成しており、生涯現役として働き続けることで、上記の生涯年収をさらに上積みすることも十分可能です。
税理士の平均初任給
税理士の初任給は、資格保有者の場合30〜40万円程度で、年収では500万円前後となります。
これは一般的な大卒初任給の平均22.5万円と比べてかなり高い水準です。ただし、資格を持たずに会計事務所で働く場合は、未経験者で年収250〜350万円程度、経験者でも350〜500万円程度が相場となっています。
特に注目すべきは大手税理士法人(BIG4)の初任給で、年収450〜600万円程度と高水準です。ただし、これはBIG4以外の税理士の平均年収450万円と比べると50〜150万円ほど高い特殊な例と言えます。
なお、独立開業の場合は実力次第で、初年度から1,000万円を稼ぐケースもあれば、収入が安定しないリスクもあります。
税理士の職種別の年収
税理士の職種によって年収は大きく異なります。
日本税理士会連合会の調査によると、職種別の平均年収は以下のようになっています。
社員税理士が886万円と最も高く、次いで開業税理士が744万円、補助税理士が597万円となっています。
企業内税理士の場合は業界によって差があり、金融系が813万円と最も高く、次いで経営企画部799万円、コンサル・アドバイザリー職722万円と続きます。
一方、会計事務所・税理士法人に勤務する場合は570万円と比較的低めですが、都市部では給与水準が高くなる傾向にあります。
職種区分 | 年収 |
|---|---|
社員税理士 | 886万円 |
開業税理士 | 744万円 |
企業内税理士(金融系) | 813万円 |
企業内税理士(経営企画部) | 799万円 |
企業内税理士(コンサル・アドバイザリー) | 722万円 |
補助税理士 | 597万円 |
会計事務所・税理士法人勤務 | 570万円 |
出典:第6回税理士実態調査報告書 より
税理士の年収が低いと言われる理由

税理士の年収が低いと言われる理由は、実態とは異なる印象が広がっているためです。
税理士全体の平均年収は740万円と、一般労働者の平均年収458万円を大きく上回っています。
しかし、年収の実態は二極化しており、1,000万円以上を稼ぐ税理士が開業税理士全体の4分の1を占める一方で、平均年収以下の層も多く存在しています。
また、定年がなく高齢でも働き続けられる職業特性上、短時間勤務の高齢税理士の収入が統計に含まれることで、全体の平均値が低く見える要因となっています。
さらに、近年は30代以下の若手税理士の増加や、異業種からの転職者の参入により、経験の浅い層の割合が増加していることも、平均収入を押し下げる一因となっています。
このように、税理士の年収は実際には決して低くありませんが、様々な要因が重なって「低収入」というイメージが形成されているのです。
税理士が年収アップを目指す方法
税理士の年収アップには、専門性の向上や転職、独立開業など、様々な選択肢があります。
平均年収780万円という高水準からさらなる飛躍を目指すためには、自分に合った戦略を選び、計画的にキャリアを構築していくことが重要です。
以下では、税理士が収入を増やすための具体的な方法と、それぞれのアプローチにおける現実的な可能性について解説していきます。
大手税理士法人で働く
大手税理士法人、特にBig4(PwC、KPMG、デロイト トーマツ、EY)で働くことは、年収アップの有効な手段です。
Big4の平均年収は約810万円で、中小規模の事務所と比べて明確に高い水準となっています。
職階が上がるにつれて年収も上昇し、マネージャーになると年収1,000万円程度、パートナーに昇格すれば1,500万円以上も狙えます。
ただし、Big4での高収入は簡単には得られません。一般スタッフの初任給は450万円~500万円程度からのスタートとなり、年収1,000万円以上を目指すには厳しい出世競争を勝ち抜く必要があります。
幅広い分野での経験を積み、マネージャーやシニアマネージャーとして魅力的な実績を残すことが求められますが、努力次第で大きな年収アップが期待できる環境といえます。
企業税理士になる
企業税理士になることは、安定した年収を確保できる有効な選択肢です。
企業税理士は、一般企業の経理部門や税務部門で税務業務を担当する専門職として働きます。企業規模によって年収は異なりますが、1,000人以上の大企業では平均年収772万円となっています。
企業税理士の魅力は、安定した給与に加えて、賞与が充実している点です。大企業では年間賞与が222万円にも達し、中小企業と比べて約2倍の水準となっています。
また、企業内での専門性を活かしたキャリアアップも期待でき、経理部門のマネージャーや役員として活躍することで、さらなる収入アップも可能です。
企業税理士は、ワークライフバランスを保ちながら、安定した高収入を目指せる選択肢といえるでしょう。
独立・開業する
税理士として独立開業することは、年収アップの有効な手段の一つです。開業税理士の平均年収は約3,300万円で、事業所得は約1,000万円となっています。
独立開業のメリットは、自分の裁量で仕事を進められ、収入も青天井となることです。勤務税理士の年収は約1,000万円で頭打ちとなることが多い一方、開業税理士は自身の努力次第で年収を大きく伸ばすことが可能です。
ただし、税理士法人同士の競争は激化しており、開業後数年間は自身で顧客を獲得する必要があります。
そのため、営業やマーケティングが重要となります。成功のコツは、資産税や国際税務などの特定分野に特化することで、差別化を図ることです。
また、セミナー開催や大学での講義など、本業以外の収入源を確保することで、より高い年収を目指すことができます。
新たな知識を得る
税理士として高収入を得るためには、特定分野における専門性を深めることが重要です。
相続税や不動産税務、法人税務などの特定分野に特化することで、クライアントからの信頼を獲得し、より高い報酬を得られる可能性が広がります。
特に資産税や国際税務は、少子高齢化やグローバル化の影響でニーズが高まっている分野です。
また、M&Aサービスや経営コンサルティング、起業支援など、税理士の独占業務以外のサービスを提供することで、差別化を図ることもできます。
さらに、外国の税制に関する専門知識を持っていることは、グローバル企業での高待遇につながりやすく、事業承継や株価算定、組織再編といった特殊業務の知識も、市場価値を高める重要な要素となります。
税理士の資格を取得するには?
税理士資格を取得するには、税理士試験に合格し、2年以上の実務経験を積むことが必要です。試験は科目合格制で、自分のペースで挑戦できる点が特徴です。
ここでは、税理士資格の取得に関する情報や手順を解説していきます。
税理士試験の概要
税理士試験は、毎年8月に3日間かけて実施される国家試験です。合格には、会計学2科目(簿記論・財務諸表論)と税法3科目の計5科目に合格する必要があります。
試験時間は各科目120分で、記述式の出題形式となっています。合格基準点は各科目とも満点の60%に設定されていますが、実質的な競争試験となっており、平均合格率は15%前後です。
科目合格制を採用しているため、一度に全科目を受験する必要はなく、合格した科目は生涯有効です。
そのため、働きながら2~5年かけて少しずつ合格を目指すことが一般的となっています。
出典:令和6年度(第74回)税理士試験合格者等について より
税理士試験の受験資格
税理士試験を受験するためには、一定の学歴や職歴、資格を満たす必要があります。
ただし、2023年より一部要件が緩和され、会計科目については誰でも受験可能になりました。これにより、幅広い人が挑戦できるようになっています。
出典:税理士試験受験資格の概要 より
学識
税法科目については学識による受験資格が必要です。具体的には以下のいずれかに該当する必要があります。
大学・短大・高専を卒業し、社会科学科目を1科目以上履修していること。または、大学3年次以上で社会科学科目を含む62単位以上を取得していること。
また、一定の専修学校の専門課程(修業年限2年以上かつ総授業時数1,700時間以上)を修了し、社会科学科目を1科目以上履修した場合も受験資格が認められます。
なお、文学部や理工学部など社会科学以外の学部でも、教養科目や共通科目で社会科学に属する科目を1科目以上履修していれば、税法科目の受験資格を得ることができます。
資格
税理士試験の税法科目を受験するための資格要件には、主に以下のようなものがあります。
日商簿記検定1級合格者、または全経簿記検定上級合格者(昭和58年度以降)であれば受験資格が得られます。
また、会計士補の資格を持っている方や、公認会計士試験短答式試験に合格している方(平成18年度以降)も受験資格があります。
受験申請時には、日本商工会議所や全国経理教育協会が発行する合格証明書など、資格を証明する書類の提出が必要となります。
職歴
職歴による受験資格は、特定の業務に通算2年以上従事することで得られます。
具体的には、法人や個人事業主の会計事務、税理士・弁護士・公認会計士等の業務補助、税務官公署での実務、行政機関での会計検査業務、銀行等での貸付関連業務などが該当します。
特に会計事務の場合、単なるデータ入力ではなく、貸借対照表や損益計算書の作成など、複式簿記による経理実務が求められます。
異なる勤務先での経験も合算可能で、合計2年以上の実務経験があれば受験資格として認められます。
受験申込時には、会社の代表者または人事責任者による職歴証明書の提出が必要となります。
弁理士や司法書士などの専門職の場合は、登録証明書と同業者2名以上の証明が必要です。
会計科目は受験資格不要である
2023年度の税理士試験から、会計科目(簿記論・財務諸表論)の受験資格要件が完全に撤廃されました。
これにより、大学や短大の在学・卒業、実務経験、簿記検定などの資格の有無に関係なく、誰でも会計科目を受験できるようになりました。
この改正は、高校生や大学1・2年生など若い世代にも税理士試験へのチャレンジの機会を広げることを目的としています。
以前は日商簿記1級合格などの要件を満たす必要がありましたが、現在は学歴や年齢を問わず、興味のある人なら誰でも挑戦できる制度となっています。
なお、税法科目については従来通り受験資格が必要ですが、こちらも社会科学に属する科目を1科目以上履修していれば良いなど、要件が緩和されています。
税理士試験の勉強方法
税理士試験の勉強方法は、一般的に3〜5年かけて科目ごとの合格を積み上げていきます。
1年目は会計の基礎となる必須科目の「簿記論」と「財務諸表論」から始めるのが定石です。この2科目は関連性が高く、同時に学習することで効率的に進められます。
2年目以降は、法人税法や所得税法などの税法科目に取り組みます。これらの科目は実務での価値が高いため、早めの取得がおすすめです。
学習時間は科目によって異なり、法人税法・所得税法は600時間、簿記論・財務諸表論は450時間が目安となります。
仕事と両立する場合は、週14〜17時間(年間600〜750時間)の学習時間を確保することが推奨されます。
基礎固めから応用、直前期まで計画的に進め、過去問演習を繰り返すことで実践力を養います。

税理士試験合格のためには、通信講座や予備校などでプロ講師の指導を受けながら体系的に知識を習得するのがおすすめです!
税理士の仕事内容
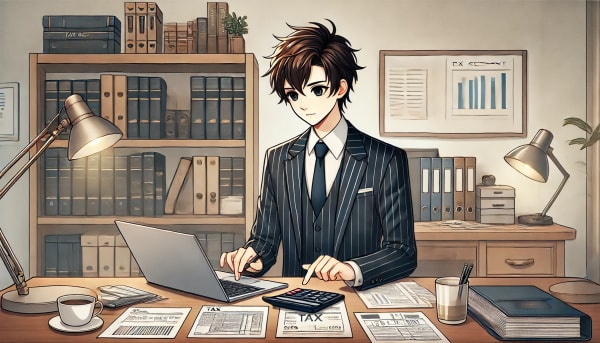
税理士の主な仕事は、税務に関する3つの独占業務である「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行うことです。
税務代理では、確定申告や青色申告の承認申請、税務調査の立ち会いなどを納税者の代わりに行います。
税務書類の作成では、確定申告書や年次決算書、各種申請書などの作成を担当します。
また、税務相談では、税金の計算方法や節税対策などについて専門的な助言を提供します。
近年は独占業務以外にも、記帳代行や会計業務、経営コンサルティングなど、業務の幅が広がっています。
特に中小企業に対しては、単なる税務の外注先としてだけでなく、経営全般に関する相談相手として、企業の業績向上に貢献する役割も期待されています。
税理士の年収に関する質問
税理士の年収の実態が気になる方も多いでしょう。
以下では、稼げる税理士の特徴や収入と学歴の関係などを紹介していきます。
稼げる税理士と稼げない税理士の違いは?
稼げる税理士と稼げない税理士の違いは、主に「提供するサービスの質」と「経営スキル」にあります。
稼げる税理士は、単なる税務申告だけでなく、クライアントの経営課題を解決する付加価値の高いサービスを提供しています。
例えば、経営コンサルティングや資金調達支援、M&Aアドバイスなど、専門性が求められる分野に特化することで他との差別化を図っています。
一方で、稼げない税理士は、単純な会計処理や申告業務に依存しがちです。これらの業務はクラウド会計ソフトやAIの普及によって代替されつつあり、価格競争に巻き込まれるリスクが高まっています。
さらに、稼げる税理士は顧客との信頼関係を築くためのコミュニケーション能力や営業力も重要視しています。
また、ITスキルや語学力を活かして、新たな市場や顧客層を開拓することにも積極的です。
このように、時代の変化に対応しながら、自身のスキルと提供価値を高め続けることが、稼げる税理士になるための鍵となります。
税理士の年収に学歴は関係ある?
税理士の年収は、学歴とは基本的に関係がありません。実力や実績、経験値が重視される業界であり、高卒でも中卒でも、優れた実務能力があれば高収入を得ることが可能です。
実際に、税務に関する深い知識と顧客対応力を持つ税理士は、学歴に関係なく高い評価を受けています。
特に、新規顧問先の開拓能力や効果的な節税対策の提案ができる人材は、学歴よりもその実践的なスキルで評価されます。
ただし、就職時の選択肢については、一部の税理士法人や事務所で大卒以上を求める場合もあるため、その点では多少の影響が出る可能性があります。
しかし、いったん実務経験を積み始めれば、年収は完全に実力主義となり、学歴による差はなくなっていきます。
税理士年収まとめ
税理士の平均年収は約740万円で、年齢や性別、勤務形態によって大きく変動します。
20代は300-500万円台からスタートし、経験を積むことで徐々に上昇。男性は50代後半で1,000万円を超えるケースもありますが、女性は平均して150万円ほど低い傾向にあります。
高収入を目指すなら、専門性を磨いて差別化を図るか、Big4などの大手税理士法人への転職、独立開業が有効な選択肢となります。
まずは自身のキャリアプランを見直し、目標に向けた一歩を踏み出してみましょう。



