【最新】国家資格難易度ランキング!簡単にとれる資格や難しい士業の資格を格付け
更新
国家資格の取得を目指しているけれど、自分の実力に合った資格が分からない。そんな悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
本記事では、合格率や勉強時間から各国家資格の難易度を徹底的に分析し、最新のランキングとしてまとめました。
医療・法律・IT・不動産など、幅広い分野の資格を網羅的に解説しているので、あなたに合った資格選びのヒントが必ず見つかるはずです。まずは簡単な資格から始めて、ステップアップを目指すのがおすすめです。
このページにはプロモーションが含まれています
国家資格難易度ランキングTOP15位
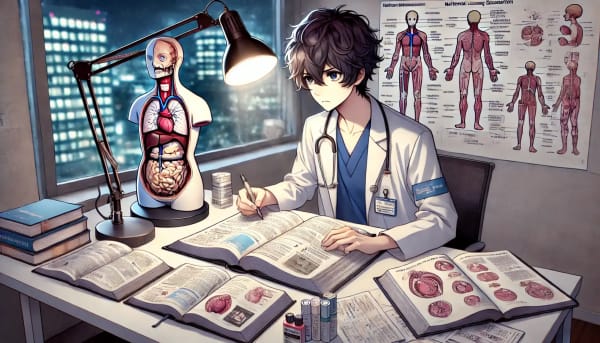
ここでは、国家資格難易度ランキングTOP15位をご紹介します。
Sランク(偏差値75以上)
1位:司法試験
偏差値75程度とされる司法試験は、法科大学院を卒業するか予備試験に合格しないと受験資格が得られません。非常に難しい資格であると言えるでしょう。
2024年の合格率は42.1%で、受験者3,779人のうち1,592人が合格しました。ただしこの数字は、法科大学院卒業や予備試験合格という高いハードルをクリアした人たちの中での合格率です。
なお、2024年の予備試験の合格率はわずか3.6%(受験者12,469人、合格者449人)でした。受験資格を得るだけでも本当に大変であることがよくわかります。
試験は短答式と論文式の2段階で実施され、憲法・民法・刑法・商法・行政法など広範な法律知識と論理的思考力が問われます。特に論文試験は超長文で高度な問題が出題され、最大の難関となっています。
出典:法務省 司法試験予備試験の結果について
2位:公認会計士試験
公認会計士試験は医師・弁護士と並ぶ三大国家資格の一つで、2024年の合格率は7.4%と極めて低い水準となっています。非常に難しい資格であると言えるでしょう。
試験は短答式と論文式の2段階方式で実施され、短答式試験に合格しなければ論文式試験を受験できません。合格までに必要な勉強時間は2,500~3,500時間とされており、試験科目も財務会計論、管理会計論、監査論、企業法など多岐にわたります。
受験資格の制限がないため誰でもチャレンジできる一方で、専門的な知識と高度な理解力が求められ、合格までには相当な努力と時間が必要です。
出典:公認会計士・監査審査会 過去の試験結果等
3位:医師国家試験
医師国家試験は、医師免許を取得するための最後の関門となる国家試験です。
合格率は例年90%以上と高く見えますが、この数字は医学部6年間の厳しい教育課程を乗り越えた者だけが受験できる試験であることを考慮する必要があります。
試験は2日間で全400問が出題され、必修問題・一般問題・臨床問題の3種類から構成されています。特に必修問題では80%以上の正答率が求められ、さらに「禁忌肢」という患者の死につながる選択をすると即不合格となる厳格な基準が設けられています。
医学部入学から医師免許取得までの道のりを考えると、難しい資格であると言えるでしょう。
出典:厚生労働省 国家試験合格発表
4位:弁理士試験
弁理士試験は、知的財産権に関する法律の専門家を目指す超難関国家資格です。令和6年度の最終合格率はわずか6.0%で、3,502人の志願者のうち191人しか合格できませんでした。
合格までに必要な勉強時間は約3,000時間とされており、1日4時間の学習でも2年以上かかる計算になります。
試験は短答式、論文式、口述式の3段階に分かれており、全ての試験に合格する必要があります。特に短答式試験の合格率は10〜20%と厳しく、合格までの平均受験回数は2.4回を要します。
理系資格の最高峰とも呼ばれ、特許・実用新案法、意匠法、商標法など幅広い知識が求められる、まさにSランクに相応しい非常に難しい資格であると言えるでしょう。
出典:特許庁 令和6年度弁理士試験の結果について

弁理士試験を目指すなら資格スクエアの講座がおすすめです!
Aランク(偏差値70以上)
5位:不動産鑑定士試験
不動産鑑定士試験は、法律・経済・会計など幅広い知識が要求される超難関国家資格です。試験は短答式と論文式の2段階方式で実施され、短答式試験合格者のみが論文式試験を受験できます。
偏差値は74と評価され、京都大学や東京大学レベルの難易度とされています。必要な学習時間は2,000時間以上と言われ、司法試験や公認会計士試験に並ぶ最難関資格の一つです。
独学での合格は非常に困難で、法改正への対応や演習問題の確保など、予備校などの専門的なサポートを活用することが推奨されています。
出典:国土交通省 令和6年不動産鑑定士試験の合格者が決定しました
6位:司法書士試験
司法書士試験は、合格率が4〜5%台と極めて低く、国家資格の中でもトップクラスの難易度を誇ります。
必要な勉強時間は3,000時間以上が目安とされており、1年で合格を目指す場合、1日8時間以上の学習が必要となります。
試験科目は11科目と多岐にわたり、民法や商法、不動産登記法など幅広い法律知識が求められます。
特に近年は、相対評価による厳しい合格基準や、各科目での足切りラインの存在により、合格難度は一層高まっています。
合格者の平均年齢は41歳前後で、30〜40代が全体の3分の2を占めており、社会人経験を経てからチャレンジする人が多いのが特徴です。
出典:法務省 令和6年度司法書士試験の最終結果について
7位:税理士試験
税理士試験は、11科目のうち5科目に合格する必要がある難関国家資格です。
合格率は科目によって異なりますが、平均18~20%程度で推移しており、5科目合格までには平均4,000時間もの勉強時間を要します。
最も大きな特徴は、科目ごとの難易度差が大きいことです。2025年2月の最新データでは、財務諸表論の合格率が8%まで低下する一方、相続税法は18.7%と大きく上昇しています。
5科目合格までに要する期間は最短でも2年、一般的には3~5年かかるため、長期戦を覚悟する必要があります。税理士は、会計・税務のスペシャリストとして高い専門性が求められる資格といえます。
出典:国税庁 令和6年度(第74回)税理士試験結果表(試験地別)
8位:一級建築士試験
一級建築士試験は、建築界の最高峰の国家資格として知られ、2024年の総合合格率は8.8%と極めて厳しい難関試験です。
試験は学科試験と設計製図試験の2段階方式で実施され、学科試験では計画、環境・設備、法規、構造、施工の5科目について出題されます。
学科試験の合格率は約19%、設計製図試験の合格率は約35%と、どちらも高いハードルとなっています。特に設計製図試験では、毎年課題が変わり、美術館や高齢者介護施設など、幅広い建築物の設計能力が問われます。
受験資格には実務経験が必要で、合格までに数年を要するケースも多く、建築のプロフェッショナルとしての総合的な実力が試される試験といえます。
出典:国土交通省 令和6年一級建築士試験「設計製図の試験」の合格者を決定
Bランク(偏差値65以上)
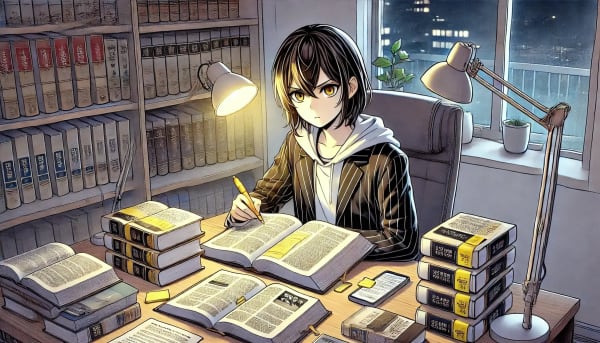
9位:社会保険労務士(社労士)試験
社会保険労務士試験は、合格率が約6~7%と非常に低く、難関国家資格の一つとして知られています。
令和6年度の試験では、受験者数43,174人に対して合格者数は2,974人、合格率は6.9%でした。
合格に必要な勉強時間は約800~1,000時間とされ、平日2時間、休日5時間程度の学習が必要です。
試験は選択式と択一式の2部構成で、各科目に最低点が設定されており、全科目で基準点を超える必要があることも難易度を高める要因となっています。
宅建や行政書士よりも難しく、司法書士や司法試験よりは易しいとされる中堅の難関資格です。
出典:厚生労働省 第56回社会保険労務士試験の合格者発表
10位:中小企業診断士試験
中小企業診断士試験は、1次試験の合格率が27.5%、2次試験の合格率が18.7%で、最終合格率は約5.1%という極めて難関な国家資格です。
大学入試の難易度に換算すると偏差値62程度で、明治大学や青山学院大学、中央大学などと同レベルとされています。
1次試験では7科目の筆記試験があり、2次試験では4科目の論述式と口述試験が課されます。特に2次試験の財務・会計分野は難易度が高く、多くの受験生が苦戦を強いられています。
社会保険労務士や行政書士と同程度の難易度とされており、仕事と両立しながらの合格には平均1,000時間程度の学習時間が必要とされています。
出典:中小企業診断協会 過去の試験結果・統計資料
11位:気象予報士試験
気象予報士試験は、毎年の合格率が4~6%と非常に狭き門である国家資格です。試験は学科試験と実技試験に分かれており、特に実技試験の難易度が高いことが合格率の低さの要因となっています。
合格に必要な学習時間は平均800~1,500時間とされ、多くの受験者が3~5回の受験を経て合格に至ります。令和6年8月の試験では合格率5.8%を記録し、学科試験は15点中10点以上、実技試験は総得点の66%以上が合格基準となっています。
気象予報士は、気象キャスターなど活躍の場が限られているものの、専門性の高さから資格としての価値は高く評価されています。
出典:気象業務支援センター 試験結果・報道参考資料
Cランク(偏差値60以上)
12位:通関士試験
通関士試験は、輸出入の税関手続きを代行する専門家になるための国家資格です。合格率は例年10〜20%で推移しており、令和5年度は24.2%でした。
合格には平均して400〜500時間の学習時間が必要とされ、独学の場合はさらに1.5倍の約750時間が目安となります。試験科目は「通関業法」「関税法等」「通関実務」の3科目で、すべての科目で60%以上の得点が求められます。
貿易に関する専門的な法律知識が必要で、普段馴染みのない分野のため、体系的な学習が重要です。ただし、計画的な学習と十分な過去問演習で、独学でも十分合格可能な資格といえます。
13位:土地家屋調査士試験
土地家屋調査士試験の偏差値は64で、社労士と同等の難関資格として知られています。
合格率は例年9〜10%前後で推移しており、2023年度の試験では4,429人中428人が合格し、合格率は9.66%でした。
合格には1,000〜1,500時間の学習時間が必要とされ、特徴的なのは法律知識だけでなく、三角関数や複素数などの数学的知識も必要な点です。
試験は毎年10月に筆記試験、翌年1月に口述試験が実施され、筆記試験では計算問題や作図の正確性とスピードも重視されます。
出典:法務省 令和6年度土地家屋調査士試験筆記試験の結果等について
14位:電気主任技術者(電験一種)試験
電気主任技術者の最高峰である電験一種は、一次試験と二次試験の両方に合格する必要があり、一発合格率はわずか4.5%という超難関資格です。
とはいえ、一次試験の合格率は約30%、二次試験の合格率は約15%で推移しており、年度によって難易度の変動が大きいのが特徴です。上位の資格と比較すると、簡単にとれる資格と言えるでしょう。
電力会社の社員が受験者の約6割を占めており、独学での合格は相当な努力が必要です。参考書も少なく、一般的な受験者は約5,000時間もの学習時間を要すると言われています。
電気工学の最高峰資格であり、「電気の司法試験」とも呼ばれるほどの難関国家資格です。
出典:電気技術者試験センター 令和6年度度第一種及び第二種電気主任技術者試験一次試験の結果について
15位:海事代理士試験
海事代理士は「海の司法書士」と呼ばれる八士業の一つで、船舶関連の法務手続きを担う専門資格です。
筆記試験の合格率は約52%、口述試験の合格率は約95%となっており、合格までの勉強時間は約500時間(筆記試験350時間、口述試験150時間)が目安です。
受験者の多くは司法書士や行政書士などの有資格者で、法律の基礎知識がある人が多いため合格率が高めとなっていますが、一般の方が受験する場合は約600時間の学習時間が必要とされます。
出典:日本海事代理士会関東支部 令和5年海事代理士試験合格者が発表されました
独学 vs 予備校・通信講座 どっちがおすすめ?
ここでは、独学と予備校の必要性についてご紹介します。
Sランク(超難関・最難関)は士業専門の予備校マスト
Sランクの超難関資格は、司法試験・予備試験、公認会計士、弁理士、税理士、司法書士など有名士業になるための資格が該当します。これらの資格は合格率が一桁台と極めて低く、3,000時間以上の膨大な学習時間を要するため、試験を乗り越えるのが非常に難しいです。
独学での合格は非常に困難で、ほとんどの合格者が予備校を利用しています。その理由として、試験科目が多岐にわたり、かつ同時合格が求められることが挙げられます。
また、予備校では合格実績のある講師陣による体系的なカリキュラムと、答案作成の実践的なトレーニングを受けることができます。さらに、モチベーション維持のための環境や仲間との切磋琢磨も、長期戦となる試験対策には重要な要素となります。
そのため、Sランクの資格取得を目指す場合は、TAC、大原、伊藤塾などの実績ある予備校の利用をおすすめします。
Aランク(難関)は予備校・通信講座利用者が有利
難関資格の合格率を比較すると、予備校利用者の方が明らかに高い傾向にあります。例えば宅建試験では、独学受験者の合格率が約10%なのに対し、予備校利用者は66%以上と大きな差が出ています。
これは難関資格特有の広範な学習範囲と複雑な知識体系が要因です。予備校では、経験豊富な講師による体系的なカリキュラムと、効率的な学習方法の指導を受けられます。
また、予備校では勉強仲間との情報共有や切磋琢磨が可能で、モチベーション維持にも効果的です。さらに、一定の勉強時間が強制的に確保されるため、仕事や学業との両立においても計画的な学習が可能となります。
特にAランクの難関資格では、独学での学習の穴を埋めるために余計な時間がかかることも。確実な合格を目指すなら、予備校の利用をおすすめします。
Bランク(中堅難関)は予備校・通信講座の部分利用がおすすめ
Bランク(中堅難関)の資格は、宅建や社会福祉士などが代表的で、300〜500時間程度の学習時間が必要とされます。
このレベルの資格は独学でも合格は可能ですが、競争率が高く油断はできません。特に法律系の科目がある資格では、基本的な法律の解釈や体系的な理解が重要になってきます。
そこでおすすめなのが、予備校の部分的な活用です。具体的には、予備校の基礎講座で体系的な知識を習得し、その後は独学で演習を重ねるという方法が効率的です。この方法なら、予備校の費用を抑えながらも、独学では理解が難しい分野をカバーできます。
また、模試や答練だけを利用するのも有効な選択肢です。自分の弱点を把握し、的確な対策を立てることができるからです。
Cランク(準難関)は独学で十分
Cランク(準難関)の資格は、基本的に独学でも十分に合格を狙える範囲です。先程紹介したもの以外にも、宅建士や簿記2級、FP2級などもこのランクに該当します。
このような、比較的簡単にとれる資格は、市販のテキストや過去問を活用することで、効率的な学習が可能です。勉強時間も100〜300時間程度で、計画的に取り組めば社会人でも半年から1年程度で合格できる水準となっています。
ただし、独学で成功するためには、自分で学習計画を立て、教材を選び、進捗管理をする必要があります。そのため、自己管理能力に自信がない場合や、基礎から体系的に学びたい場合は、予備校の利用も検討する価値があるでしょう。
独学のメリットは費用を抑えられることですが、予備校のような強制的な学習環境がないため、モチベーション維持が重要なポイントとなります。
【格付け】将来性がある資格一覧

ここでは、将来性があると言われている資格をランキング形式でご紹介します。
1位:医師(医師国家試験)
医師国家試験の合格率は90%以上と高いものの、受験資格を得るまでのハードルが極めて高く、医学部医学科の偏差値は全国平均で70以上が必要です。
難しい資格ですが、医師免許は一度取得すれば生涯有効で更新の必要がなく、高い年収と安定した身分が保証されます。厚生労働省の調査によると、医療法人の医師の平均年収は約1,200万円前後で推移しています。
日本では高齢化により医療需要が増加するため、今後さらに医師の需要は高まると予測されています。また医療はAIが進歩しても人の判断が必要な分野であり、医師という職業の重要性は今後も変わらないと考えられます。さらに、医師は海外でも需要が高く、グローバルに活躍できる可能性があります。
2位:公認会計士
公認会計士は、弁護士、医師と並ぶ三大国家資格の一つで、合格率約10%の難関資格です。
現在、監査業務の厳格化による会計士不足が続いており、売り手市場となっています。さらに、M&Aを含めた企業の海外進出の増加や、ESG関連の監査需要の拡大により、活躍の場が広がっています。
AIの進化により定型業務は自動化されますが、それにより公認会計士は経営戦略の策定やリスク管理、コンサルティングなど、より高度な判断を要する業務にシフトできます。
年収面でも、転職時のオファーが1000万円を超えることも珍しくなく、M&Aブティックでは2000万円以上の提示も可能性があるなど、将来性は非常に高いと言えます。
3位:弁護士(司法試験)
司法試験は近年合格率が40%以上と上昇傾向にあり、以前と比べて挑戦しやすい環境が整っています。
弁護士の将来性が高い理由の一つは、企業法務やインハウスローヤーの需要が拡大しており、従来の法律事務所以外での活躍の場が広がっているからです。
また、弁護士の仕事は景気に左右されにくく、好景気時は企業の契約業務、不景気時は倒産処理など、経済状況に関係なく一定の需要があります。
さらには、コンプライアンス意識の高まりや、グローバル化に伴う法務ニーズの増加により、企業における法務人材としての価値が高まっています。
4位:弁理士
弁理士は、合格率6%と難関資格の一つですが、将来性の高い資格として注目されています。
グローバル化に伴い日本企業の海外出願が増加傾向にあり、国際的な知財業務の需要が高まっていることがその理由の一つです。
また、弁理士の年齢構成を見ると50歳以上が全体の56%を占めており、今後10年で最大1,400人の減少が予測されているため、若手弁理士の需要が高まると考えられます。
さらに、AIの発達により業務効率化は進むものの、発明の本質を理解し依頼者とコミュニケーションを取りながら権利化を進める業務は、AIで代替することが難しいとされています。
これらの要因から、弁理士は将来的にも安定した需要が見込める資格と言えるでしょう。
5位:中小企業診断士
中小企業診断士は、経営コンサルタントとして唯一の国家資格であり、高い将来性を持つ資格として注目されています。
その理由として、AIによる代替可能性が極めて低いことが挙げられます。経営コンサルティングには数字に表れない要素の分析や、高度なコミュニケーション能力が不可欠だからです。
さらに、コンサルティング需要は今後も伸びると予想されており、中小企業診断協会の調査では62%以上の診断士が需要増加を見込んでいます。
特に事業再生や新分野進出、戦略的支援の要請が高まっており、グローバル化に伴う経営アドバイスの需要も拡大しています。
また、経営の専門家として高い専門性を持つため、新規参入者に仕事を奪われにくい特徴があります。
出典:中小企業診断協会 過去の試験結果・統計資料
将来性が見込めない資格一覧
ここでは、将来性が見込めないと言われている資格をランキング形式でご紹介します。
1位:司法書士
司法書士は、合格率が約5%と極めて低く、3,000時間以上の勉強時間を要する難関資格です。
しかし、AIの進化により定型的な書類作成業務の代替が進み、登記件数も年々減少傾向にあることから、従来の業務範囲が縮小する可能性が高まっています。
また、司法書士の主要業務である不動産登記は、人口減少に伴い取引件数が減少しており、収入の安定性に不安があります。さらに、デジタル化の進展により、オンライン申請の普及や自動化が進むことで、従来の業務の一部が不要となる可能性も指摘されています。
このように、長期的な視点で見ると、司法書士の伝統的な業務領域は徐々に縮小していく傾向にあります。
2位:社会保険労務士(社労士)
社会保険労務士は、合格率が約6%と難関資格の一つですが、将来性に懸念があります。
最大の理由は、AIや人事労務管理ソフトの普及により、従来の独占業務である申請書類作成や手続き代行の需要が減少していく可能性が高いことです。また、企業のDX化に伴い、社会保険や労務手続きの自動化が進んでおり、特に中小企業での導入が加速しています。
さらに、労働関連法規や社会保険制度は頻繁に改正されるため、常に最新知識のアップデートが必要で、専門家としての付加価値を維持するのが困難になってきています。
このような状況から、資格取得に必要な1,000時間以上の学習時間に対して、将来的な投資対効果が見込みにくい資格といえます。
3位:通関士
通関士は、貿易業務に関する専門資格として知られていますが、実際には将来性に懸念があります。
主な理由は、通関手続きの電子化・自動化の急速な進展により、従来の業務の多くがAIやシステムに置き換わる可能性が高まっているためです。また、通関業務の簡素化や規制緩和により、通関士の独占業務が縮小傾向にあることも懸念材料です。
さらに、個人での独立開業が限りなく困難であり、キャリアの選択肢が限られているのも大きな課題です。
加えて、通関士試験の合格率は10~20%と難関でありながら、資格取得後の年収や待遇が他の国家資格と比較して必ずしも高くないことも、将来性を疑問視する要因となっています。
4位:不動産鑑定士
不動産鑑定士は、市場規模の縮小と受験者数の減少が続いており、将来性に懸念が生じています。不動産取引市場自体が縮小傾向にあり、従来型の鑑定業務は減少しています。
さらに、AIやデジタル技術の進化により、基本的な不動産評価の自動化が進むことが予想され、従来の業務形態では生き残りが困難になる可能性があります。
実際に、毎年新たに誕生する不動産鑑定士は100人を下回る状況が続いており、若手の参入も限られています。
このような状況から、高難度の試験に合格するための労力に見合う将来性が見込めないと判断する若者も増加しています。
ただし、相続関連の需要増加や都市再開発など新たな分野での活躍の可能性も残されているため、コンサルティング能力を磨くなど、従来の業務形態からの転換が求められています。
5位:気象予報士
気象予報士は合格率4〜6%と難関資格でありながら、資格取得者の約7割が気象とは無関係の業務に就いているのが現状です。
気象予報士として活躍できる職場は限られており、テレビ局や気象会社などの求人は極めて少ないのが実態です。
また、近年のAI技術の進歩により、気象予報の自動化が進んでおり、従来の予報業務の一部が代替される可能性も指摘されています。
ただし、地方自治体での防災対策や企業の気象データ分析など、新たな活躍の場も徐々に広がりつつあります。しかし、現時点では気象予報士の需要が現実の求人数に追いつくまでにはまだ時間がかかると予想されています。
国家資格の難易度まとめ
本記事では、国家資格を難易度別に分類し、超難関の司法試験から比較的取得しやすいITパスポートまで、詳しくランキング形式で解説しました。
勉強時間や合格率に基づいて各資格の難易度を客観的に評価し、あなたに合った資格選びのヒントを提供しています。
まずは自分のスキルや目的に合わせて、チャレンジしやすい資格から始めてみましょう。資格取得への第一歩を踏み出すために、ぜひ当記事を参考にしてください。

