弁護士の就職先は?司法試験合格後の進路や法律事務所の就活のポイントも解説
更新
弁護士を目指す人にとって、司法試験に合格することは夢の第一関門です。
しかし、合格後の進路選択は決して簡単ではありません。
この記事では、弁護士の主な就職先や、法曹界での多様なキャリアパス、さらには法律事務所への就職活動のポイントをわかりやすく解説します。
人気講座ランキング

 もっと見る>
もっと見る>- 特出した実績を持つ最注目のオンライン講座!


- 業界最高の合格者占有率を記録する王道予備校

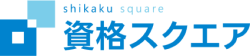 もっと見る>
もっと見る>- リーズナブルかつ高品質なコスパ抜群の講座
このページにはプロモーションが含まれています
弁護士の就職先・活躍の場は?
まずは、司法試験に合格したのちに弁護士として働く人の就職先として一般的なものをみていきます。

法律事務所
司法試験に合格した人の多くは、弁護士のキャリアを始める場所として法律事務所を選びます。司法試験受験生の大半は、法律事務所で働くことを前提に、合格を目指して努力しているでしょう。
法律事務所には、規模や専門分野によってさまざまな種類がありますが、どの事務所を選ぶか、どのような経験を積むのかは長期的なキャリアプランに大きく影響します。
五大法律事務所や大手法律事務所のほか、企業法務系の事務所など、選択肢は多岐にわたります。大手と中小の事務所では得られる経験や求められるスキルが異なるため、自分の特徴や将来の方向性を考慮して、自分にあった事務所を選び取ることが重要になります。
法律事務所での業務内容
弁護士の役割は多岐にわたり、刑事事件では被疑者・被告人の弁護、民事分野では、離婚など家庭内の法的問題を公正に解決します。
また、企業法務では、経営活動の法的な健全性を確認し、リスクから組織を守ります。
法律事務所によって得意分野は異なりますが、弁護士は全般的には法的問題の予防と解決を担うと言えます。
法律事務所での年収は?
法律事務所に勤務する弁護士の平均年収は約1,100万円ですが、経験年数や勤務する法律事務所の規模によって大きく変わります。新人弁護士の初年度の平均年収は550万円前後ですが、年数を重ね経験を積むごとに、年収も上がっていきます。
一方、五大法律事務所のような大手の法律事務所に勤めれば、新人でも1,000万円を超える高額年収が一般的です。
事務所の規模が大きければ大きいほど、収入は高くなりますが、それだけ競争も激しいと言えるでしょう。
法律事務所での仕事に向いている人は?
法律事務所で成功を収めるためには、どの立場の弁護士であっても営業力が不可欠です。
経験年数や役職に関わらず、顧客を確保し続けることがキャリアを築く上では大変重要です。
したがって積極的な営業活動を通じて顧客を掴み取り、年収アップや自らのキャリアを切り開きたい人には、法律事務所は最適な職場といえます。
一般企業(企業内弁護士・インハウスローヤー)
司法試験合格者の中には、一般企業に企業内弁護士(インハウスローヤー)として就職することを選ぶ人も少なくありません。
企業内弁護士は、所属企業の法的問題を解決する重要な役割を担いますが、案件の多寡に左右されにくい安定した収入とワークライフバランスが維持できることが魅力的です。
企業内弁護士の業務内容
企業内弁護士は、企業活動における法的リスクを適切に管理し、健全な事業運営を支える重要な役割を担っており、取引契約や知的財産権の管理から危機管理まで幅広い業務に携わります。
また、コンプライアンスの重視、グローバル化の進展によるM&Aや組織再編の増加といった現代のビジネス環境の変化に対応するため企業内弁護士の採用が増加傾向にあります。
企業内弁護士の年収は?
企業内弁護士の初任給は、概ね年収500万円前後ですが、経験を積むにつれて年収は増えていき、800万円以上を期待することもできます。ただし、法律事務所とは異なり、受け持つ案件数によって収入が増加するわけではありません。
一般企業のため、長く勤務すれば年収は徐々に上がる傾向にあり、役職に就けば1,000万円を超えることもあります。
そのため、企業内弁護士を目指す場合は、長期的な視野から年収やキャリアパスを検討してみまそう。
企業内弁護士に向いている人とは?
企業内弁護士は、仕事と生活の両立(ワークライフバランス)を重視する人におすすめの働き方です。多くの一般企業では働き方改革が進み、法律事務所と比べて残業が少なく、福利厚生なども含めた手厚い待遇が用意されているため、魅力的な環境が整っています。
ただし、企業には給与水準が存在し、それを大幅に超えるような高収入を目指すのは難しいでしょう。
したがって企業内弁護士は、安定した待遇のもとで仕事と私生活を両立しながら自分の法律知識を発揮したい方におすすめの職業だと言えます。
公務員(自治体内弁護士)
弁護士としてのキャリアを歩む方の中には、自治体の法務分野で専門的な知識とスキルを活かし、公務員(自治体内弁護士)として勤務している方もいます。
彼らは非常勤職員や任期付き職員、任期付短時間勤務職員など様々な形態で採用され、都道府県庁や市役所に在籍しています。
公務員としての弁護士の任期は最大5年間ですが、多くの場合は2年から3年程度で採用され、その後延長されます。
自治体内弁護士の業務内容
自治体内弁護士は、各自治体の法務部をはじめ教育委員会や労働委員会、児童相談所や障害者センターといった様々な部署に配属され、条例や規則の策定、住民からの法律相談対応など、幅広い業務を担っています。
公平で公正な自治体運営のためのルール作りに携わるほか、住民の様々な問題や不安の解決を通じて、地域社会の安定と発展に貢献しています。
基本的に公務員の兼任は禁止されていますが、自治体の許可を得ることで弁護士と公務員を兼任することができます。
自治体内弁護士の年収は?
自治体内弁護士の平均年収は概ね800万円程度です。一方、民間企業や法律事務所に所属する弁護士の年収は約1,000万円となっているため、自治体内弁護士の方が若干低めになっています。
しかし、自治体内弁護士は公務員と弁護士としての仕事を兼任できる場合があり、働き方次第で更なる高収入を得ることも可能であると言えます。
自治体内弁護士に向いている人とは
自治体内弁護士は、住民の声に直接触れ、その要望を行政に反映させる重要な役割を担っています。
住民の生活向上のために行政と住民の橋渡しをし、双方が納得のいく解決策を見出すことが求められます。
このように地域に密着したサービスを提供し、職員や住民から直接感謝されるなど、影響力や貢献度を実感しやすい仕事であるため、やりがいのある仕事を探している人におすすめの職業だと言えます。
法テラス
「法テラス」は、国が設立した法的支援機関です。
経済的な理由で弁護士費用を負担することが困難な人々に対して、法律相談や支援を行っています。また、法テラスでは就職が困難な弁護士を常勤で採用し、国選弁護事件や出張法律相談などの機会を提供しています。
他にも、法テラスが弁護士が不足している地域に開設した「4号事務所」は、弁護士が活躍する新たな場所となり、法的問題を抱える人々からの相談を受け付け、支援を行っています。
法テラスでは専属のスタッフ弁護士を採用しています。ただし、新卒採用される弁護士は、法テラスに入る前に一般の法律事務所で実務研修を受けることが求められます。
ひまわり公設事務所
弁護士が大都市に集中し、地方では不足しているという問題に対処するため、日本弁護士連合会や地元の弁護士会が「ひまわり公設事務所」の設立に踏み切りました。
この事務所では、弁護士が不足している地域に新たに採用された弁護士が一定期間勤務して公設事務所を設立し、独立開業と同等の条件で業務を行います。
こうした取り組みは、弁護士過疎地域の課題解決だけでなく、新人弁護士の就職先確保にもつながります。ひまわり公設事務所の存在は、全国どこでも弁護士が活動できる環境づくりへの第一歩と言えます。
人気講座ランキング

 もっと見る>
もっと見る>- 特出した実績を持つ最注目のオンライン講座!


- 業界最高の合格者占有率を記録する王道予備校

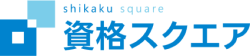 もっと見る>
もっと見る>- リーズナブルかつ高品質なコスパ抜群の講座
司法試験・司法修習の合格後の弁護士以外の進路は?
多くの司法修習生は法律事務所でキャリアを始めますが、中には別の進路との間で悩む方もいるでしょう。司法修習生が持つ法律の知識は弁護士以外にも幅広い職種において活用することができます。
また、弁護士として活躍されている方の中にも転職を考えている方はいらっしゃるでしょう。
ここでは弁護士だからこそ転職しやすい職業なども併せて紹介していきます。
裁判官
法曹三者のうちの一つである裁判官がまず考えられます。
裁判官は各地の裁判所で多様な訴訟案件を審理し、判決を下すという困難な仕事に携わります。約3年ごとの転勤を経験しながら、さまざまな地域で知見を深めていきます。
裁判官のポストには、司法修習期間中に良い成績を収めた人材が求められることが多いようです。そのため、裁判官の道を考えている人は司法修習を頑張ることが重要だと言えます。
裁判官の業務内容
裁判官は、公訴や訴訟、申立てなどの事件を公正に裁き、判決を下す重要な役割を担っています。被告人の人生を左右するため、慎重な準備と熟考が欠かせません。
まず、訴訟の経緯や当事者の主張、証拠の内容などを詳細に検討します。次に、裁判において、当事者や代理人、検察官、証人からの意見を丁寧に聴取し、互いの主張と証拠を慎重に精査します。そして最終的に、法律に基づいて適切な判断を下して判決を言い渡すのです。
刑事裁判や民事裁判など、裁判の種類は様々ですが、いずれも公正な判断が求められる重責です。裁判官には高い倫理観と確かな法的知識が必要不可欠であると言えます。
裁判官の年収は?
裁判官の年収は、経験年数や役職により大きく異なりますが、平均すると約900万円前後とされています。
裁判官の給与は「裁判官の報酬等に関する法律」に基づき、経験や役職に応じた階段式の報酬体系が採用されています。
簡易裁判所判事の場合、経験により月給が23万円から81万円の範囲、判事補は23万円から42万円、判事は51万円から117万円となっています。
裁判官に向いている人とは
裁判官は司法試験に合格した人の中でも優秀な人だけがなれる特別な存在であり、その職務を果たすためには、真剣な決意と優れた資質が必要とされます。
公平な思考・判断力と、時代とともに変化する法律を正確に理解し、適用する能力が欠かせません。
人の人生を大きく左右する判断をするという責任を引き受け、新たな法律の制定や改正を学び続けるなど、正しい倫理観と向上心を持ち合わせる人が裁判官に向いていると言えます。
検察官
次に考えられるのは、法曹三者の一つである検察官です。
刑事事件において被疑者の取り調べや立証活動を行い、起訴するかどうかを決定する重要な役割を担っています。約2年ごとに全国各地の検察庁へ転勤することが多く、柔軟性と新しい環境への適応力が求められます。
司法修習生の中から、厳しさと公正さを備えた優秀な人材が検察官として選ばれ、公の秩序と安全を守るために活動しています。刑事法の専門家として働きたい人にとって、検察官は魅力的なキャリアパスの一つとなっています。
検事の業務内容
検察官は法に基づいて任命された公務員で、刑事司法手続きにおいて重要な役割を担っています。主な業務として、警察と連携して事件の捜査を行っています。
また、裁判所に事件を起訴し、公判の場で真相を追及します。証拠を提出し、証人尋問を行って真実を明らかにするのも検察官の役目です。
さらに、裁判所の判決の執行についても監督し、法と公正に基づいた刑の実行を確保します。
検察官は、事件の捜査から裁判、判決執行監督に至る一連の過程において、公正な司法実現のために重要な役割を果たしています。
検事の年収は?
検察官の年収は法律によって定められており、一般的には500万円から600万円程度ですが、経験と役職が上がるにつれて年収は増えていきます。
特に部長クラスになると1,000万円を超え、検事総長の年収は約1,800万円、次長検事は約1,500万円と高額になります。
また、検事20号としてキャリアを開始するため、初任給は237,700円と、一般的な大卒者と大学院卒者の間くらいの収入であると言えます。
検事に向いている人とは
検察官には正義感が欠かせない資質ですが、それだけではなく、感情をコントロールする能力と、短期間の中でも的確な判断力を発揮できる力が求められます。
検察官は社会の公正を守る重要な役割を担っているため、強い正義感と共に、冷静さと確かな判断力が必要不可欠なのです。
公平な視点から事件に臨み、感情的になることなく限られた時間の中で事案を公正に審査できる資質こそが、検察官に相応しい人物といえるでしょう。
大学教授・講師
弁護士は法廷での活躍だけでなく、大学の法学部や法科大学院、予備校などでも教育の場に関わることができます。
大学教授として後進を育成したり、予備校講師として受験生を指導したりと、豊富な経験と知識を次の世代に伝えることができます。他にも法律の専門家として一般向けに講演会を開く弁護士もいます。
こうしたキャリアを選ばれる弁護士の中には弁護士と兼業する方もいれば、専任で大学教授になる方もいるなど、働き方は多様だと言えます。
政治家
弁護士は法律知識や社会問題の解釈力を活かして、政治家として活躍する道を選ぶこともあります。多くの政治家は地方議員から始め、その経験を積んで国政に挑みますが、弁護士や公務員、医師、経営者などの様々な職業から政治家を目指す人はいます。
国会議員の平均年収は2,200万円程度と報酬は高いものの、対人スキルやリーダーシップ、体力が求められます。
正義感に満ちた弁護士のような人材にとって、政治家のキャリアは社会貢献の機会となりますが、プレッシャーの高い仕事でもあり、体力と持久力が必要不可欠です。
法律学者
法律学者は、法律の体系や理論、その解釈と適用について深く探求する法律の専門家です。彼らの活動の場は主に大学の法学部であり、学生の教育と研究に従事しています。
弁護士が法律を活用して具体的な紛争解決に当たるのに対し、法律学者は法律そのものを研究対象とし、その理論的側面に焦点を当てています。
法律学者の収入は、役職によって異なりますが、大学教授で平均1,000万円、准教授で850万円、講師で700万円程度とされています。弁護士に比べると収入を大幅にアップする機会は少ないものの、安定した高収入が得られる点が魅力です。
法律学者になるためには、法律に関する深い知識はもちろんのこと、熟考力と議論力、社会情勢への理解力が求められます。
司法書士事務所
司法試験に合格した人や弁護士として働く人の中には、少数ですが司法書士として働くことを選択する人がいます。弁護士資格を持つことで、司法書士事務所など別士業で働くことができるからです。
司法書士の初年度の年収は350万円から400万円程度ですが、経験を積めば収入も上がっていきます。
現代社会では、ワークライフバランスを重要視したキャリア選択をする人も増加し、司法書士事務所で働くことはその一つの選択肢となっています。
特許事務所
司法書士と同様に、弁護士資格を生かせる職種として弁理士があります。
弁理士は特許事務所で働き、技術分野や知的財産権の専門知識を活かした仕事をすることが多い職業です。
弁理士の平均年収は700万円から750万円程度ですが、勤務先やスキルによって大きく変動し、経験を積めば更に高い収入が期待できるため、特に営業力がある人に向いている職業であると言えます。
人気講座ランキング

 もっと見る>
もっと見る>- 特出した実績を持つ最注目のオンライン講座!


- 業界最高の合格者占有率を記録する王道予備校

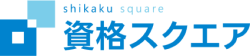 もっと見る>
もっと見る>- リーズナブルかつ高品質なコスパ抜群の講座
弁護士の最も一般的な就職先は法律事務所
弁護士の職場として最も一般的なのが法律事務所です。司法試験に合格した人の多くがその進路を選びます。法律事務所では、様々な経験を積むことができるからです。
法律事務所にはそれぞれに特徴があり、取り扱う案件の内容や特性が大きく異なります。大手法律事務所では大企業の法務業務や金融関連業務を扱うことが多く、一方で小規模な事務所では個人の法務相談や刑事事件を中心に扱います。
また、法律事務所で働く弁護士の呼び名は、階級や勤務形態により異なります。以下では法律事務所に所属する弁護士がどのような呼び名で呼ばれてるのかを見ていきます。
法律事務所の「ボス弁」
「ボス弁」は「ボス弁護士」の略で、自ら事務所を開業、経営している事務所の中心的な存在を指します。
ボス弁護士は、他の弁護士を雇っている人から、個人事務所を営む人まで様々です。
ボス弁護士は、法律知識に加えて経営手腕や人間関係能力も求められます。彼らは事務所運営と案件処理の両面で重要な役割を果たしており、法律事務所の中核を成す存在と言えます。
法律事務所の「パートナー弁護士」
法律事務所には、経営陣や共同経営者などの様々な役職のパートナー弁護士がいます。特に大規模な事務所では、経験や実績、役職によってパートナー弁護士の呼び名が異なってきます。
シニアパートナーは最高位の経験豊富な弁護士で、エクイティパートナーは事務所の所有権を持ち業績に応じた配当を受けます。
マネージングパートナーは事務所の経営を主導し、ジュニアパートナーは将来的に上位のパートナーに昇進する可能性のある弁護士のことを言います。
パートナー弁護士は、経営管理や若手弁護士の育成、クライアント対応、そして事務所の評判維持などの重要な役割を担っています。
法律事務所の「イソ弁・アソ弁」
イソ弁とは「居候弁護士」、アソ弁とは「アソシエイト弁護士」の略であり、どちらも法律事務所に雇われている新人弁護士のことを指します。
新人弁護士は、ボス弁護士や法律事務所に雇用され、新規の顧客を独自に確保するのではなく、法的知識やスキルを身につけることを主な目的として働きます。
特にイソ弁の中には、独立して事務所を開設したりすることを目指す人も多くいます。実力が認められると、上位の「ジュニアアソシエイト」や「シニアアソシエイト」などと呼ばれるようになり、地位が上がっていきます。
法律事務所の「ノキ弁」
ノキ弁とは、「軒並弁護士」の略で、法律事務所に所属せずに、事務所の一部を借りて独立して活動する弁護士のことを指します。
法律事務所に間借りをしている状態であり、その事務所とは別の個人事業者として働くので給与は発生しません。
また、法律事務所に就職することができずにノキ弁になる弁護士も、近年では多くなっています。
法律事務所の「タク弁」
タク弁は「自宅弁護士」の略で、法律事務所に所属するのではなく、自宅を事務所として活動する弁護士のことです。
法律事務所への就職ができなかったために自宅で事務所を開いた場合もありますが、自ら独立開業して自宅に事務所を構えている場合もあるなど、タク弁になる理由は様々であると言えます。
近年増加傾向にあるインハウスローヤー
弁護士の新しい働き方として、企業や団体に所属し、企業法務の専門家としての役割を担う「インハウスローヤー」が増えてきています。
従来、弁護士は自由業や法律事務所に所属するイメージが強かったですが、インハウスローヤーは一般企業に属しながら法的なリスク管理や問題解決に当たります。
以下では、今後さらに増加すると思われる弁護士のインハウスローヤーとしての働き方を紹介していきます。
民間企業で働くインハウスローヤー
近年、外資系や大手の一般企業の中には法的リスクを適切に管理し、利益の最大化を図るために、専属の弁護士である「インハウスローヤー」を雇用する企業が増えてきています。
インハウスローヤーは、企業内で発生する法律問題の処理や解決を行うほか、外部の顧問弁護士との連絡窓口としての役割も担っています。
彼らは商社や金融機関、IT企業などさまざまな業種の企業で、会社役員として法務部門に所属しています。企業内で直接法的問題に対応することで、トラブルの未然防止ができるため、その存在はますます重要視されています。
官公庁・公的機関で働くインハウスローヤー
近年、企業だけでなく、中央省庁や地方自治体の行政庁など公的機関においても、法令遵守やガバナンス強化の観点から、専門的な法的支援が求められるようになってきました。
そこで、公務員や常勤・非常勤職員として、弁護士がインハウスローヤーとして活躍する機会が増えてきています。彼らの主な役割は、法的な問題についてアドバイスを行ったり、リスク管理や訴訟対応といった実践的な支援を提供することです。
しかし、公的機関での業務は企業とは異なり、法制度や政策に関する理解が不可欠となるため、一定の経験が求められる場合が多くあります。
人気講座ランキング

 もっと見る>
もっと見る>- 特出した実績を持つ最注目のオンライン講座!


- 業界最高の合格者占有率を記録する王道予備校

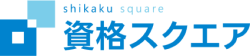 もっと見る>
もっと見る>- リーズナブルかつ高品質なコスパ抜群の講座
弁護士の就職活動
弁護士としてキャリアを歩む際、自分自身の価値観や目標を明確にすることが重要です。
仕事と生活のバランスや経済的な安定、職場環境、人間関係、社会貢献など、様々な要素を総合的に検討して自分に合った道を見つけることで、どこで働くべきかが明確になるでしょう。
弁護士になるには司法試験に合格するだけではダメ?
弁護士になるためには、難関試験と名高い司法試験に合格した後も、1年間の司法修習を経て、実務経験を積む必要があります。
しかし、これで弁護士としての道が開かれるわけではありません。司法修習生を待ち受ける次なる困難は厳しい就職活動です。
近年、司法制度改革により司法試験合格者数が増加した結果、弁護士人口が急増しました。特に都市部では、就職活動がかつてなく難しくなっており、地方でも容易に就職できるような状況にはありません。
司法試験合格後、約7割の修習生が法律事務所への就職を志しますが、そのためには司法修習中から就職活動の準備を怠ってはなりません。
年収を重視するなら「法律事務所」
弁護士の年収を向上させたい場合、法律事務所への就職がおすすめです。
特に、五大法律事務所や大手の企業法務を扱う法律事務所は、高年収が大きな魅力の一つとなっています。
一般的に弁護士の初年度年収は550万円程度ですが、五大法律事務所では1,000万円以上となり、約2倍の年収を得ることができます。
しかし、五大法律事務所への就職には高い条件が課されており、学歴や成績が重視されることから敷居が高いとされています。
安定した収入や残業の少なさを重視するなら「インハウスローヤー」
企業内弁護士(インハウスローヤー)は、ワークライフバランスが良好で福利厚生も充実しているため、注目を集めています。企業に直接雇用されるのでサービス残業や休日出勤が少なく、働き方改革が浸透している環境で働けます。
プライベートの時間を確保しやすく、生活リズムを整えやすいのが特徴と言えます。また、一般企業では法律事務所と比べて手厚い福利厚生が期待できます。
年収や賞与がすぐに上昇することは少ないかもしれませんが、安定した収入機会があり、自ら案件を探す必要がありません。
そのため、安定した収入と働きやすさを求める人には、インハウスローヤーがおすすめだと言えます。
弁護士(司法修習生)の就活|履歴書で有利になるポイントは?
弁護士として活躍するためには、履歴書を通して自身の強みを効果的に表現することが重要です。
以下では弁護士(司法修習生)の履歴書で、就職活動の際に注目されやすいポイントを確認していきます。
司法試験の成績
司法試験の成績は特に、法律事務所への就職活動において重要な評価基準となります。
就職活動が競争が激しくなる中、多数の応募者がいるため、事務所側は書類選考で人数を絞り込む必要があります。そのような状況下で、客観的な選考基準として司法試験の成績が採用されることが多くなっています。
特に五大法律事務所などの大手事務所ではこの傾向が顕著で、「○位以内の成績者」など、明確な採用基準を設けているところも多くあります。そのため、書類選考を何度も通過できない場合は、応募先を見直すことも考えましょう。
司法試験の受験回数
司法試験の受験回数は、法律事務所の選考において重要な判断材料となる可能性があります。特に五大法律事務所のような大手法律事務所では、一発合格を高く評価する傾向にあります。
一方で、2〜3回程度の受験であれば大きな問題にはなりませんが、4回以上に及ぶと書類選考で不利に働く可能性が高まります。
そのため、その点を補えるような自身の長所や強みをアピールし、他の就活生と差をつける必要が出てきます。
受験生の皆さんは、就職活動に向けて受験のタイミングなども考慮する必要があると言えます。
出身の法科大学院と成績
特に一部の大手法律事務所では、卒業した大学や法科大学院を採用時に考慮する傾向にあります。もちろん、出身校だけが採用の決め手となるわけではありませんが、選考の際に影響を及ぼす可能性があることを認識しておく必要があります。
また、法科大学院での成績も採用を検討する上での材料の一つとなり得ます。ただし、最も重視されるのは司法試験の成績であり、法科大学院の成績はそれを補完する位置付けになります。
しかし、法科大学院で特に優秀な成績を修めたり実績を残した場合には、履歴書にてそれをアピールしてみましょう。そうすることで、一定の評価を得られる可能性があります。
大学・大学院時代の所属ゼミ
横のつながりが強い弁護士業界では、所属していたゼミの名前も重要視される傾向があります。特に著名な教授や弁護士が主導するゼミに在籍していた場合、高く評価されるでしょう。
履歴書にはゼミ所属を明記し、そこで得た具体的な経験やスキルを記載することで、自分の専門性や強みを効果的にアピールできます。
面接官の弁護士の関心を引き、有利に働くこともあると言えます。
弁護士以外の資格(TOEIC、金融系資格など)
履歴書作成時には、他の資格を持っていることも有利に働く場合があります。
中小規模の法律事務所では、会計や税務の業務を兼ねる場合が多いため、簿記や金融、財務関連の資格を持っていると高く評価されます。
一方、大手法律事務所では海外業務が多いため、英語力を証明するTOEICなどの資格を所持していると有利になります。特に700点以上のTOEICスコアは強みとなるでしょう。
弁護士の就職先についてまとめ
弁護士の活躍の場は、法律事務所や企業の法務部門、そして公務員など、多岐にわたっています。司法試験合格後は、実務研修を経て、自身のキャリアプランを立てていくことが求められています。
さらに、就職活動では、司法試験や大学時代の活動が重要となり、求められるスキルや得意分野を持つことも大切になります。弁護士としてどのようなキャリアを選ぶかはあなた次第なのです。
本記事を参考にして、弁護士としての将来について考えてみてください。