中小企業診断士合格までの勉強時間は?難易度や最短合格のための勉強法まで解説
更新
経営コンサルタントとしての唯一の国家資格である中小企業診断士。
一筋縄では行かない難関資格としても名高いですが、中小企業診断士の取得にはどれほどの勉強時間が必要なのでしょうか。
この記事では、中小企業診断士合格までの勉強時間を実際の合格者アンケートをもとに紹介していきます。また、合格者が実行している勉強法や最短合格スケジュールについても解説するので、中小企業診断士への合格を目指す方はぜひご覧ください。
このページにはプロモーションが含まれています
中小企業診断士の勉強時間はどのくらい?

勉強時間は870時間、学習期間は1〜2年
中小企業診断士合格までの勉強時間 | 回答数 |
300時間未満 | 0 |
500~700時間 | 2 |
700~900時間 | 4 |
900~1100時間 | 3 |
1100~1300時間 | 0 |
1300時間以上 | 1 |
中小企業診断士合格までの期間 | 回答数 |
6ヶ月未満 | 0 |
6~12ヶ月 | 0 |
1~2年 | 7 |
2~3年 | 1 |
3~4年 | 1 |
4年以上 | 1 |
スキルアップ研究所が実施した中小企業診断士試験の合格者アンケートによると、中小企業診断士の合格までには平均で870時間が必要という結果となりました。これは1日に2時間、すなわち1週間に14時間の勉強を続けた場合、約1年半の期間を要する計算となります。
また、アンケートによると、合格までの平均学習期間は1〜2年となっており、やはり中小企業診断士を目指すのであれば長期スパンでの計画となることが明らかとなりました。
ただし当然、必要な勉強時間は人によって差があり、アンケート結果内でもばらつきが見られます。簿記やFPといった金融関連の資格を取得している方や、大学で経済・経営を専攻していた方は比較的予備知識があるため、中小企業診断士試験の難易度の高い分野でもさほど苦に感じないということもあるでしょう。しかし予備知識のない人にとっては、金融関連の分野などが難関となる可能性が高いといえます。
そのため、勉強時間の目安にはとらわれず、実際に勉強に取り組む際には自身が理解しているかどうかを重視すべきです。
【調査概要】
項目 | 内容 |
調査方法 | インターネット調査 |
調査期間 | 2024年1月21日〜2024年1月28日 |
調査概要 | 中小企業診断士試験の学習に関するアンケート |
調査対象 | 20代〜50代の中小企業診断士試験に合格した方10名 |
最短合格を目指すための勉強スケジュール

中小企業診断士試験において、科目ごとの勉強時間配分は重要な戦略となります。
ここからは、最短合格を実現するためのスケジュールを紹介していきます。
科目ごとの勉強時間の配分
中小企業診断士試験では、特に、「財務・会計」と「経済学・経済政策」は1次試験での難易度が高く、専門知識や基本的な経済理解が必要なため、勉強時間の半分弱をこれらの分野に割くことが一般的です。一方で、企業経営理論や運営管理は財務・会計ほど難しくはないものの、2次試験の事例問題と深い関連があり、しっかりと理解を深める必要があります。
科目別の難易度や2次試験との関連性を考慮して、効果的な時間配分を行うことが推奨されます。
以下、科目・分野別の勉強時間の目安の表となります。(二次試験の勉強時間を含む)
科目 | 勉強時間 |
財務・会計 | 200時間 |
経済学・経済政策 | 160時間 |
企業経営理論 | 120時間 |
経営法務 | 120時間 |
経営情報システム | 100時間 |
運営管理 | 100時間 |
中小企業経営・政策 | 70時間 |
最短で6ヶ月で合格を目指せる
例えば、平日に4時間、土日に8時間勉強することで、週に約36時間の勉強時間を確保することができます。このペースを維持すると、必要な平均学習時間である870時間の勉強を約24週、つまり約6ヶ月で完了させることができます。
学生や主婦の方など、まとまった勉強時間が確保しやすい方は、短期集中で半年合格が狙えるでしょう。効率よく計画を立て、集中して取り組むことが合格へのカギとなります。
社会人なら1年合格が現実的な最短
社会人が中小企業診断士試験に合格を目指す場合、現実的な目標は学習期間1年での合格です。
平日に2時間、土日に4時間ずつ勉強時間を設けることで、週に約18時間の学習が可能となります。この学習ペースでは、合計870時間の勉強を48週、すなわち約12ヶ月で達成することができます。
鬼門は、平日の2時間をどう確保するかです。通勤時間でも、往復にすると30分〜1時間以上になる方も多いはずです。通勤時間や昼休みといった隙間時間を効果的に利用して、勉強時間に充てることが成功の鍵となります。継続的に努力を重ねることで、働きながらでも1年での合格を目指すことが現実的な目標となるでしょう。
科目合格を使った1.5〜2年計画もおすすめ
中小企業診断士試験の科目合格制度を利用し、1.5〜2年計画で合格を目指すのは、戦略として非常におすすめです。この場合、1年目に試験のいくつかの科目で合格を目指し、残りの科目は2年目で挑戦することになります。
科目合格制度を活用すれば、試験準備の負担を分散させることが可能となり、また、全科目を一度にクリアするよりも心理的なプレッシャーを軽減できます。
一度で全科目に合格することを目指し、全科目が中途半端になってしまうよりも、合格を狙う科目を絞ってしっかりと仕上げる方が現実的です。1年目で合格した科目の学習内容が2年目の学習に役立つことも多く、効率的に試験対策を進めることができます。
段階的に試験対策を進めることで、合格への道がより具現化されていくでしょう。
科目合格制度とは?
中小企業診断士試験における科目合格制度とは、1次試験で各科目の基準点以上を取った場合、その科目の受験を翌年以降免除できる制度です。科目合格の有効期限は3年間で、この期間内に1次試験の全科目に合格する必要があります。
なお、基準点は、「満点の60%を基準として、試験委員会が相当と認めた得点比率」であるため、科目により異なります。
中小企業診断士の難易度は?
最短合格へ向けたスケジュール感を把握できたところで、改めて中小企業診断士の難易度を確認していきましょう。
合格率
年度 | 受験者数*1 | 一次試験合格者数 | 一次試験合格率*2 | 二次試験合格者数 | 二次試験合格率 | 最終合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年 | 16,627 | 3,094 | 21.7% | 910 | 18.5% | 4.0% |
平成26年 | 16,224 | 3,207 | 23.2% | 1,185 | 24.3% | 5.6% |
平成27年 | 15,326 | 3,426 | 26.0% | 944 | 19.1% | 5.0% |
平成28年 | 16,024 | 2,404 | 17.7% | 842 | 19.2% | 3.4% |
平成29年 | 16,681 | 3,106 | 21.7% | 828 | 19.4% | 4.2% |
平成30年 | 16,434 | 3,236 | 23.5% | 905 | 18.8% | 4.4% |
令和元年 | 17,386 | 4,444 | 30.2% | 1,088 | 18.3% | 5.5% |
令和2年 | 13,622 | 5,005 | 42.5% | 1,174 | 18.4% | 7.8% |
令和3年 | 18,622 | 5,839 | 36.4% | 1,600 | 18.3% | 6.7% |
令和4年 | 20,212 | 5,019 | 28.9% | 1,625 | 18.7% | 5.4% |
令和5年 | 21,875 | 5,560 | 29.6% | 1,555 | 18.9% | 5.5% |
令和6年 | 21,274 | 5,007 | 27.5% | 1,516 | 18.7% | 5.1% |
*1:欠席科目がある人を含む
*2:(一次試験合格者数)÷(欠席した科目が一つもない受験者数)で算出
参考:J-SMECA 一般社団法人中小企業診断協会「中小企業診断士試験 申込者数・合格率等の推移 」
中小企業診断士試験の最終合格率は約4〜8%と、受験者にとっては非常に厳しい数字です。年によっては4%を切ることもあるようです。
一次試験の合格率は年によって変動がありますが、大体30%前後で推移しており、良い年では40%を超えることもあります。一方で、二次試験の合格率は近年約18%となっており、一次試験をクリアした受験者にとっても引き続き高いハードルが設けられています。結果、一次試験と二次試験を両方潜り抜けられるのは、毎年一握りの受験者のみになってしまうのです。
中小企業診断士試験の合格を目指すには、やはり一朝一夕ではどうにもならず、計画的な学習が必要であることが伺えます。
出典:JF-CMCA公式サイト
合格ライン
中小企業診断士試験の合格基準は、受験者にとって重要な目標の一つです。
1次試験では、総得点が満点の60%以上であること、そして全科目で40点以上を獲得している必要があります。また、各科目における合格ラインは満点の60%以上と設定されています。
2次試験においても、筆記試験では総点数の60%以上及び全科目で40点以上が合格の条件とされ、口述試験では評定が60%以上となっています。
各試験の合格基準を意識しながら、バランスよく、かつ苦手を作らない学習が求められます。
出典:JF-CMCA公式サイト
大学入試で例えると偏差値63
中小企業診断士の難易度を偏差値で表すと、偏差値63となります。
この偏差値は大学入試に当てはめるとMARCHくらいになるので、決して最難関ではありませんが、それでも高い難易度を誇り、かつ十分な権威性を持つ資格といえます。
大学受験との比較は、中小企業診断士試験が求めるレベルの高さと、合格した際に得られる社会的評価の重さを理解する上で一つの参考になるでしょう。
中小企業診断士に独学で合格は可能?
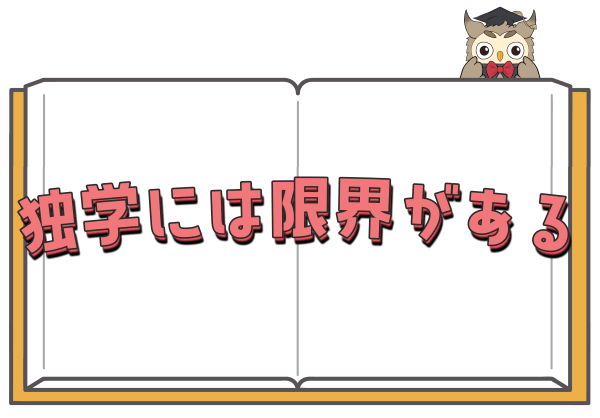
独学で合格は非常に難しい
上述の通り、中小企業診断士は非常に難易度の高い資格となるため、独学での合格は大変難しいといえます。
この試験は、幅広く専門的な知識が必要で、それを自力でカバーするには膨大な時間と努力が必要となります。上述の通り、試験の合格率や合格基準からも、その高いハードルが伺えます。
これに対し、資格予備校・通信講座などを利用すれば、試験の傾向などから頻出部分を優先して勉強を進められるなど、効率的な学習をサポートしてもらえます。
そして多くの受験生がこうした講座での指導を受けた上で試験に臨んでくることを考えても、独学で合格ラインを超えるのは非常に厳しいことが分かるでしょう。
通学不要でオンラインでも学べる通信講座であれば、独学と同様に働きながらでも隙間時間に勉強が進められるので、社会人の方であれば通信講座の利用をした対策を行うことを推奨します。
実績抜群のスタディングを活用して学習を進めよう
中小企業診断士対策の予備校・通信講座の中でも、業界トップクラスの合格実績を誇るスタディングは特におすすめです。
スタディングはスマホ学習に特化した通信講座であり、講義の視聴、テキストの閲覧、問題演習まで全てオンライン上で完結します。そのため、なかなか机に向かって学習する時間が取れない社会人の方でも、通勤時間などの隙間時間を使って効率よく試験対策を進めることが可能です。
また、費用の安さも魅力的であり、スタディングであればTACなどの大手予備校の3分の1以下の価格で受講することが可能です。ぜひこの機会にスタディングの講座をチェックしてみてはいかがでしょうか。
独学のメリット
自分のペースで勉強できる
中小企業診断士の試験は幅広い分野からの出題が特徴ですので、自分のペースで学習を進められることが大きなメリットになります。中小企業診断士試験は試験範囲が広いため、得意分野にはあまり時間をかけず、苦手分野に集中して取り組むことが重要になります。独学なら、自身の理解度に応じて学習計画を柔軟に調整でき、弱点を効果的に強化できるのです。
さらに、仕事や日常生活に合わせて学習スケジュールを自由に変更できるのも独学の魅力です。これにより、長期にわたる試験対策でも無理なく継続することができます。
費用を抑えられる
中小企業診断士の試験は科目数が多く専門性も高いため、講座やスクールでの受験対策は費用がかさみがちです。しかし、独学なら大幅にコストを抑えられます。教科書や問題集などの書籍を中心に学習を進めることで、効率的に費用を節約できるのです。
幸いなことに、中小企業診断士試験には豊富な市販教材があります。過去問題集や科目別の解説書など、比較的安価で充実した教材が揃っているため、低コストでも十分な対策が可能です。さらに、インターネット上の無料資料や過去問データを活用すれば、費用を抑えつつ質の高い学習を進められます。
柔軟な教材選びができる
中小企業診断士試験は、経済学、経営戦略、財務会計など幅広い分野を網羅しています。そのため、独学では柔軟な教材選びができることが大きな強みとなります。市販の教材は実に豊富で、基礎知識をしっかり押さえられるものから、難度の高い問題に挑戦できる応用的なものまで、幅広く選択できます。
さらに、各科目ごとに強化したい分野に特化した教材をピンポイントで購入できるのも魅力です。これにより、自分の弱点を効果的に克服することが可能になります。加えて、過去問題集やオンラインの無料学習リソースも豊富にあるため、自分の学習状況や目標に応じて最適な教材を自由に組み合わせられます。
独学のデメリット
理解に時間がかかる
中小企業診断士の試験は、専門性が高く幅広い知識が要求されます。財務会計や経営戦略など多岐にわたる分野を学ぶ必要があるため、独学では理解に時間がかかるという難点があります。
特に財務・会計分野では、数字の分析や計算スキルが求められます。これらの背景知識が不足していると、内容の把握に苦労することがあるでしょう。また、経済学や法務などの科目は専門用語や理論が多く、一人で理解するには相当な努力が必要です。
モチベーションを保ちにくい
中小企業診断士試験は、合格までに長期間の学習を要するため、独学では学習意欲の維持が大きな課題となります。試験科目は経済学、財務会計、経営戦略など多岐にわたり、全体の学習量が膨大なため、継続的な勉強が求められます。
独学の場合、自己管理によるスケジュール調整が必要ですが、日々の生活や仕事に追われると、計画通りに進まず、学習意欲が低下しがちです。さらに、難解な科目が多いため、理解に苦しむ場面でモチベーションを保つことが一層困難になります。
特に中小企業診断士試験は合格率が低く、一度で合格できるとは限りません。そのため、長期的な視点で粘り強く取り組む姿勢が不可欠です。
情報の偏りや不足のリスクがある
中小企業診断士試験を独学で目指す場合、情報の偏りや不足が大きな課題となります。試験範囲は経済学、財務、経営戦略など多岐にわたるため、全分野をバランス良く学習する必要があります。しかし、独学では主に市販の参考書やインターネット上の情報に頼ることになり、最新の出題傾向や重要テーマを見逃す恐れがあります。特に、中小企業診断士試験は年ごとに傾向が変化することもあり、最新情報の入手が重要です。
このリスクを軽減するには、体系的かつ最新の情報に基づいた学習方法が望ましいでしょう。専門家監修の教材や、実際の試験傾向を反映した学習プランを活用することで、独学では補いきれない部分をカバーできます。
そのため、多くの受験者が通信講座を選択しています。通信講座では、最新の試験情報に基づいた効率的な対策が提供されるため、情報の偏りや不足を防ぎつつ、合格に向けて着実に学習を進めることができます。
働きながら合格は可能
実際に、働きながら中小企業診断士試験の合格を掴む方は多くいらっしゃいます。
以下の表は、令和6年度に中小企業診断士試験に合格した方の職業別割合を表した表です。
職業別割合 | 合格者数 | 割合 |
経営コンサルタント自営業 | 16人 | 1.1% |
税理士・公認会計士等自営業 | 46人 | 3.0% |
上記以外の自営業 | 28人 | 1.8% |
経営コンサルタント事業所等勤務 | 48人 | 3.2% |
民間企業勤務 | 1,035人 | 68.3% |
政府系金融機関勤務 | 38人 | 2.5% |
政府系以外の金融機関勤務 | 107人 | 7.1% |
中小企業支援機関 | 16人 | 1.1% |
独立行政法人・公益法人等勤務 | 16人 | 1.1% |
公務員 | 63人 | 4.2% |
研究・教育 | 6人 | 0.4% |
学生 | 21人 | 1.4% |
その他(無職を含む) | 76人 | 5.0% |
合計 | 1,516人 | 100.0% |
中小企業診断士試験に挑むには必然的に勉強期間が長くなるため、働きながらでないと生計が保てなくなることからも、働きながら合格する方の割合が多くなるといえます。
多くの合格者が1年以上の長期間をかけてじっくりと準備を進め、仕事と学習のバランスを取りながら試験に臨んでいます。働きながらの合格は、十分な準備と適切な戦略があれば、実現可能な目標です。
中小企業診断士に合格するための勉強法
中小企業診断士試験に合格するためには、どのように勉強していけばいいのでしょうか。ここでは、中小企業診断士の勉強法について解説します。
過去問を軽視しない
中小企業診断士試験の対策には、過去問を利用した学習が重要です。
例えば診断士試験には毎回問題の20%ほどがかなり難しくなっており、これらに時間を費やし過ぎると解くべき他の80%の問題に取り組む時間が不足する恐れがあります。
一方で診断士試験の多くの問題は過去問に類似しているため、過去問演習を通じて基本的な知識を身に付け、問題を見極める力や知識をアウトプットする力を養うことが合格への鍵となります。
過去問の分析結果を手に入れよう
中小企業診断士の試験対策において高い指導実績を持つ資格学校のクレアールでは、こうした過去問分析に基づいた効率的な学習法を「非常識合格法」としてまとめ、講義のカリキュラムの基礎としています。
通常この勉強法を実行するにはクレアールの講座を受講するほかありませんが、現在クレアールでは「非常識合格法」のノウハウをまとめた書籍を無料でプレゼントしています。
これは特に初学者の方にとっては試験の全体構造をより明確に理解し、合格への道のりを効果的に描く手助けになるはずです。
ただしこのプレゼントは先着100名限定となっているので、この機会を逃さず手に入れておくのが良いでしょう。
1日に取り組む科目は少しずつ
中小企業診断士試験の学習においては、1日に取り組む科目数を少なくし、それぞれに1時間ほどのまとまった時間を割くようにするのがおすすめです。具体的には、1日に2〜3科目に集中することで、各分野に対する理解を深めていくようにします。
さらに、学習の順序にも工夫をすることが重要です。時間を要する科目や理解が難しい科目を学習計画の初期段階に位置づけ、暗記が中心の科目は後半に取り組むことで、効率的に知識を蓄積することができます。
インプットとアウトプットのバランスを意識
これは全ての勉強に言えることではありますが、インプット・アウトプットを両方バランスよく行い、試験で通用する知識を身につけることが重要です。
テキストを読むなどのインプット学習に比重が偏りがちですが、身につけた知識を正しく使えるか、また正しく理解できているかは、問題を解くなどのアウトプットを経験しないとわからないことです。インプットとアウトプットをバランスよく重ねることで、正しい知識の定着を促していきます。
2次試験を見据えた1次試験の勉強を
中小企業診断士試験の1次試験では専門知識を問い、2次試験ではその知識をどう応用できるかが試されます。特に、企業経営理論、財務・会計、運営管理、経営情報システムの4科目は、2次試験と深い関連があります。
そのため、1次試験の勉強では、単に知識を暗記するだけでなく、その内容を実際に活用する力を養うことが重要です。理解した知識を自分のものとして使いこなす意識を持つことで、2次試験で求められる応用力を身につけることができます。
また、最終的なゴールは単に試験に合格することではなく、中小企業診断士として実際に活躍することにあります。この視点を持ちながら、表面的な理解にとどまらない本質的な学習を心がけることが、合格を超えた目標達成への鍵となります。
全てを完璧にしようとしない
とはいえ中小企業診断士試験の学習において、全てを完璧に理解しようとする姿勢は、実は逆効果になることがあります。
試験範囲は非常に広く、全てを完璧に把握しようとすると、学習量が膨大になりすぎてしまい、結果的に全ての理解が半端になってしまう恐れがあります。そのため、合格ラインに焦点を当て、合格するために必要な知識とスキルを確実に身につけることを目指すべきです。
完璧を目指すのではなく、堅実に合格を目指す勉強方法を選ぶことが、賢明なアプローチと言えるでしょう。
スキマ時間も活用して無理のない勉強時間確保を心掛ける
中小企業診断士の合格に必要な勉強時間はかなり長いです。1日2~3時間は勉強時間を確保したいところでしょう。しかし、3時間もまとまった勉強時間を取ると集中が持たず、かえって効率が落ちてしまいます。
そのため、電車内での時間やレストランでの待ち時間など、手持ち無沙汰でスマホをいじるくらいしかできない時間を勉強時間に充てましょう。そうするだけでも1日30分から多い人なら1時間の勉強時間になるはずです。
多くの人が、1日の食事を3回に分けて摂っていると思います。一気に3時間勉強しようとすることは、1日の食事を全て1回で食べきってしまうようなものです。1日に何回か勉強することで、ストレスのかからない勉強ができ、中小企業診断士合格に近づきます。
問題演習を繰り返すことで解き方を覚えていく
問題演習はアウトプットに含まれる勉強方法ではあるのですが、同じ問題を何度も繰り返し解くことで同じような問題の解法をインプットすることができます。基礎知識が身につけば自然とアウトプットもできるようになるわけではなく、問題への取り組み方も身につける必要があるのです。
そのため、インプットに時間をかけて教科書を完璧に理解してから問題演習をするのではなく、ある程度教科書の内容を網羅したら一度問題演習に取り組み、理解があやふやだった部分を見直して教科書を読み返し、また同じ問題に取り組むというサイクルを繰り返すようにしましょう。
中小企業診断士の勉強時間のまとめ
本記事では、合格者アンケートをもとにして中小企業診断士合格までの勉強時間について解説してきました。
中小企業診断士試験の合格には、平均870時間という長期間にわたる学習、そして粘り強く学習を継続する根気が求められます。
正しい勉強法を押さることで着実に実力を身につけていくことができるので、合格に達するまで努力を重ねていきましょう。


