薬機法管理者とは?コスメ薬事法管理者との違いや意味ないなどの評判についても解説
更新
薬機法管理者とコスメ薬事法管理者は、一見同じような職種に聞こえますが、実はそれぞれの役割と扱う領域が異なります。
この2つの職種の違いや重要性を理解するには、それぞれが携わる業界の特性を把握することが欠かせません。
この記事では、両者の定義や関連する職業の概要、さらにはメリット・デメリットまでを分かりやすく解説します。
このページにはプロモーションが含まれています
薬事法管理者はどのような資格?
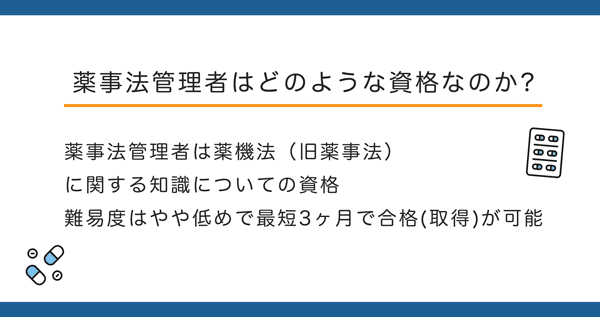
薬事法管理者とは、薬事法有識者会議が主催している民間資格のことを指します。
ヘルスケアビジネスで必要とされる医薬品や医療機器などの製造から販売、管理に至るまでの流通全般に関わる薬機法の知識に関する資格です。
この資格を持つことで、企業の法令遵守体制の構築や、適切な製品開発・販売を推進する役割を担うことができます。
また、医薬品などの安全性確保と使用者の利便性向上、消費者の生命と健康の維持にも貢献しています。
薬事法管理者の資格概要
薬事法に関する専門知識を証明する資格として、民間の「薬事法管理者資格」が挙げられます。民間資格ながらも、ヘルスケア関連事業において重要な役割を担っているのが特徴です。
この資格を受験するには、まず薬事法有識者会議が認定する講座を修了する必要があります。そして、インターネットを通じて月に3回行われる筆記試験に合格しなければなりません。
受験料は講習料とあわせて3万円程度です。更新料は、1・2回目は2万円、それ以降は1万円となっています。合格率は公開されていませんが、一定の学習が求められる資格となっています。
薬事法管理者資格とは別に「コスメ薬事法管理者資格」もあり、この資格は化粧品やコスメ関連の専門知識に重点が置かれています。
難易度はやや低め
合格率が公表されていないため具体的な難易度を示すことはできませんが、薬事法管理者の資格取得は、比較的簡単な方だと言えます。
その理由は、試験が月3回と頻繁に実施されており、公式情報によれば最短3ヶ月の学習期間での合格が可能なためです。
国家資格と違い年間を通して学習する必要はなく、1年に1度しかチャンスがないというプレッシャーもありません。
最短3ヶ月で合格(取得)が可能
薬事法管理者試験は、約3ヶ月という短期間で資格を取得できると言われています。
この期間であれば、粘り強く学習を続けることで薬事法についての深い知識と理解を身につけることができます。
短期間でスキルを習得できる上にその知識を直ちに活用できるため、コストパフォーマンスに優れた資格と言えます。今後のキャリアにも役立つスキルが身に付くことでしょう。
公式の講座を利用して試験勉強ができる
薬事法管理者の資格取得を目指す際、薬事法ドットコムの公式eラーニング講座が大変役立ちます。この講座では、試験対策だけでなく実務で役立つ知識やスキルも広く学べるため、初心者にもおすすめです。
薬事法の具体的な法構造に始まり、適切な表現力に至るまで様々な知識を身につけられます。
また、1年間繰り返し受講できるため、試験に自信がない場合でも合格できるまで自分のペースで学習を重ねることができます。
薬事法管理者とコスメ薬事法管理者は何が違うのか
「薬事法管理者」と「コスメ薬事法管理者」の違いを説明していきます。
薬事法管理者は、医薬品や医療機器などの幅広い分野を網羅しています。一方で、コスメ薬事法管理者は化粧品に特化した資格となっています。
この違いから、薬事法管理者の学習範囲は広く、資格取得までにかかる費用も約84,800円と高額となっています。一方、コスメ薬事法管理者は50,000円と比較的手頃な費用で取得することができます。
化粧品業界を目指す方や化粧品の専門知識への理解を深めたい方は、コスメ薬事法管理者の資格取得をお勧めします。
薬事法管理者の出題内容
薬事法管理者の資格試験は、薬事法から化粧品・医療部外品に至るまで、幅広い分野の知識を問う試験です。
薬事法の実践的理解から始まり、違反時のペナルティ、サプリメントや健康食品、表示・広告規制、美容・健康機器などの実務に直結する内容が出題されます。
講習を通して段階的に学習を進めれば、eラーニングによる効率的な知識習得が可能となります。
薬事法管理者のカリキュラム内容
薬事法管理者のカリキュラムは全部で14章から構成されています。
章 | 内容 |
|---|---|
第1章 | 薬事法の基本的理解 |
第2章 | 薬事法違反のペナルティ (1) 行政指導 |
第3章 | 薬事法違反のペナルティ (2) 刑事摘発 |
第4章 | 景表法の実践的理解 |
第5章 | 薬事法とサプリメント(※狭義のサプリメント) |
第6章 | 健康増進法とサプリメント |
第7章 | 行政関与型 (1) 特保 (特定保健用食品) |
第8章 | 行政関与型 (2) 栄養機能食品 |
第9章 | 明らか食品 |
第10章 | 使える表現・使えない表現(広告表現) |
第11章 | ダイエット食品 |
第12章 | 機器タイプ(健康・美容機器) |
第13章 | 塗りタイプ(化粧品・医薬部外品) |
第14章 | 行政関与型 (3) 機能性表示食品 |
薬機法管理者の資格はそもそも民間資格で、通信講座や塾にはなく、上記のカリキュラムの講座を受講する必要があります。そのため、このカリキュラムにしたがって教材を読み進めていくだけで大丈夫です。
薬事法管理者資格を取得したいときの流れ
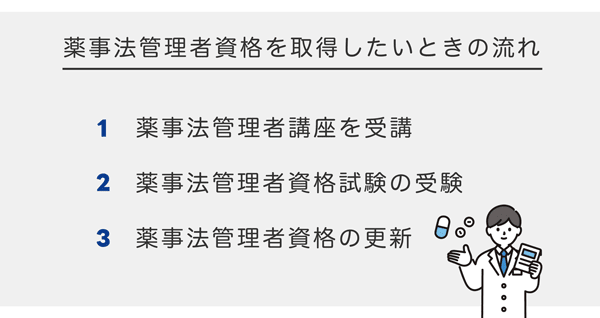
本章では、薬事法管理者資格を取得したい時の流れについて説明していきます。
薬事法管理者講座を受講
まずは、薬事法管理者講座を受講する必要があります。
インターネットで受講する場合は、以下の手順を踏みます。最初にユーザー登録を行い講座に申し込みます。費用を支払うと受講者IDとパスワードが発行され、入金確認後1年間が受講期間となります。
また、受講開始時には、本人確認のため身分証の提出が求められます。
受講料の支払い方法については、セット購入の場合と異なる点に注意しましょう。
薬事法管理者資格試験の受験
次に、薬事法管理者資格試験を受験します。
1年間の受講期間が終了した後は、資格試験の申し込みを行いましょう。支払いを済ませたら資格試験を受験することができます。
合格すれば資格の更新ができ、不合格の場合でも追試を受けて再挑戦することが可能となります。
薬事法管理者資格の更新
更新日の1カ月前になると、登録したメールアドレスに通知が届きます。その通知を受けたら、すぐに更新手続きを開始しましょう。
更新をするためには、オンラインで学習コースを受講しチェックテストに合格する必要があります。そして、チェックテストに合格すると新しい認定カードが送付されます。
有効期限は資格の取得後1年間となっているため、更新手続きは忘れずに行うようにしてください。
薬事法管理者を取得する時の注意点
資格の更新料がかかる
薬事法管理者の資格を維持するためには、継続的な学習と費用が欠かせません。
具体的には、毎年20,000円の更新料を支払い、最新の知識を得るために更新講習会を受講することが義務付けられています。
更新手続きを怠ると資格を失う可能性があるため、更新料の支払いと講習受講には細心の注意を払う必要があります。
薬事法管理者は国家資格ではないので仕事があるとは限らない
薬事法管理者の資格は国家資格ではありません。そのため、その価値は特定の分野で自分の能力や知識をアピールする手段としてどれだけ活用できるかにかかっています。
例えば、ライターやマーケター、アフィリエイターなどの職種では、新薬の開発や製造、販売に関する業務の専門性と信頼性を高めるのに役立ちます。
薬事法管理者の資格は、同業者との差別化を図りたい人にとって有益な資格と言えますが、その前提として活動分野がある程度決まっている点に留意しておきましょう。
資格取得にかかる費用が少し高い
薬事法管理者の資格取得には一定の費用がかかります。
初年度は、講座料金89,800円と更新料10,000円で合計約10万円が必要です。
万が一試験に不合格となった場合は、追試料金10,000円を支払う必要があります。
しかし、追試制度のおかげで資格取得に必要な費用を抑えられる面もあり、無駄な時間とお金の節約につながるメリットがあります。
講座を受講しないと受験資格がない
薬事法管理者の資格取得のためには、まず薬事法ドットコムの講座を受講する必要があり、その受験資格を得たうえで認定試験に合格することが求められています。
講座はeラーニング方式なので、自分のペースで学習でき最短3ヶ月での合格も可能となります。
そのため、自分のペースで合格を目指せますが、試験受験には講座受講が必須となることを覚えておいてください。
薬事法管理者の年収は?
薬事法管理者の資格自体は直接的に年収アップにはつながりませんが、その知識を活かせるヘルスケア業界や化粧品業界に就職すれば、キャリアアップとともに転職や再就職時に有利に働くでしょう。
ある求人情報サービスによると薬事法管理者の資格が活かせる業界の年収は、医薬品メーカーでは約565万円、医療機器メーカーで約487万円、化粧品メーカーで約424万円となっています。
実際に多くの企業が薬事法管理者やコスメ薬事法管理者の資格保有者を歓迎し、給与アップの好条件を提示しています。
さらに、この資格を持つことで、薬事法や医薬品関連の記事作成時に高い単価設定が可能になるなど、文章作成やライター業務においても有利になるでしょう。
薬事法管理者は意味ないのか

薬事法管理者は、医薬品や医療機器の製造・販売に関わる重要な役割を担っています。
この資格は、専門的な知識を身につけることで、医薬品業界の信頼性を高めて業績向上に貢献できます。したがって、薬事法管理者という資格は決して無意味ではありません。
本章では、薬事法管理者の資格が生かせる仕事・求人を説明していきます。
薬事法管理者が活かせる仕事
まず、広告会社やメーカーなどの業界で活かすことができます。例えば、広告会社では薬事法に関する専門知識を持つ人材が求められ、薬事法管理者がその役割を担うことができます。
一方、Webライターも、この資格が直接的に活かせる職業となります。薬関連の記事を執筆する際には幅広く正確な知識が必要とされているため、薬事法管理者資格を持つライターは一般のライターよりも高い単価を得られる可能性があります。
具体的には、資格情報サイト「資格広場」によると、薬事法管理者資格を持つライターは10円以上の単価を得ることが多いそうです。
さらに、ヘルスケア業界や化粧品業界でも有利に働くでしょう。専門的な知識を活かせる資格として、これらの業界での就職や転職、キャリアアップの際に評価されます。
薬事法管理者が活かせる求人
薬事法管理者の役割は、企業や業界によって重要度が変わってくるため、「薬事法管理者は意味がない」と誤解されがちですが、実際の求人を見るとその重要性を確認することができます。
例えば、ある企業では、広告やPRの内容が薬事法・景品表示法に適合しているかをチェックする役割が求められており、正社員雇用で基本給は251,600円以上、手当も支給されています。
また、必要な能力としてコンプライアンス知識があげられ、薬事法管理者資格保有者が歓迎されているのが現状です。
薬事法管理者資格を取得することのメリット・デメリット
薬事法管理者資格は、必要な努力を重ねれば確実に目指すことができる資格です。
しかし、その知名度の低さや取得プロセスの複雑さから、時間がかかってしまう可能性があります。
そこで、本章では資格を取得することのメリットとデメリットをまとめてみました。
薬事法管理者資格取得のメリット
薬機法規制にも負けない
美容や健康業界では、薬機法や景品表示法などの法規制が厳しくなっているため、これらの規制を理解し、適切に対応することが求められています。
資格取得によって証明される専門性は、日々の業務はもちろん、今後のキャリア形成にも大きく貢献します。法規制に関する知識は、業界で価値の高いスキルとなっていくでしょう。
このように、資格を持っておくことで自身の市場価値の向上とキャリアアップにつなげることができるのです。
社内での評判が上がる
薬事法管理者資格は、個人のスキルアップにとどまらず、企業内での評価向上にもつながります。法管理者は、法令遵守に関する専門知識を持ち、広告制作や商品開発などの現場で法令違反のリスクを事前に回避できます。
例えば、広告のキャッチコピーに薬機法に違反する表現が含まれていた場合、薬事法管理者がそれを指摘し修正を求めるという役割を果たせます。
また、化粧品や健康食品の開発においても、薬事法管理者が商品企画から販売に至るプロセス全体を管理することで、製品の品質と安全性を確保することができます。
フリーランスとしてライターとしての仕事で単価が上がる
現時点でライターとして働いている人にとっても、薬事法管理者資格の取得は大きなチャンスとなります。
株式会社メディアエクシードが運営している「資格広場」によると、この資格を持つライターは作業単価が約20倍以上になる可能性があるそうです。たとえば、通常は一文字10円の案件でも、高額報酬の仕事に応募できるかもしれません。
医療や化粧品などの特定分野で働かなくても、ライターとしての活躍の場が用意されていると言えます。
薬事法管理者資格取得のデメリット
知名度が低い
薬事法管理者資格は一般的には知名度が低く、その専門性や価値が広く理解されていない点がデメリットです。
資格保有者の能力が適切に評価されにくいため、業界内でしか価値が認められず、「知る人ぞ知る」資格という側面があります。
講座を受講しなければ受験資格がない
薬事法管理者資格を取得するには、一定の準備が必要です。
受験には、薬事法有識者会議が認定する講座の修了が義務付けられており、この講座は短期間では終わらず最短でも3か月を要します。また、講座費用として59,800円がかかります。
独学で資格を取得したいと考える場合は、時間と費用の負担が大きくなる可能性があるという点においてデメリットと言えます。
しかし、資格取得にはある程度の覚悟が必要ですが、将来的には大きな強みとなります。
薬機法管理者まとめ
本記事では、薬機法管理者とコスメ薬事法管理者の役割の違いについて解説しました。
両者は法令順守を担う重要な存在ですが、専門分野が異なっています。
薬機法管理者は医薬品や医療機器に関する規制を、コスメ薬事法管理者は化粧品に関する規制を監視する役割を担っています。
双方とも各業界で欠かすことのできない存在であり、軽視されるべきではありません。